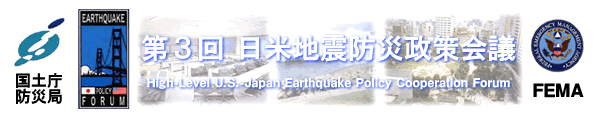 | ||
| 目次 日本における耐震改修技術の概要について | 国際消防救助隊について(1) | |
| ■国際消防救助隊 昭和60年11月14日(現地時間13日)に発生したコロンビアのネバド・デル・ルイス火 山の噴火による泥流災害に際して、救助隊の派遣について意向打診が外務省から消防庁に 対して行われた。この援助活動は実現には至らなかったが、消防庁では、こうした活動に は国際協力の一環として積極的に対応することとし、昭和61年に国際消防救助隊 (International Resque Team of Japanese Fire-Service 略称“IRT-JF“愛称“愛ある手“) を整備したところである。その後、政府は外務省を中心に、海外で大災害が発生した場合 の国際緊急援助体制の整備を進め、昭和62年9月に「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」が 公布施行された。この法律は、海外の地域における大規模災害時に、被災国政府等の要請に応じて実施す る総合的な国際緊急援助体制の整備を図ることを目的としたものであり、消防庁長官は、 外務大臣からの協力要請及び協議に基づき、消防庁職員に国際緊急援助活動を行わせると ともに、消防庁長官の要請を受けた市町村はその消防機関の職員に国際緊急援助活動を行 わせることができることとなった。 国際緊急援助隊の一部を構成する国際消防救助隊は、全国40消防隊、501名の救 助隊員から構成されており、世界のトップレベルの救助技術を有する救助隊員として、これ まで11回海外において救助活動や支援活動を行っている。近年では、トルコ西部における 地震災害や台湾地震災害において迅速に出動し、高度な資機材を用いて救出活動をした ところである。 消防庁では、今後とも他の機関と連携しながら国際消防救助活隊の派遣体制についてより 一層の充実を図るとともに、登録隊員に対する教育訓練の充実を図っていく。 国際消防救助隊の活動 平成11年に入ってから、都市近郊における地震が多数発生し、特に1月に発生した 南米のコロンビア共和国、8月にトルコ共和国、そして9月に台湾で発生した地震は、多くの 建物が倒壊し多数の死者が発生するなど、大きな被害をもたらした。 これらの地震により、各被災国等から我が国に対し、救助活動の要請がなされたことから、 消防庁では国際消防救助隊を派遣し、活動を行った。 これらの派遣に当たっては、電磁波により人間の拍動を読みとり生存者を発見する装置や、 狭い隙間に小型カメラを入れて観察する機材など、現在の科学技術を応用した高度な 資機材を携行した。それらの資機材による人命検索活動は、各被災国から大きな期待が寄 せられた。 本稿では、平成11年中にコロンビア共和国、トルコ共和国及び台湾で発生した地震に関し 救助活動の概要を紹介する。 | ||
| |
