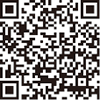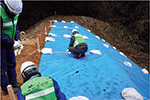第4節 政策対応
(1)支援制度等の適用等
<1>災害救助法の適用
新潟県、富山県、石川県及び福井県の計35市11町1村に災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された(法適用日令和6年1月1日)。国庫負担により、各県が実施する応急的な救助(避難所の設置・運営、応急仮設住宅の供与等)が実施された。なお、令和6年9月20日からの大雨についても石川県の3市3町に同法が適用された(法適用日令和6年9月21日)。
<2>激甚災害の指定
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づき、令和6年1月11日に指定政令の閣議決定を行い、激甚災害(地域を限定しない本激)に指定した。これにより、公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例等、合計12の措置が適用された(令和6年2月9日の閣議決定による追加指定含む。)。なお、令和6年9月20日からの大雨についても同年10月25日に指定政令の閣議決定を行った。
<3>特定非常災害の指定
特定非常災害の指定については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づき、令和6年1月11日に指定政令の閣議決定を行い、令和6年能登半島地震による災害を特定非常災害として指定するとともに、本特定非常災害に対し、行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置、期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置、債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置、相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置、民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置を適用した。
<4>大規模災害復興法に基づく非常災害の指定
大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号。以下「大規模災害復興法」という。)に基づき、令和6年1月19日に指定政令の閣議決定を行い、令和6年能登半島地震による災害を非常災害として指定した。これにより、被災した港湾(七尾港等8港湾)、空港(能登空港)、海岸(宝立正院海岸等3海岸)、農地地すべり(稲舟地区)、農地海岸(石崎海岸等7海岸)、民有林(興徳寺地区等5区域9か所)、漁港海岸(鵜飼漁港海岸)、漁港(狼煙漁港(狼煙地区))の災害復旧工事及び地すべり対策(国道249号の沿岸部)について、地方公共団体に代わって国が権限代行により実施した。
<5>生活の再建に向けた措置
令和6年1月6日に石川県は全域(19市町)に被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の適用を決定、その後も富山県(全域(15市町村))、新潟県(全域(30市町村))が同法の適用を順次決定した。これにより、住宅が全壊等の被害を受けるなど一定の要件に該当した場合に、当該住宅に居住していた被災世帯に対し、住宅の被害状況に応じて、基礎支援金(最大100万円)及び住宅の再建方法に応じた加算支援金(最大200万円)が支給された。なお、令和6年9月20日からの大雨についても、石川県は同年10月9日に輪島市及び珠洲市に同法の適用を決定した。
くわえて、能登地域の6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)では、他の地域と比べて特に被災状況が深刻であるとともに、高齢化率が著しく高いことのみならず、家屋を建設できる土地が極めて少ないなど、半島という地理的な制約があって、住み慣れた地を離れて避難を余儀なくされている方も多い。そのため、地域コミュニティの再生に向けて乗り越えるべき、大きくかつ複合的な課題があるという実情・特徴を踏まえ、当該地域において、住宅半壊以上の被災をした高齢者・障害者のいる世帯、資金の借入や返済が容易でないと見込まれる世帯を対象として、石川県が最大300万円の給付を行う新たな交付金制度(地域福祉推進支援臨時特例交付金)が創設され、対象世帯に支給された。
また、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき、災害による死者の遺族に災害弔慰金、災害により重度障害を負った方に災害障害見舞金が支給されるとともに、要件に該当する世帯主に災害援護資金の貸付が実施された。
(2)被災地、被災地方公共団体等への広域応援
今般の災害においては、被災者支援、被災地方公共団体支援等のため、被災地外から数多くの機関が支援に駆けつけた。
前節で述べたとおり、救出・救助等のため警察(警察災害派遣隊)、消防(緊急消防援助隊)、自衛隊、海上保安庁の各部隊が被災地に派遣され、保健・医療・福祉分野においてもDMAT、DPAT、JMAT、日本災害歯科支援チーム(JDAT)、日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)、DHEAT、保健師等チーム、日本環境感染学会の災害時感染制御支援チーム(DICT)、日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)、災害派遣福祉チーム(DWAT)ほか、災害支援ナース等の看護師や介護職員など医療・福祉に携わる多くの職員が被災地に派遣された。
また、公共土木施設等の被災状況調査や道路啓開のほか、緊急避難輸送、緊急物資輸送などの輸送の支援や被災建築物の応急危険度判定のため、国土交通省の緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)が派遣されたほか、農林水産省サポート・アドバイス・チーム(MAFF-SAT)など各省庁においても各分野における災害復旧や被災者支援のための専門組織が派遣された。
被災地方公共団体に対する全国の地方公共団体からの広域応援も大規模に実施された。被災地方公共団体の災害マネジメント支援のため能登地域の被災6市町に6県市より総括支援チームが派遣されるとともに(6月21日まで)、石川県内14市町、富山県内3市及び新潟県内1市に対して、63都道府県市から対口支援方式(カウンターパート方式)による支援チームの派遣(避難所の運営・罹災証明書の交付等の災害対応業務を担う職員の派遣)が行われた(8月4日まで)。また、インフラ・ライフラインの応急対応や復旧に関しても、水道、電気、通信等において全国からの応援派遣が行われたほか、被災地の水道が長期にわたり断水状態となったため、全国の地方公共団体等から給水車やトイレトレーラーの派遣も行われた。
なお、発災当初から多くの応援地方公共団体職員、復旧事業者、ボランティア等の支援者が被災地に入り、多岐にわたる支援を実施したが、被災地ではホテル・旅館等も大きな被害を受け、宿泊施設が不足した。このため、石川県等において、特別交付税措置や独立行政法人中小企業基盤整備機構の仮設施設整備支援事業等も活用し、支援者のための宿泊施設の確保・充実に努めるなど、支援者支援を実施した。
(3)支援パッケージと財政措置、税制上の対応
政府は、令和6年1月2日、内閣総理大臣決定により、内閣官房副長官を長とし、各府省庁事務次官等を構成員とする「令和6年能登半島地震被災者生活生業再建支援チーム」を開催し、被災者の生活や生業の再建を迅速かつ円滑に支援することとした。同支援チーム等における検討の成果を基に、令和6年1月25日に「生活の再建」「生業の再建」「災害復旧等」の分野ごとに政府として緊急に対応すべき施策を「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」(令和6年能登半島地震非常災害対策本部決定。以下「支援パッケージ」という。)として取りまとめ、公表した2。
また、政府は、発災時点において残額が4,600億円を超えていた令和5年度予算の一般予備費等を活用し、変化する財政需要に対して機動的に対応した。具体的には、まず、令和6年1月9日に当面のプッシュ型の物資支援への財政的裏付けとして予備費の使用(約47億円)を決定した。そして、支援パッケージの施策の実施のため必要となる財政措置として、令和6年1月26日に1,553億円、同年3月1日に1,167億円、同年4月23日に1,389億円、同年6月28日に1,396億円の予備費の使用等を決定した。なお、能登半島地震に関する予備費使用については、このほかにも令和6年9月10日に1,088億円、同年10月11日に509億円、令和7年2月28日に1,068億円が決定され、能登地域の復旧・復興に向けた予備費の使用額は累計8,217億円となった。特に令和7年2月28日に決定された予備費では、能登の創造的復興に必要となる施策に対して柔軟かつ機動的に対応できるよう、自由度の高い交付金として「能登創造的復興支援交付金」500億円を措置した。くわえて、令和6年12月17日に成立した令和6年度補正予算では、令和6年能登半島地震及び豪雨災害の復旧・復興に向けた取組として、生活の再建1,062億円、生業の再建188億円、災害復旧等1,434億円の合計2,684億円が措置されたほか、令和7年度当初予算においても、引き続き、被災者の生活・生業の再建支援やインフラ復旧など、被災地のニーズに切れ目なく対応していくこととしている。
被災地方公共団体に対する地方財政措置としては、まず、令和6年1月9日に石川県及び県内17市町を始めとする51団体、さらに、同年2月9日に石川県及び県内7市町に対して、当面の資金繰りを円滑にするため、同年3月に交付すべき特別交付税の一部(261億400万円)を繰り上げて交付することを決定した。その上で、令和6年3月22日には令和5年度特別交付税の交付決定を行い、このうち令和6年能登半島地震の災害関連経費分は402億円となった。また、応援職員等の宿泊場所を石川県が一元的に確保する場合の費用に対する新たな特別交付税措置や、上下水道の災害復旧事業及び隣接住宅地も含めてエリア一体的な液状化対策を講じる「宅地液状化防止事業」に対する地方財政措置の拡充なども実施した。また、令和6年6月25日には令和6年能登半島地震復興基金の設置のため、石川県に対し特別交付税520億円を措置した。
税制に関しては、所得税等の申告・納付等の期限の延長を講じたほか、令和6年2月21日に成立(同日公布・施行)した「令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(令和6年法律第1号)等に基づき、住宅・家財等の資産の損失の令和5年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の計算における雑損控除の適用、災害減免法の特例による令和5年分の所得税の減免、事業用資産の損失の令和5年分の所得税の計算上の必要経費への算入を可能とする等の措置を実施した。
このほか、個人住民税が全額免除される水準となった被災者を含む世帯について、非課税世帯等への物価高対策支援(合計10万円/世帯。こども加算5万円/人)の対象とすることとした。
(4)被災地に寄せられた善意の支援への対応
石川県においては、被災された方々へのお見舞いとして寄せられた義援金(令和6年10月14日時点で約756億円)を公平に配分するため、石川県令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金配分委員会を設置し、同年2月1日の第1回委員会以降、第一次から第四次までの配分計画を決定した。これにより、石川県においては、死者・行方不明者180万円、災害障害者90万円、重傷者10万円、住家全壊180万円等の義援金の配分が決定され、令和7年1月末現在、人的・住家被害について約10.8万件、約403億円が配分済みとなっており、このほか6市町の全住民に一律5万円が給付された特別給付分について約12.4万人、約62億円が配分済みとなっている3。また、新潟県、富山県、福井県においても同様に義援金配分委員会の決定に基づく義援金の配分が決定され、被災者に配分された。
(5)復旧・復興への対応
<1>令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部
政府は、令和6年1月31日に、能登半島地震からの復旧・復興を関係省庁の緊密な連携の下政府一体となって迅速かつ強力に進めるため、内閣総理大臣を本部長、全閣僚等を本部員とする「令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部」(以下「支援本部」という。)を設置した。具体的には、令和6年1月25日の支援パッケージの取りまとめを受け、支援本部において、<1>各府省の復旧・復興に向けた進捗状況の確認、<2>各府省の施策の整合性の確認、<3>予備費の執行等に係る連絡調整等を行うこととされた。支援本部は令和6年2月1日以降計12回開催され(令和7年4月1日現在)、被災地のニーズを受け止めながら、機動的・弾力的に予備費等を活用し、インフラ・ライフラインの復旧、被災者・被災事業者支援等により復旧・復興を推進している。このうち、令和6年8月26日に開催された第9回支援本部では「能登半島地震の教訓を踏まえた災害対応の強化(基本的な方向性)」が提示され、政府の災害対応体制の強化、被災者に寄り添った支援体制の強化、初動対応などにおける連携強化の方向性が打ち出され、特に司令塔機能の強化、国の応援組織の充実強化、避難所の環境整備の更なる推進、福祉対応体制の強化、専門ボランティア団体等との連携強化については法改正も視野に制度改正を検討することとされた。
<2>石川県の対応
一方、石川県においても、能登半島地震の被災地の創造的復興に向けた各種の取組について、政府とも連携しながら県庁内の調整を図り、推進するために、令和6年2月1日に知事を本部長とする「石川県令和6年能登半島地震復旧・復興本部」を設置し、同年6月には「石川県創造的復興プラン」を取りまとめ、公表した。同プランでは、「能登が示す、ふるさとの未来」を創造的復興のスローガンとして掲げ、県成長戦略の目標年次である令和14年度末までの9年間を計画期間として2年後の短期、5年後の中期、9年後の長期の区分により、「地域が考える地域の未来を尊重する」「あらゆる主体が連携して復興に取り組む」「若者や現役世代の声を十分に反映する」など12の基本姿勢に基づき、創造的復興リーディングプロジェクトを始めとする取組を通じて、創造的復興を成し遂げることとしている。特に、復興プロセスを生かした関係人口の拡大や能登サテライトキャンパス構想の推進など13の象徴的プロジェクトを「創造的復興リーディングプロジェクト」と位置付け、復興の成功事例として創出し、活力あふれる能登を蘇らせる創造的復興の象徴として県内外に発信していくこととしている。
また、石川県では、復興基金創設のために交付された特別交付税520億円に、能登半島地震被災地宝くじの収益金の半分に相当する約19.8億円を加え、総額約539.8億円の復興基金を創設した。復興基金では、市町からの要望を踏まえ28事業を基本メニューとしてメニュー化したほか、市町枠配分として市町が地域特有の課題に早期かつ機動的に活用できるよう、各市町の住家被害、災害復旧事業費、避難者の受入数等に応じて配分した。
さらに、復興のためのノウハウやマンパワー不足、資金確保などの課題に対し、地域団体等に伴走し、全国からの様々な支援を効果的に結びつけるコーディネート的役割を担う中間支援組織として、石川県と能登6市町で「一般社団法人能登官民連携復興センター」を設立し、令和6年10月21日から活動を開始した。
<3>能登創造的復興タスクフォース会議
石川県が策定した「石川県創造的復興プラン」の方針に沿って、能登の6市町の復興まちづくりを本格化していくためには、国・県・市町の関係者が緊密な連携を図り、事業の進捗確認や現場で生じた課題の解決に取り組むことが必要であり、また、被災地である能登地方には、国土交通省の能登復興事務所を始め関係省庁及び関係機関が現地事務所等の設置や、職員の派遣等により、復旧・復興の支援体制を強化しており、こうした関係機関と石川県・6市町の連携体制を一層強化し、創造的復興を進めていくため、政府では、内閣官房の復旧・復興支援総括官(能登半島地震への対応を強化するため令和6年4月1日に新設)を座長、石川県知事を座長代理とする「能登創造的復興タスクフォース会議」を7月1日以降計7回開催している(令和7年5月現在)。同タスクフォース会議では、公費解体の推進、復興まちづくり、生業再建、インフラ復旧等の復旧・復興に関する諸課題について検討し、復興を進めている。
<4>復旧・復興を支援する現地の体制
国では、能登地域の復旧・復興を支援していくため、令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部や能登創造的復興タスクフォース会議に加え、関係省庁・関係機関でも現地の支援体制を充実してきた。
国土交通省では、復旧・復興を加速化し、強力に推進していくため、令和6年2月16日に北陸地方整備局の組織として「能登復興事務所」、金沢港湾・空港整備事務所内に「能登港湾空港復興推進室」を七尾市内に設置した。両事務所では復旧・復興に向けた河川事業、砂防事業、海岸事業、道路事業、港湾事業、空港事業に取り組んでいる。さらに、令和6年4月1日には国土技術政策総合研究所の組織として「能登上下水道復興支援室」を七尾市内に設置し、上下水道一体の災害対応や被災自治体への支援に取り組んでいる。
農林水産省北陸農政局では、復旧・復興に向けて、七尾市、輪島市及び穴水町の海岸施設災害復旧工事、輪島市の地すべり防止工事及び珠洲市のダム復旧工事に関し、国が権限代行などにより行う一連の調査・工事を迅速に進めるため、令和6年4月1日に「能登半島地震災害復旧現地事務所」を穴水町に設置した。
林野庁近畿中国森林管理局では、復旧対策の円滑な事業実施のため、石川森林管理署に「奥能登地区山地災害復旧対策室」を設置し、金沢市(石川県農林総合研究センター内)に事務室を開設した。
水産庁では、水産関係対策の現地対応力を強化するため、令和6年3月22日に「水産庁石川県現地事務所」を金沢市に開設した(令和6年4月12日に穴水町へ移転)。
総務省では、生活支援情報の提供(詳細はコラム参照)や被災者からの相談対応などの被災者支援を強化するため、本省及び全国の行政相談センターから金沢市内の石川行政評価事務所に応援職員を派遣した。
株式会社地域経済活性化支援機構(REVIC)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が、被災した事業者の二重債務問題に対応するため、石川県や地域金融機関等と共同で「能登半島地震復興支援ファンド」を設立したことに伴い、令和6年4月1日に公益財団法人石川県産業創出支援機構内に「能登産業復興相談センター」を開設し、同日から、能登半島地震における被災事業者への復旧・復興に向けた資金繰り支援を始めとする各種相談対応を行っている。さらに、奥能登地域の被災事業者への相談体制を拡充するため、令和6年6月3日に能登空港内に「能登産業復興相談センター 奥能登サテライトオフィス」を開設し、同日より、能登半島地震からの復旧・復興に向けた資金繰り支援を始めとする各種相談対応を行っている。
独立行政法人都市再生機構(以下「UR」という。)では、被災自治体の復興支援のため、令和6年4月16日に「能登半島地震復興支援室石川事務所」を金沢市内に設置した。
<5>令和6年9月20日からの大雨への対応
能登半島の被災地では、令和6年9月20日からの大雨により、応急仮設住宅222戸で床上浸水が発生した。こうした水害による被害についても、石川県及び被災市町による取組のほか、国も令和6年能登半島地震及び豪雨災害に係る補正予算として2,684億円を計上したほか、上記復旧・復興支援本部、タスクフォース会議等の枠組みにより支援してきた。令和6年10月6日から令和7年3月31日まで、企業・業界団体の御協力の下、被災地に温かい食事を提供できるよう、延べ約700台のキッチンカーを派遣した。
2 内閣府ホームページ「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」
(参照:https://www.bousai.go.jp/pdf/240125_shien.pdf)

3 石川県ホームページ「令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金配分委員会について」
(参照:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/gienkinbussi/r6notohantoujishingienkin.html)