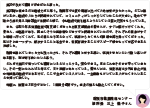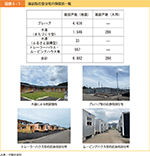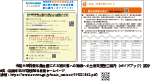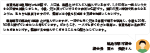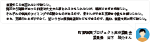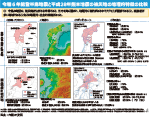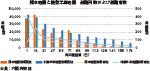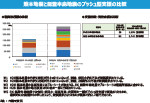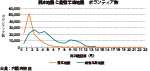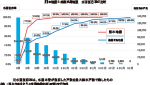第6節 被災者支援
(1)避難生活・応急仮設
被災地では発災直後より多くの被災者が長期にわたる避難生活を送ることとなり、発災直後(令和6年1月2日5時現在)は、1道1府9県の約1,300か所の避難所が開設され、避難者数は5万人を超えた。翌3日6時現在では、新潟県、富山県、石川県の3県で約480か所の避難所が開設され、約3万人が避難していた。避難者数は被災地のライフライン復旧や仮設住宅建設が進むにつれて減少し、被害の大きかった石川県でも令和7年3月末にて全ての避難所が閉鎖している。
能登地域の被災地では、道路の寸断により多くの孤立集落が発生したほか、上下水道や電気等のライフラインの被害により日常生活を送ることが困難となり、石川県において被災者を環境が整った県内外のホテル・旅館等に避難(2次避難)させた。令和6年2月16日現在で最大5,275人が避難し、同年12月24日現在では全ての2次避難所において避難者数が0となった(累計11,817人)。また、いしかわ総合スポーツセンター(金沢市内)等に一時的な避難所(1.5次避難所)が開設され、高齢者等の要配慮者を中心に最大で367人(令和6年1月21日時点)の避難者を受け入れた。1.5次避難所は令和6年9月30日18時で閉鎖した(累計1,501人)。
石川県においては、支援を必要とする被災者の把握及び孤立防止のため、民間支援団体と連携の上、被災生活により状態の悪化が懸念される在宅高齢者等に対して個別訪問等を実施し、早期の状態把握、必要な支援の提供へのつなぎ等を行う被災高齢者等把握事業を令和6年2月から6月まで実施した。また、被災者見守り・相談支援等事業において、被災者が応急仮設住宅に入居するなど、異なる環境の中にあっても、安心して日常生活を営むことができるよう、孤立防止等のための見守り支援や、日常生活上の相談を行った上で、必要に応じて専門の相談機関へつなぐなどの支援を実施した。
災害を乗り越えるためには(珠洲市健康増進センター)
令和6年能登半島地震の災害支援において、珠洲市保健医療福祉調整本部長を務めた珠洲市健康増進センター所長 三上 豊子(さんじょう とよこ)さん。発災後、炊き出し、入浴支援、生活全般の調整を一手に担う。また、被災高齢者等把握事業の陣頭指揮を執り、4月からは復旧・復興本部被災者支援部会長も兼務。珠洲市において被災者支援の中核を担い、ここまで御尽力されてきた三上さんからメッセージをいただいた。
被災地では16万棟を超える住家が被害を受け、被災者の住まいの確保が喫緊の課題となった。特に甚大な被害を受けた奥能登地域では、応急仮設住宅の建設に適した平地が限られることに加え、建設工事従事者のための宿泊拠点が少なく、また、水道等のライフライン復旧にも時間を要する中、住まいの確保に向けた取組が進められた。
住宅再建の前提となる被害認定調査や罹災証明書発行のため、内閣府では、令和6年1月13日に罹災証明書の申請や被害認定調査の実施に関する留意事項(外観調査の簡素化、写真等を活用した判定、空中写真等を活用した一括全壊判定による迅速化など)を示し、調査や交付の迅速化に関する周知を図るとともに、その後も迅速かつ適切に被害認定調査及び罹災証明書の交付が行われるよう、新潟県、富山県及び石川県内の関係市町村に対し助言した4。このほか、1.5次避難所等においても罹災証明書の交付手続ができるよう窓口が設けられたほか、マイナンバーカードを利用してマイナポータルから罹災証明書の発行を申請できるなどオンライン申請の取組が各地方公共団体で進められている5。
被災した方々に対する応急的な住まいに関する支援としては、「応急仮設住宅(建設型)」の他に、民間賃貸住宅を借上げて供与する「賃貸型応急住宅」、「公営住宅等の提供」等があり、石川県が県内外の地方公共団体や国と連絡調整を行い、地域の実情、提供までに要する時間等を総合的に勘案しながら、順次、応急仮設住宅等を提供してきた。応急仮設住宅(建設型)は、令和6年1月12日に輪島市と珠洲市で、同月15日からは能登町と穴水町で着工した。同年12月23日に応急仮設住宅(建設型)は必要戸数6,882戸の全てが完成した。今回の災害では、ムービングハウス、トレーラーハウスなどの移動型車両等が積極的に活用されている。また、石川県は従来型のプレハブ建設を進めるとともに、救助期間の終了後も市町の公有住宅として恒久的に使用することができる木造仮設住宅の建設を進め、里山里海景観に配慮した長屋型の木造仮設住宅(まちづくり型)や地元集落を離れた方がふるさとに回帰することを目的とした戸建風の木造仮設住宅(ふるさと回帰型)を積極的に建設した。
石川県は民間賃貸住宅を活用した賃貸型応急住宅(みなし仮設)の提供を進めており、令和7年3月31日時点の入居戸数は3,073戸(ピーク時は3,792戸、令和6年8月1日現在)となっている。また、石川県の近隣県である新潟県、富山県及び福井県においても賃貸型応急住宅が提供された。
国土交通省は、令和6年12月16日時点で、即入居可能な公営住宅等を全都道府県において約9,400戸確保し、入居済み戸数は約1,110戸となっている(最大1,110戸、12月16日現在)。また、高齢者が安心して暮らせるよう各種相談等に対応する「生活支援アドバイザー」を配置したUR賃貸住宅を全国で300戸確保した。また、財務省は、同年11月5日時点で、北陸4県の即入居可能な国家公務員宿舎等の情報として、新潟県107戸、富山県188戸、石川県139戸及び福井県101戸を提供しており、石川県の要請を受け、石川県の国家公務員宿舎104戸の使用を許可した。
また、令和6年9月の大雨により、輪島市内の5団地(199戸)、珠洲市内の1団地(19戸)の仮設住宅において床上浸水したことから、これら6団地において復旧工事を行い、令和6年12月26日に全ての復旧工事が完了した。さらに、この大雨に伴う応急仮設住宅の新規建設について、令和7年3月28日に必要戸数286戸全てが完成した(図表6-1)。
被災者に生活支援情報を届けるためのガイドブック
従来、地震や豪雨等による災害が発生した被災地では、国や地方公共団体などが被災者支援の取組を行っていても、各々がそれぞれ情報を発信しており、被災者に必要な情報が届きにくいという課題があった。そこで、総務省行政評価局では、被災者向けの生活支援情報を一冊に取りまとめたガイドブックを作成し、被災者の方々に配布する活動を行っている。
ガイドブックには、罹災証明書の発行や住宅の応急修理制度、生活福祉資金の貸付など、発災後に寄せられるお困りごとに関連する国や地方公共団体などの行う支援の内容と問合せ先を掲載しており、令和6年能登半島地震では、発災直後の1月10日に石川行政評価事務所のホームぺージに公表するとともに、紙媒体を避難所や自治体、郵便局や社会福祉協議会などに届け、令和7年3月末までに約8.4万ダウンロード、約2.1万部を配布している。
ガイドブックの取組は、令和6年能登半島地震の対応の振り返りや課題・教訓の整理を行った「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ」の報告書において、
○ 全省庁の支援制度を網羅的に一つにまとめたガイドブックは被災者にとって有用であり、また紙媒体は被災地で活用しやすいという評価があった。
○ 今後、被災者に対して各種支援情報をより迅速かつ正確に提供できるよう、平時から国と自治体が連携し、被災者支援制度についてのガイドブックの掲載内容をあらかじめ標準化しておくべきである。また、同ガイドブックを、国・自治体共通の被災者への情報発信ツールの基盤と位置づけ、相互に活用することを検討すべきであるとされた。
総務省では、当該報告書を踏まえ、平時から自治体と連携を強化し、ガイドブックを自治体にも活用してもらうなど、国・自治体共通の情報発信ツールにするなどの取組を進めていく。
(2)ボランティアの取組
発災以降、避難所運営や重機によるがれき撤去などの被災者支援を専門とする400を超える専門性を持ったNPO等が被災地に入り、活動を行っている。また、令和6年1月2日からNPO法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)が石川県庁に入り、専門性を持ったNPO等、行政、社会福祉協議会等との情報共有会議を通じた情報共有、活動調整を行っている。
また、被災地の社会福祉協議会が主体となって、各市町に災害ボランティアセンターが設置されたことにより、ボランティア希望者の受付、刻々と変化する被災者のニーズとボランティアを結び付けるマッチング等が実施され、被災した住宅の片付けや災害ごみの分別・運搬等の活動が行われている。
今般の災害では、発災当初は被災地へのアクセス道路が限られることによる渋滞の発生や、被災地内での宿泊場所の不足等から、一般ボランティアが直接被災地入りすることを控えていただきたい旨の呼び掛けが石川県等からなされた。その後、石川県は国や関係機関と連携しつつ、県の特設サイトにおいてボランティア活動希望者の登録を受け付け、被災者の要望(ニーズ)と個人ボランティアの調整(マッチング)を行うほか、被災地内における宿泊拠点の確保を進めるなど、ボランティア等支援者の活動環境の整備に取り組んだ。また、道路状況の改善や各市町における一般ボランティアの受入れ体制が整ったこと等もあり、その後はボランティアの受入れが進んだ。令和7年3月17日までのボランティアの活動人数は石川県約17万人、富山県約5千人、新潟県約2千人と延べ約18万人となった(全国社会福祉協議会調べ)。
(3)災害廃棄物の処理等
今回の地震及び令和6年9月の大雨による被災家屋からの片付けごみ、全壊・半壊建物の解体に伴う災害廃棄物の発生量は、本年1月に石川県が「公費解体加速化プラン」を改定、解体棟数の見直しが行われており、災害廃棄物発生量の推計は約410万トンとされている。
被災地の復旧・復興のためには損壊家屋の早期解体を進める必要があり、申請に基づき市町が所有者に代わって解体・撤去する公費解体が進められている。特に被害の大きい石川県内の6市町等では公費解体の申請受付・契約事務の加速化のために、災害廃棄物処理の知見・経験を有する環境省職員や地方公共団体職員によるマネジメント支援とともに、応援地方公共団体職員派遣により、申請受付等の支援を行ってきた。被災自治体の災害廃棄物処理を支援する「災害等廃棄物処理事業費補助金」について、令和6年能登半島地震が特定非常災害に指定されたことを受け、損壊家屋等の公費解体・撤去において全壊家屋に加えて半壊家屋を支援の対象とするとともに、本補助金の国庫補助率1/2及び地方負担額に対して95%の特別交付税措置を講ずるほか、被災自治体の財政力に鑑みて災害廃棄物処理の財政負担が特に過大となる場合に、県が設置する基金を活用して地方負担額を軽減することにより、円滑・迅速な災害廃棄物処理を推進している。
石川県の被災市町においては、令和6年9月の大雨や令和7年の大雪の影響に伴い一時解体作業に遅れが生じたものの、本年3月末現在での公費解体の進捗状況は、解体見込棟数39,235棟に対し、申請棟数は38,825棟、解体完了棟数は22,485棟となっている。解体事業者の解体工事体制の充実・強化として600班規模体制から1,200班規模体制に増強し、大量に発生する解体ごみの鉄道輸送や海上輸送などにより広域処理の拡充を図るなど、石川県災害廃棄物処理実行計画の目標年次である令和7年10月の原則解体工事完了を目指し、公費解体の推進を図っている。
(4)復興まちづくり
石川県では令和6年能登半島地震からの創造的復興に向けた道筋を示すため、「石川県創造的復興プラン」を令和6年6月に策定した。国土交通省では、本計画を受けて被災市町における復興まちづくりを支援するため、被害状況の把握や住民アンケート等直轄調査を令和6年3月から順次実施することにより復興まちづくり計画の策定を支援するとともに、令和6年4月からは国土交通省職員による地区担当の配置、URによる技術的支援、関係省庁連携による横断的支援等を実施してきた。
また、令和6年8月以降、先行的な復興プロジェクトとして「仮設店舗の立地」や「輪島朝市カムバックイベント」等が実施され、令和6年9月にURは奥能登地域で更なる支援強化のための拠点として、輪島市役所内に「UR 奥能登・輪島ベース」を設置した。
令和6年度末までに奥能登地域の全市町において「復興まちづくり計画」が策定され、今後、本計画に基づき、事業の具体的検討が進められることとなるため、引き続き、復興まちづくりを支援していく。
輪島朝市の復興に向けて
令和6年能登半島地震により、本町商店街朝市通りで火災が発生。毎年1月4日に初売りを行っていたが、地震と火災のせいで今後の見通しが全く立たない状況となった。組合員の多くが金沢市に避難していた中で、輪島朝市の開催の想いは強く、「金沢で朝市を開催できないか」という声があがった。昔から輪島港とつながりのあった金沢市の金石港で、多くの方々から御支援いただき、令和6年3月23日に最初の「出張輪島朝市」を開催し、約30店舗が出店、一日だけで約13,000人の方々に来ていただいた。また、輪島市内では令和6年7月10日から市内のショッピングモールで出張輪島朝市を開催し、現在も水曜日定休日以外は約40店舗が出店している。
「出張輪島朝市」はこれまでに(令和6年12月末現在)全国約90か所で開催させていただいた。毎回約10~20店舗が参加している。嬉しいことにオファーはその倍以上もあった。また、今回の出張輪島朝市の開催を通して、輪島市と関係がある方や昔からの顧客の方など、人とのつながりを感じた。何度も足を運んでくれる方もいて大変感謝している。
1,200年近く歴史ある輪島朝市を絶やさないという気持ちが強かった。「出張輪島朝市」という名前も元の場所で再開できた時に「輪島朝市」としたいので、各地で開催する朝市は「出張」として冠している。今後も出張朝市はオファーある限り続けていきたい。
復興まではどうしても時間がかかる。ただし、今まで輪島朝市は露店スタイルでしかやったことがなかったが、今回各地で出張朝市を開催させていただき、我々にも出張スタイルのノウハウができてきた。輪島朝市は日本三大朝市として、1970~80年代は200万人いた観光客が、いまは20万人まで減ってきている。今回のピンチをチャンスにして観光客を増やしていきたい。また、輪島市役所からも、市民の憩いの場になってもらいたいとの話もいただいている。復興に当たっては、今までにできた人脈や、出張輪島朝市のノウハウなどを生かして、今後は新しい朝市を展開していきたい。
液状化対策について、国土交通省では、発災以降、TEC-FORCEによる現地調査を実施したほか、国・県・被災自治体による会議などを通じて、液状化対策に関する支援制度や取組事例について情報提供してきた。また、液状化に伴い地表面が横方向に移動する、いわゆる「側方流動(地震で地盤が液状化した際に、地盤が水平方向に移動する現象)」が発生し、顕著な液状化被害が発生した地域等については、被災自治体における液状化災害の再発防止のための対策等の検討を直轄調査等により支援してきた。
くわえて、地方公共団体が実施する、公共施設と隣接宅地等の一体的な液状化対策に対する支援策である「宅地液状化防止事業」について、補助率を通常の1/4から1/2に引き上げるなど、支援策の強化を行い、被災自治体による取組を支援してきた。
令和7年3月現在、顕著な液状化被害を受けた市町において液状化対策を含む復興計画を作成したところであり、早いところでは液状化災害の再発防止対策のための実証実験が進められている。今後、被災自治体において地元住民の合意形成を図りつつ、順次、事業に着手される予定であり、引き続き事業実施に向けた支援を実施していく。
輪島市町野町における復興まちづくりに向けた取組事例
令和6年能登半島地震により、輪島市町野町全体が機能不全に陥った。各家庭に電気、水も来ず、いつ元に戻れるか見通しが立たない状況ではあったが、町野町は少子高齢化の地域であり、このまま何もしなければ地域としてまずいのではないか、そんな思いから地元有志の若者を集めて「町野復興プロジェクト実行委員会」を令和6年2月に立ち上げた。地域の暗い空気を吹き飛ばし、「1日でもいいからみんなで笑える日を作ろう」と考え、地域の人達の「娯楽」として4月には花見イベントとして「さくらフェス」、5月には能登牛の炊き出しイベント「肉フェス」、6月には町野町にこんな施設があったらいいなという声を踏まえて「屋外映画館」を実証実験的に行うなど、毎月のようにイベントを企画してきた。
しかし、町野町が復興に進み始めたそんな最中、奥能登豪雨が発生。また地域の人達の心がくじけそうになってしまうのを感じた。「雪が降る前にまずは豪雨の前の状態に戻したい」という気持ちから、自分たちでボランティアの受入れを始めた。多くの方々の支援のおかげで、町野町は少しずつ復興に向かって進んでいくことができた。
令和7年1月からは輪島市から補助を受けて交通移動支援事業を開始した。また、高齢化の地域では、SNSなども使うのが難しい。情報伝達に一番効率が良いのはラジオと考え、臨時災害放送局の実験放送として1日限りの「まちのラジオ」を行った。インターネット配信も行っており、遠方の方からも応援のメッセージを頂けて、町野町に目を向けていただく良いきっかけとなった。
令和7年4月からは町づくり協議会を立ち上げた。町野町のファンを増やすために、デジタル住民票みたいなものもやってみたいと考えている。また、今後は臨時災害放送局の開局やまちづくり会社に移行して、地ビール工場の設立やログハウスの建設など、プロジェクトのテーマ「わくわく楽しい町野町」を目指して必要なことをやっていきたい。
輪島市門前町における復興まちづくりに向けた取組事例
總持寺(そうじじ)祖院の歴史を伝える「輪島市櫛比の庄禅の里交流館」の管理部長として、輪島市門前町の總持寺通り商店街を拠点に発災前から地域一体となったまちづくりを進めてきた。コロナも落ち着き、今後の新たな展開を考えていた矢先に令和6年能登半島地震が発生。その時は「準備してきたものが全て失われた」と思った。
不幸中の幸いで商店街の人は(怪我などはあったが)全員無事。店も継続してやっていきたいという想いを持つ人が多かった。発災後、支援団体の拠点を交流館に置くことになり、支援団体と地域をつなぐコーディネーター役に。支援とニーズのマッチングが進むことで、令和6年10月に仮設店舗がプレオープン。すでに自身の家で営業を再開している店舗もあったため、あえて3拠点にわけて仮設店舗をオープンすることで、町全体を回ってもらえる仕組みを考えた。
また、総持寺通り協同組合がまちの賑わいにつなげようと令和3年より毎月第2土曜日に開催していた地域イベントの「門前マルシェ」。地震後も再開希望の声も多くあり、令和6年6月に「禅の里交流館」に商品を持ち寄り、出店形式で開催。その後、支援の一環として「門前マルシェ」に併せて演奏会やビアガーデンも開催。「門前マルシェ」の目的は「継続できるように」というお手軽にできる方法で実施していたのが商店街のやり方に合っていた。
地震から1年経ち、ボランティアも減って、町が閑散としてきたイメージがあった。0になってからどうするかを考えても遅い。復興のために何が必要か今から考えていくことが必要と思い、令和6年の秋頃から住民ヒアリングやワークショップを開催。現時点では、ニーズ調査中ではあるが、令和7年度は今後どのようにまちづくりを行っていくか、決める年になると思っている。その一つ目は「ランドリーカフェ」の立ち上げ。コインランドリー、クリーニング屋さんがなく、復興に当たる多くの事業者さんから洗濯が大変という声が、また、発災後、仮設住宅に住むようになって集まりにくくなり、交流の機会が減ってしまったという声が聞かれた。そこで、生活力を取り戻してもらうためにもこれらの願いを叶える手段として「ランドリーカフェ」の立ち上げを計画している。復興までは時間がかかるため、モチベーションを保つためにも今後は1年ごとの目標を設定して達成感を味わいながら復興に向けた取組を進めていければと考えている。
私たち商店街の復興が、住民にとって「希望の光」になると信じて頑張っていきたい。
主要な指標における平成28年熊本地震と令和6年能登半島地震の比較
「令和6年能登半島地震に係る災害応急対応の自主点検レポート」(令和6年能登半島地震に係る検証チーム)においても記載されているように、令和6年能登半島地震ではアクセスの困難等から、比較的規模感の近い震災である熊本地震(平成28年4月14日発災)に比べ、被災者の避難生活等において対応が困難であった部分が多々あり、それらを可視化する観点から、代表的ないくつかの指標により、時系列の比較を行った。
●アクセスを困難とする地理的・社会的要因
能登半島地震が発災した能登半島は、山地が多い半島であり、また、三方を海に囲まれ、地理的に制約がある中で、奥能登へのアクセスルートが遮断され、交通等のアクセスが困難であった被災地であること、また、高齢者が多い地域であることなどの地理的・社会的特徴から、発災直後の避難活動・避難生活に留まらず、その後の復興・再建の段階においても、被災者や被災自治体等にとって厳しく困難な状況となった。
●避難所・避難者数
能登半島地震及び熊本地震における避難所・避難者数を比較すると、発災後1か月程度において、熊本地震では顕著に減少しており、能登半島地震においても、段階的な減少傾向を示しているものの、その傾向は緩やか状況となっている。また能登半島地震では、1次避難のほか、市町の区域を越えた広域避難、2次避難所に移るまでの一時的な滞在を想定した1.5次避難、ホテル・旅館等への2次避難が行われた。
●応急仮設住宅の建設状況
熊本地震では、発災後約7か月(平成28年4月29日~11月14日)で4,303戸を完成したのに対し、能登半島地震では、発災後約5か月(1月12日~5月25日)で4,245戸を完成させていることから、平地が少なく用地確保等の課題がある中においても、熊本地震等の知見を生かしながら、熊本地震の時を上回るペースで応急仮設住宅の整備を行っている。能登半島地震では最終的に、石川県内の10市町で、6,882戸(159団地)の建設型応急仮設住宅が整備された。さらに、災害リスクの残るエリアでの水害(奥能登豪雨)で、応急仮設住宅が被災する事態も生じたが、従来のプレハブ型の住宅以外に、地元の景観に配慮し、恒久的な住まいとして活用可能な長屋型の木造応急仮設住宅や、ふるさと回帰型の応急仮設住宅も整備され、熊本地震と比して、更なる多様な建築様式による住宅が整備された。
●プッシュ型支援の実施状況
能登半島地震では熊本地震の約3倍の期間(82日)において、プッシュ型支援を実施しており、支援額もほぼ倍の額となった。これは、熊本地震における教訓を生かした政府としての積極的対応の結果とも言えるが、支援の日数・執行額が示すように、避難生活が長期にわたり、効果的に物資を支援していく必要性が顕著に生じていたことが伺える。支援物資の内容面を見ても、能登半島地震は寒い時期(1月)に発災したこともあり、プッシュ型支援では初となる燃料の支援を行うとともに、衣類の支援を充実させるなど、被災地のきめ細やかなニーズを踏まえた物資調達と支援が展開された。一方で、多岐にわたる被災者のニーズに対し、一度に全員に行きわたる量を確保できなかったため、被災市町の現地担当者が公平性の観点から物資を配布できなかった事例も見られ、避難生活支援の難しさ(課題)が表面化することも見受けられた。
●ボランティア参加状況
ボランティアの総数は、発災後14か月で比較すると、熊本地震約12万人に対し能登半島地震では約18万人と総数では能登半島地震の方が多いものの、発災後1か月頃までは、能登半島地震は熊本地震の半分以下という状況であった。その背景として、発災当初は、道路事情等により、ボランティアの受入れにも制限を設けることとなったことも要因の一つであると考えられる。その後は熊本地震では発災後3か月目以降は大きく減少するが、能登半島地震では発災後1か月半頃から増加していき、3か月目をピークにその後も一定数もボランティア数が確保され、特に9月の豪雨災害後に再び増加している。
●公費解体の進捗状況
損壊家屋等の公費解体の進捗状況について、能登半島地震と熊本地震ではそれぞれ集計単位が異なるため、一概に比較することはできないが、発災1年後の状況は、熊本地震では約65%(平成29年4月)、能登半島地震では約45%(令和7年1月)である。これは、日本海側最大の半島である能登地域では、アクセスルートが限られることや、過疎地域であり高齢化率が高く、建物の全壊割合が高いなど災害廃棄物処理を進める上での課題が多くあったためと考えられるが、石川県では、公費解体の完了目標を熊本地震とほぼ同程度の、発災から約1年9か月(原則令和7年10月末まで)と設定し、解体計画を策定している。令和6年9月20日からの大雨により解体工事が一時的に中断したものの、現在(令和7年3月末)は、同解体計画を上回るペースで解体が進んでいる。
●水道の復旧状況
令和6年能登半島地震では、熊本地震と比較して、半島地域特有の限られた交通手段が被災したことや悪天候による作業時間の制約等が重なり、水道施設の復旧に長い時間を要した。
4 内閣府ホームページ「令和6年能登半島地震に係る罹災証明書の迅速な交付に向けた留意事項等について」(令和6年1月13日事務連絡)
(参照:https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/tsuuchi_r60113_seirei.pdf)
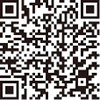
5 デジタル庁ホームページ「【令和6年能登半島地震】罹災証明書(り災証明書)のオンライン申請について」
(参照:https://www.digital.go.jp/2024-noto-peninsula-earthquake)