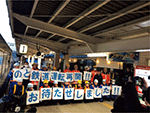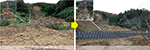第5節 被災地の復旧状況
(1)インフラ被害及び復旧状況
<1>道路
能登半島の大動脈と言われる国道249号を始め、多くの道路に崩落、土砂崩れ、ひび割れ、段差が生じた。特に石川県においては、のと里山海道、国道249号、珠洲道路、七尾輪島線などの県管理道路で87か所が通行止めとなり、奥能登全体が孤立状態とも呼べるようなアクセスが困難な状態に陥った。多くの道路で通行止め等が発生した能登半島では、被災地に流入する車両が一部の道路に集中することにより、各地で渋滞が発生し、支援物資の運搬や復旧作業の支障となった。また、発災直後は道路の通行止めにより33地区最大3,345人が支援を受けられない孤立状態に陥ったため、孤立集落の解消が喫緊の課題となった。
このため、国土交通省では令和6年1月2日から幹線道路の緊急復旧に着手し、1月9日には緊急復旧により半島内の幹線道路の約8割が通行可となり、さらに、1月15日には約9割まで進捗した。これにより、孤立集落は1月19日に実質的に解消した。また、1月23日には権限代行により国土交通省が石川県に代わり本格復旧を代行することを決定し、復旧作業を進め、令和7年2月現在において地震による通行止め箇所は11か所(うち3か所は緊急車両通行可)となった。
一方で、令和6年9月20日からの大雨により、国道249号(沿岸部)を始め、輪島市、珠洲市等の県管理道路で48か所が通行止めとなった。奥能登地域においては大雨により再度被害が発生したものの、従来の目標通り12月には沿岸部を経由した輪島市門前町-珠洲市間の国道249号の通行が可能となった。また、県管理道路等についても、8月末に確保できていた全ての集落・漁港・浄水場等(長期避難箇所に関連するところは除く。)への通行も可能となった。令和7年2月現在において大雨による通行止め箇所は8か所(うち3か所は緊急車両通行可)となった。
<2>空港
能登空港は、滑走路等に多数の亀裂及び灯火等に損傷が生じたため、発災当初は閉鎖されたが、発災翌日からは救援ヘリコプターの受入れを開始し、令和6年1月12日には、救援機の受入れ時間の拡大や滑走路の応急復旧により自衛隊固定翼機の受入れを開始した。1月27日からは能登-羽田間を1日1往復、週3日での民間航空機の運航も再開され、令和6年4月15日からは1日1往復、12月25日からは発災前と同頻度の1日2往復で運航している。また、2月1日には、大規模災害復興法の適用による権限代行により、国土交通省が石川県に代わり本格復旧を代行することを決定し、滑走路等の主要な施設について、利用を確保しながら復旧を進め、令和7年度末までの完成を目指す。
<3>港湾(漁港を除く)
港湾に関しては、新潟県、富山県、石川県、福井県にある29港のうち、計22港湾(七尾港、輪島港、飯田港など)で岸壁や防波堤の損傷等の被害が確認された。特に被害が大きかった能登地域の港湾においては、石川県からの要請により七尾港、輪島港、飯田港、小木港、宇出津港、穴水港の計6港について、令和6年1月2日から港湾法(昭和25年法律第218号)に基づき、港湾施設の一部管理を国土交通省が実施し、各港湾で被災した施設の点検・利用可否判断や応急復旧、支援船等の岸壁の利用調整等を行った(令和6年8月1日終了)。
令和6年2月1日には、石川県、富山県、七尾市からの要請により、上記6港に伏木富山港、和倉港を加えた計8港について、「大規模災害復興法」に基づき、被災した港湾・海岸施設の本格的な復旧工事の一部を国土交通省が代行することとなり、令和6年度内に全ての港湾で本格的な復旧工事に着手した。
<4>鉄道
発災直後、被災した各県で鉄道の運転を見合わせたものの、北陸新幹線、JR北陸線は、令和6年1月2日から運転を再開した。レールのゆがみや支柱の傾斜等が生じたJR七尾線(津幡-和倉温泉)は、1月15日から高松-羽咋間で、1月22日から羽咋-七尾間で、2月15日から七尾-和倉温泉間で運転を再開した。大規模な土砂流入や広範にわたる路盤損傷等、被害の規模が大きかった第三セクターののと鉄道七尾線(和倉温泉-穴水)においては、TEC-FORCEや独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の鉄道災害調査隊(RAIL-FORCE)を現地に派遣し、被災状況調査や事業者に対する技術的助言等の支援を行い、土砂撤去作業の早期着手や土砂搬出作業の円滑化により、2月15日には和倉温泉駅-能登中島駅間で、4月6日には全線で運転を再開した。
<5>土砂災害・河川・海岸
令和6年能登半島地震により、土砂災害が456件発生(石川県424件、新潟県18件、富山県14件)(令和7年1月現在)し、石川県では6河川(14か所)で河道閉塞等が確認された。このうち、不安定な状態で斜面や渓流に土砂・流木が堆積し、今後の降雨により二次災害が発生するおそれが高い石川県河原田川、町野川及び国道249号の沿岸部において、国土交通省による緊急的な土砂災害対策を進めていたところ、令和6年9月20日からの大雨により、石川県内で新たに土砂災害が273件発生した(令和7年2月現在)。この大雨により、石川県からの要請等を踏まえ、国土交通省においては、早急に対策を行う必要がある塚田川(輪島市)等において直轄による砂防工事に着手した。これらの応急対策については、令和7年度出水期までに完了予定としている。また、令和6年12月に公表したスケジュールなどに基づき恒久対策を実施している。
また、令和6年能登半島地震により、国管理河川では4河川、県管理河川では113河川で施設の損傷等が確認されていた(令和7年1月現在)が、令和6年9月からの大雨により、県管理河川の28河川において氾濫による浸水被害が発生し、石川県においては県管理河川の38河川で施設の損傷等が確認されている(令和6年10月現在)。この豪雨により、新たに河川の埋塞や施設損壊、土砂・洪水氾濫等による被害が生じたため、国土交通省においては、県管理河川のうち早急に対策を行う必要がある塚田川(輪島市)、珠洲大谷川(珠洲市)等の5河川において新たに権限代行による応急復旧工事に着手した。これらの応急対策については、令和7年度出水期までに工事完了予定。完了した箇所から本復旧・改良工事に着手し、奥能登地区緊急治水対策プロジェクト(令和7年3月公表)に基づき、令和8年度末までに被災護岸等の本復旧、令和10年度末までに河道拡幅等の改良工事の完了を目指すこととしている。
また、令和6年能登半島地震により、海岸については、石川県の12海岸において堤防護岸損壊等の施設の被災を確認した。宝立正院海岸では、権限代行により国土交通省が復旧工事を実施することとし、地域の復興まちづくり計画と整合を図りながら本復旧を進めることとしている。
<6>文教・保育施設
新潟県、富山県、石川県を中心に国立学校32校、公立学校890校、私立学校102校、社会教育・体育・文化施設等768件の物的被害があり、一部の学校施設では地盤や基礎の被害が確認されている(令和6年5月30日現在)。特に被害の大きかった石川県内では冬休み明けの令和6年1月9日には公立学校86校が休校し(令和6年2月6日までに短縮授業やオンライン学習等を活用しつつ、全ての学校で一定の教育活動が再開)、輪島市や珠洲市、能登町の中学校では金沢市・白山市の施設へ集団避難が実施された(令和6年1月17日から3月22日まで)。また、多くの学校が避難所として使用されることとなった。
その後、学習の場の確保のための応急措置や仮設校舎の整備などが進められ、特に被害の大きかった奥能登地域の1市2町8校においては2学期(令和6年9月)から仮設校舎を活用した授業が始まっている。また、施設の補修復旧を行う校舎については、本格復旧の設計が順次完了し、工事が行われており、国は公立諸学校建物其他災害復旧費負担金等による支援を実施している。
また、保育所を含む児童福祉施設等においては、新潟県、富山県、石川県を中心に394件の物的被害が確認されている(令和6年5月14日現在)。石川県内の特に被害の大きい2園の保育所については、小学校を間借りして臨時開園していたが、令和7年4月時点で2園とも元の園舎での保育を再開している。奥能登2市2町において、地理的に通える範囲内でいずれかの保育所等で利用ができている状況であり、被災後に勤務する保育士数が減少したものの、保育士不足に備えた対応として能登半島地域で勤務する保育士等の全国募集、全国の公立施設の保育士等の応援派遣の仕組みの構築などにより、利用児童数に対応した保育士数は確保できている。こども家庭庁においては、二次避難しているこどもが地元に戻ってきたときに、安心して保育を受けられる体制整備を引き続き進めるとともに、こどもの遊びの機会提供や学習のためのスペース設置など、災害時のこどもの居場所づくりに関する取組を引き続き支援していくこととしている。
<7>文化財
輪島市門前町にある総持寺祖院で、国の登録有形文化財である17の歴史的建造物全てが被害を受けるなど、新潟県、富山県、石川県を中心に文化財429件(国宝・重要文化財(建造物)58件、重要文化財(美術工芸品)6件、登録有形文化財(建造物)184件など)が被害を受けた(令和6年11月8日時点)。また、重要無形文化財「輪島塗」を始めとする無形文化財についても、多くの関係者が被災した。
被災した有形文化財については、建造物の応急措置等を行う文化財ドクター派遣事業、美術工芸品等の破棄・散逸防止を行う文化財レスキュー事業を実施した。国の登録有形文化財については、文化庁と独立行政法人国立文化財機構が連携して専門職員等を派遣し、災害復旧事業については国庫補助率の引上げを行った。また、無形文化財の関係でも、石川県立輪島漆芸技術研修所等への国による支援を実施し、同研修所については令和6年10月7日から授業等が再開されている。
<8>病院・社会福祉施設
医療施設(診療所を含む。以下同じ。)については、令和6年7月30日現在で石川県内の19施設など最大計26施設で被災が確認され、2病院において倒壊の危険のある建物があることが確認された(建物内の患者は搬送済み)。3施設で停電が、23施設で断水が発生していたが、同年7月30日現在において、石川県内全ての病院の断水は復旧した。被災地における医療体制確保の中心となる能登北部公立4病院においては、発災直後からDMAT等による診療・広域避難支援や看護師の応援派遣により、必要な医療支援が行われた。厚生労働省では、被災した医療施設の再開に向けて、医療施設等災害復旧費補助金における交付対象施設の基準額の上限撤廃や公的医療機関施設の補助率の引上げ等を行っている。
社会福祉施設については、高齢者関係施設で、石川県内の191施設など最大計307施設で被災が確認され、30施設で停電が、161施設で断水が発生した。また、令和7年4月現在、能登地域6市町(珠洲市、輪島市、七尾市、能登町、穴水町、志賀町)の休止していた高齢者関係施設28施設のうち16施設が再開している。また、障害者関係施設においても、石川県内の41施設など最大計48施設で被災が確認され、6施設で停電が、30施設で断水が発生した。令和7年4月1日現在、能登地域6市町(珠洲市、輪島市、七尾市、能登町、穴水町、志賀町)の休止していた障害者関係施設46施設のうち38施設が再開している。厚生労働省では、被災した社会福祉施設の再開に向けて、社会福祉施設等災害復旧費補助金の補助率の引上げや、福祉・介護人材の確保として災害の影響により休業・縮小した障害福祉施設・事業所等の再開に伴うかかり増し経費の支援等を行っている。
(2)ライフライン被害及び復旧状況
<1>電気・ガス
北陸電力送配電株式会社管内において、電柱の倒壊や断線等により、令和6年1月1日に最大約4万戸が停電した。北陸電力送配電株式会社では、停電の続く避難所等における早期の停電解消に努め、同年3月15日に、安全確保等の観点から電気の利用ができない家屋等(北陸電力送配電株式会社が保安上の措置を実施)を除き復旧した。
被災地域において、主に石川県金沢市などの都市部に普及していた都市ガスについては、発災当初の段階で液状化の影響による導管被害等により一部で一時的に供給を停止したものの、令和6年1月4日には、ガス製造事業や一般ガス導管事業の被害・供給支障については解消した。ガス小売事業(旧簡易ガス)については、住宅崩壊等により復旧困難な場所を除き、同年1月10日までに供給再開している。被害の大きかった奥能登地域で多く利用されているLPガスについては、供給基地や充填所等の設備支障があったものの、別の場所からの代替配送や、各家庭の軒下を含む被災地内の在庫のボンベの活用等により、供給面での支障が生じることはなかった。
<2>上下水道
本地震では、耐震化されていない水道管で損傷が生じただけでなく、耐震管でも継ぎ手部分が抜けるなどの破断が生じた。さらに、浄水場等の基幹施設が被害を受け、石川県を始めとして新潟県、富山県、福井県、長野県、岐阜県の6県29市7町1村にある最大約136,440戸で配水管破損、管路破損等の被害により断水が生じた。水道施設の復旧に関しては、施設被害の甚大さとアクセスや宿泊拠点が制限される能登地域での支援の難しさから復旧作業は難航したものの、被害状況の調査や復旧計画の立案を行う水道事業体の技術職員が順次現地に派遣され、復旧作業が進められ、令和6年5月31日をもって輪島市、珠洲市の建物倒壊地域等の631戸を除き、水道本管は復旧した。
しかし、令和6年9月の大雨により輪島市、珠洲市、能登町において新たに最大5,216戸で断水が発生した。この大雨により被災した上下水道施設についても早期の復旧作業を図り、建物倒壊地域等を除く全ての地区で令和6年末に断水が解消された。
また、下水道に関しても、1月5日から全国の地方公共団体の下水道職員や民間事業者(公益社団法人日本下水道管路管理業協会等)が下水道管路の復旧支援を実施したほか、1月7日からは地方共同法人日本下水道事業団により、稼働停止の下水処理場等の緊急点検等を実施した。特に被害の大きかった能登地域6市町(珠洲市、輪島市、七尾市、能登町、穴水町、志賀町)においても、令和6年3月5日で下水処理場等の稼働停止は解消し、令和6年4月25日で下水道本管の流下機能は珠洲市の建物倒壊地域等を除き、確保されている。
現在も上下水道一体となって早期復旧に向けた支援が実施されているほか、集落排水施設、浄化槽と連動した復旧作業が進められている。
<3>通信
停電や光ファイバの断絶により、携帯電話の基地局の稼働停止が発生し、令和6年1月3日には、石川県及び新潟県において、携帯電話事業者4社の合計で839基地局が停波した。特に石川県においては、発災直後8市町において支障エリアが発生し、被害の大きかった6市町の通信可能なエリアは、支障ピーク時において被災前の約30%まで減少した。携帯電話事業者各社は、移動基地局等(車載型基地局、可搬型衛星アンテナ、有線給電ドローン、船上基地局)を活用して応急復旧を進め、立入困難地点を除き令和6年1月15日、17日までに応急復旧をおおむね終えたほか、商用電源の復旧、光ファイバの張替、基地局の修理等により、本格復旧を進めた。固定通信についても令和6年2月6日に石川県輪島市の一部を除きサービスが復旧した。また、通信に支障が生じた地域において、総務省と携帯電話事業者、固定通信事業者の連携により、衛星通信機器を避難所に提供するなど、通信を確保する取組を実施した。なお、通信事業者各社は令和6年9月の大雨により生じた被害を含め、道路啓開の状況も踏まえながら、引き続き通信サービスの本格復旧を進めている(令和7年3月現在)。
<4>放送
放送インフラに関しては、地上波テレビ・ラジオが発災当初、商用電源の供給停止によって稼働していた予備電源の燃料枯渇等により一部エリアで停波となったため、被災者が信頼できる情報を入手できるよう、中継局への自衛隊等との連携等による燃料補給、衛星放送を活用したNHK金沢放送局の番組の放送、避難所等へのテレビ・アンテナの設置等が行われ、その後の商用電源の復旧もあり、令和6年1月24日には全域で停波が解消した。また、被災地域はケーブルテレビの依存度が高く(能登町96.4%、珠洲市70.1%等)、3月末までに主センター施設等の応急復旧が完了しており、引き続きケーブルの断線等により不通となった伝送路の本格復旧が進められている。
(3)生業(なりわい)の復興に向けて
<1>中小・小規模事業者の支援
石川県を中心とする北陸地方等において製造業、中小企業の建物や設備の損傷等の被害が多数発生した。石川県においては、県内の中小企業の被害額について、商工会議所及び商工会等へのヒアリング等から石川県全体で約3,200億円と推計しており、その多くは地域に根差す、個人事業主や小規模事業者となっている。また、令和6年11月5日時点で、被災地域外のサプライチェーンにも影響を及ぼし得る業種については、約9割が生産を再開又は再開の目処が立っている状況である一方、工芸品については約4割の企業において生産再開の目処が立っていない状況となっている。特に、地震の揺れや輪島朝市通りの火災で店舗や工房の多くが倒壊・焼失し、輪島塗を始めとする被災地の重要な地場産業である伝統産業も甚大な被害を受けた。
被災事業者の再建支援のため、政府は令和6年1月11日に本災害を激甚災害(地域を限定しない本激)に指定し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)による災害関係保証の特例を適用した上で、同年1月25日には生業再建のための措置を含む支援パッケージを取りまとめた。中小・小規模事業者支援として、中小企業等の施設・設備の復旧・整備を補助する「中小企業特定施設等災害復旧費補助金(なりわい再建支援事業)」や、小規模事業者の事業再建の取組を支援する「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)」、被災した商店街等のアーケード・街路灯等の撤去・改修などの支援、そのほか日本政策金融公庫等による金融支援等を行っている。また、コロナ融資等の既往債務が負担となって新規資金調達が困難となる等のいわゆる二重債務問題に対応するため、「能登半島地震復興支援ファンド」を設立したほか、被災事業者の復旧・復興に向けた資金繰り支援を始めとする各種相談体制を構築し、上記ファンドでの債権買取支援等につなげるために「能登産業復興相談センター」を開設した。加えて、コロナ禍での民間金融機関による実質無利子・無担保融資(民間ゼロゼロ融資)等の返済条件変更時の追加保証料をゼロとする支援も行っている。さらに、伝統産業の復興については、輪島塗仮設工房の設置や、事業再開に必要な道具・原材料の確保等にかかる費用を最大1,000万円補助する等の支援を行っている。
<2>農林水産業の支援
(農業関係)
農業関係においては、農地や農道、用排水路、ため池等の農業用施設の損壊に加え、畜舎や共同利用施設等が損壊したほか、農業・畜産用機械の被害が多数発生した。また、令和6年9月の収穫期の大雨により約400haの農地で土砂・流木が堆積するなど、石川県他14県において農地6,073か所、農業用施設11,845か所(令和7年3月31日現在)で被害が確認された。特に、世界農業遺産に登録された「能登の里山里海」のシンボルでもある白米千枚田(棚田)で大きな被害が生じたことが、被災地の主要産業でもある一次産業の象徴的な被害となっている。
農林水産省は、令和6年能登半島地震による被害に加え、令和6年9月の大雨被害に対しても同様の支援を措置し、機械・ハウス・畜舎等の再建・修繕への補助等を実施するとともに、MAFF-SATを延べ11,000名以上派遣し、技術的な助言・指導など、早期復旧に向けた支援を行い、奥能登地域における水田の営農再開面積は令和5年水稲作付面積の約8割となった。
被災した国営造成施設(4地区)については、国直轄による復旧に取り組むとともに、甚大な被害を受けた七尾市、輪島市及び穴水町の農地海岸は国による直轄代行工事により大型土のう設置等の応急工事が完了し、本格復旧工事に着手した。また、農地地すべり(1地区)は国による直轄代行工事により、地すべりの兆候を確認しつつ復旧工事を進めている。
(林野関係)
林野関係においては、令和6年能登半島地震による被害に加え、令和6年9月の大雨により、石川県他8県において林地荒廃300か所、治山施設93か所、林道施設等3,068か所、木材加工流通施設・特用林産施設等145か所(令和7年3月31日時点)で被害が確認された。特に甚大な被害となった輪島市及び珠洲市の民有林に生じた大規模な山腹崩壊箇所等については、国直轄による災害復旧等事業を実施している。令和6年9月には災害復旧等事業に引き続き、両市の民有林6区域において民有林直轄治山事業に着手した。このような中、令和6年9月20日からの大雨により山腹崩壊等の被害が発生したことから、林野庁では、地震被害の際に取得した航空レーザ測量データも活用しながら、石川県や関係市町に対して、被害把握や復旧計画の策定に向けた技術支援を行った。
また、被災した木材加工流通施設等の整備や毀損した施設の撤去等復旧・整備への補助、「緑の雇用」制度を活用した雇用維持への支援等が行われ、本格復旧に向けて継続的な支援が行われている。
(水産業関係)
水産業関係においては、津波や地盤の隆起等により、漁船の転覆、沈没、座礁や漁港施設の損壊、共同利用施設の損傷等多くの被害が発生し、石川県他2県で73漁港に被害が生じ、石川県では69漁港のうち60漁港が被災した。特に、能登半島外浦地域の輪島市、珠洲市を中心に多くの漁港で地盤の隆起等により出漁できない状態であった。その後、災害復旧事業等による早期復旧作業が進み、石川県の北部6市町(珠洲市、輪島市、七尾市、能登町、穴水町、志賀町)においては、漁獲金額で対前年比7割(漁獲量で6割)まで回復した(令和6年12月現在)。
水産庁では、特に地盤隆起等による被害が大きい漁港(約20漁港)については、短期的な生業再開のための仮復旧と、中長期的な機能向上のための本復旧(泊地の浚渫や隣接地への沖出し等)の2つのフェーズに分けた復旧が必要であったこともあり、有識者による技術検討会を設置し、被災パターンに応じた復旧方法・手順等について令和6年7月に取りまとめ石川県に提供したほか、石川県、珠洲市からの要請により、狼煙漁港、鵜飼漁港海岸の復旧について、国による直轄代行工事を実施するなどの支援を行っている。
<3>観光復興等への支援
令和6年能登半島地震に加え、令和6年9月の大雨により、地域の主要産業の一つである観光産業も大きな被害を受けた。能登地域の代表的な観光地である輪島朝市では火災により約240棟、約49,000m2が焼失し大きな被害を受けたが、東京や大阪等の各地域で「出張輪島朝市」を開催している。また、有数の温泉街である和倉温泉(七尾市)では20余りの旅館・ホテルが被害を受けたが、一部の施設では早くから支援者を受け入れ、一般客の受入れを再開している施設もある(令和7年3月時点)。
観光産業の復興支援のため、生業(なりわい)再建支援等の中小・小規模事業者支援策や、雇用調整助成金の特例等による被災事業者の従業員の雇用維持に加え、観光庁等においては観光需要・経済活動の回復や風評被害の払拭等を図るため、被災地を始めとして北陸地域に関する正確な情報の発信、被災地の観光復興・北陸地域全体の誘客に資するプロモーションを重点的に行ってきた。旅行需要喚起策として、旅行・宿泊料金の割引支援を行う「北陸応援割」(補助率50%、最大2万円/泊)を、令和6年3月から4月に石川県、富山県、福井県、新潟県で、その後も石川県では同年5月から7月、同年9月から11月に、新潟県では同年6月から7月に実施した。また、同年3月から9月まで、公益社団法人日本観光振興協会が民間事業者等と連携し、「行こうよ!北陸」キャンペーンを実施し、福井県、石川県、富山県、新潟県を目的地とした各種旅行商品、各種キャンペーンやイベント情報等について発信するなど、地域の観光復興に向けた取組を行った。さらに、令和7年1月には「能登半島地震からの復興に向けた観光再生支援事業」において地方公共団体、関係団体や個別事業者が一体となった復旧・復興計画の作成、復旧後の誘客促進を図るためのコンテンツ造成等の取組を公募し、3月に採択した。今後、専門家の派遣などによる支援を行う。