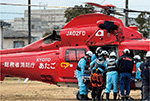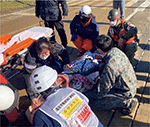第3節 政府の対応
(1)初動及び本部体制の確立
政府は、本地震の発生を受けて、1月1日16時11分に官邸対策室を設置し、16時15分には、岸田内閣総理大臣(当時)から、<1>国民に対し、津波や避難等に関する情報提供を適時的確に行うとともに、住民避難等の被害防止の措置を徹底すること、<2>早急に被害状況を把握すること、<3>地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針の下、政府一体となって、被災者の救命・救助等の災害応急対策に全力で取り組むことが指示された。17時30分には、特定災害対策本部が設置され、さらに、22時40分には、同本部を格上げして非常災害対策本部が設置され、2日9時15分に第1回非常災害対策本部会議が開催された。
また、1日20時00分に内閣府調査チームを石川県庁へ派遣した。さらに、同日23時22分には古賀内閣府副大臣(当時)を本部長とする非常災害現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を石川県庁内に設置した。現地対策本部は、インフラ、物資、生活支援、生業(なりわい)再建に関する4つのチームを編成し、石川県庁と緊密な連携を図った。特に、インフラチームにおいては、法面崩壊、倒木、電柱倒壊等による道路交通途絶が生じ、ライフライン復旧活動にも一部支障が生じたため、現地対策本部内に道路、電気、通信、水道の関係者でチームを構成し、被害を受けたインフラ施設の復旧順位を明確にして効率的な道路啓開の調整を行いながら、復旧作業が進められた。また、被害の大きかった能登地域の6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)には内閣府及び関係省庁の連絡調整要員(リエゾン)を派遣し、被災地の状況確認や被災市町との連絡調整を行った。
(2)救出・救助活動
地震発生後、人命救助を第一に、警察、消防、海上保安庁、自衛隊等が連携し、大規模な救出、救助活動が行われた。
警察では、発災直後から広域緊急援助隊の派遣を行うなど全国警察から部隊を派遣し、石川県警察と一体となって被災者の救出、救助活動や行方不明者の捜索等の各種警察活動を実施した。11月30日までに被災地に派遣された警察職員は延べ約13万5千人にのぼり、倒壊家屋内からの救出、救助や警察用航空機(ヘリコプター)によるホイスト救助等により、115名を救助した。
消防庁では、発災当初から約2,000名規模で緊急消防援助隊を出動させた。緊急消防援助隊と地元消防本部を合わせ、合計で延べ約7万名程度が消火、倒壊家屋からの救出、消防防災ヘリコプターによる孤立集落からの救出、病院や高齢者福祉施設からの転院搬送を実施した。その結果、435名を救助、3,500名の救急搬送を行った(令和6年1月1日の地震発生後からの累計)。
海上保安庁では、令和6年12月4日までに延べ巡視船艇等4,436隻、航空機922機、特殊救難隊18名、機動救難士810名が、救急搬送や行方不明者の捜索などを実施した。
防衛省では、道路網が寸断された半島部において、発災直後から航空機による被害情報収集や捜索救助活動等を開始しており、令和6年1月2日には統合任務部隊を編成し、最大約1万4千人態勢で対応に当たった。また、当初から自衛隊のヘリコプターなどを集中運用して人命救助を実施しつつ、洋上の艦船を拠点とした物資輸送や道路の開通作業に必要な重機や車両、資機材の輸送の実施など、陸・海・空自衛隊の能力を最大限に発揮し活動に当たり、同年4月1日現在で、約1,040名を救助(避難者の輸送等を含む。)した。
(3)応急医療活動
発災後、被災地の医療機関の多くが被災した。また、建築物被害が軽微又は全半壊を免れた医療機関においても職員の出勤、患者搬送、医薬品等の搬送等に支障が生じた。このため、被災者の医療支援を行うため、医療機関や避難所等に全国から災害派遣医療チーム(DMAT)、災害派遣精神医療チーム(DPAT)、日本医師会災害医療チーム(JMAT)、日赤救護班、災害支援ナース等の派遣が行われ、救命措置等の応急医療活動を実施したことに加え、自衛隊の医官や看護官等による衛生支援チームが、孤立地域を中心に巡回診療を実施した。
傷病者搬送、入院患者避難、病院支援等を行うDMATはこれまでに1,139チーム、避難所巡回等を通じ、避難者のこころのケアを実施するDPATは213チーム、被災市町や2次避難所等において医療支援を実施するJMATは1,096チームが派遣され、被災地で活動した。また、公益社団法人日本看護協会の災害支援ナースは延べ3,040名が避難所や被災地の医療機関に派遣された(令和7年4月1日現在)。
さらに、感染症の専門家等が避難所等の感染管理についての助言等を行うとともに、被災県以外の都道府県及び指定都市から派遣された災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)による保健所等の指揮調整機能の支援や、各地方公共団体から派遣された保健師等チームなどによる各市町で作成した住民のリストに基づく巡回訪問等の実施により避難所や在宅等で避難生活を送る被災者の健康管理等を行った。
(4)生活必需物資の調達及び輸送
発災直後から、総理の指示を受け、被災地からの要請を待たずに被災者の命と生活環境に不可欠な物資を国が支援する「プッシュ型支援」を開始し、翌2日には支援物資の第1便が石川県の広域物資輸送拠点に到着した。
具体的な支援物資は、食料、飲料水、乳児用粉ミルク・液体ミルク、毛布、携帯トイレ等の緊急性を要する物資に加えて、特に寒さ対策に必要な防寒着、暖房器具や燃料、避難所等での女性や子育て世帯の方の視点を踏まえて生理用品、お尻拭きシート、乳児用おむつのほか、被災者の健康を確保するための弾性ストッキング、避難所の環境改善に必要な段ボールベッドや、断水が長期化する中で洗濯ニーズに対応するための簡易洗濯キットや洗濯機等の物資など、被災地のニーズを踏まえた支援を実施した。また、民間の物流事業者の協力の下、広域物資輸送拠点から被災地方公共団体への輸送は、主に自衛隊や一般社団法人石川県トラック協会が対応した。さらに、各被災市町の物資輸送拠点においても、市町ごとに物流事業者が担当して避難所等への端末輸送に対応したほか、専門ボランティア団体等が仕分け作業に対応した。