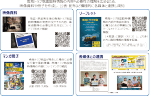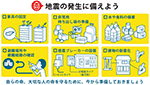第3節 発生が危惧される災害種別ごとの対策
3-1 地震・津波災害対策
(1)南海トラフ巨大地震対策の検討
南海トラフ巨大地震対策については、平成26年3月に作成した南海トラフ地震防災対策推進基本計画(以下本項において「基本計画」という。)等に基づき、国や地方公共団体、民間事業者等が連携し、重点的に進めてきたところであるが、令和6年3月には、基本計画の作成から10年が経過することから、基本計画の見直しに向けた検討を開始した。
令和7年3月には、地震学や地震工学等の有識者で構成される「南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会」において、最新の科学的知見を踏まえ、津波高や震度分布、被害想定の計算手法等の技術的な検討結果を取りまとめた。
(参照:https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/kento_wg/index.html)
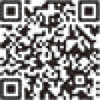
さらに、同月、中央防災会議防災対策実行会議の下の「南海トラフ巨大地震防災対策検討ワーキンググループ」において、基本計画に掲げた防災対策の進捗状況の確認と課題の整理、「南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会」で検討した新たな計算手法と、防災対策の進捗を踏まえた被害想定の見直しなど、今後推進すべき新たな対策の検討結果を取りまとめた。取りまとめに当たっては、「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ」の検討結果を踏まえた。また、令和6年8月8日の日向灘を震源とする地震に伴う南海トラフ地震臨時情報の発表を受けての防災対応に関する検証を行い、改善方策を取りまとめた。
(参照:https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/index.html)

(2)首都直下地震対策の検討
首都直下地震の防災対策については、平成26年3月に作成、平成27年3月に変更(平成27年から10年間の減災目標、施策の具体目標を設定)した首都直下地震緊急対策推進基本計画(以下本項において「基本計画」という。)等に基づき、国や地方公共団体、民間事業者等が連携し、重点的に進めてきたところであるが、令和7年3月には基本計画における減災目標等の設定から10年が経過することから見直しに向けた検討を進めている。
令和5年12月に中央防災会議防災対策実行会議の下に設置した「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」において、基本計画に掲げた防災対策の進捗状況の確認と課題の整理、最新の知見を踏まえた被害想定の見直しを実施するなど、今後推進すべき新たな対策の検討を進めている。これに先立ち、「首都直下地震モデル・被害想定手法検討会」において、震度分布や津波高、被害想定に係る新たな計算手法について検討した。
(参照:https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg_02/index.html)

また、大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策については、ガイドラインを策定して(平成27年3月)、原則3日間の一斉帰宅抑制を基本原則とする対策に取り組んでいる。一方、近年の社会状況の変化等を受け、令和6年7月にガイドラインを改定し、「帰宅困難者等の適切な行動判断のための情報提供の在り方」と「一斉帰宅抑制後の帰宅場面における再度の混乱発生の防止」の2つの観点を加えた。
(参照:https://www.bousai.go.jp/jishin/kitakukonnan/index.html)

(3)日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策の検討
日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の防災対策については、令和2年4月に「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ」を設置し、令和3年12月には最大クラスの地震・津波による人的・物的・経済的被害想定結果を、令和4年3月には被害想定を踏まえた防災対策を取りまとめた。このワーキンググループの報告を受け、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)の下、令和4年9月には、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策を推進すべき地域等の指定を行うとともに、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」(以下本項において「基本計画」という。)を変更した。
また、日本海溝・千島海溝沿いでは、モーメントマグニチュード7.0以上の地震が発生した後、続いて発生する大規模な地震(後発地震)の事例なども確認されていることから、後発地震への備えとして、令和4年11月に「北海道・三陸沖後発地震注意情報防災対応ガイドライン」を公表するとともに、令和4年12月から「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の運用を開始した。
令和5年5月には、実際に発災した場合に備えて、警察・消防・自衛隊の救助部隊の活動拠点等をあらかじめ明確にし、積雪寒冷地特有の課題や地理的条件も踏まえながら、速やかに救助活動等を実施できるようタイムラインを明示した「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震における具体的な応急対策活動に関する計画」を作成した。
今後、基本計画に定められた減災目標の達成に向けた防災対策や、北海道・三陸沖後発地震注意情報の性質や内容を踏まえた適切な防災行動の普及・啓発に取り組み、関係地方公共団体等と連携しながら、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策を引き続き推進していく。
(参照:https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/WG/index.html)

(4)中部圏・近畿圏直下地震対策の検討
過去の地震事例によると、西日本においては、活断層の地震により甚大な被害がもたらされた事例や、南海トラフ地震の前後に活動が活発化した事例があり、府県を越えて市街地が広がっている中部圏・近畿圏で大規模地震が発生した場合の被害は甚大かつ広域にわたると想定される。
この中部圏・近畿圏直下地震については、平成16年から平成20年にかけて、中央防災会議の下、被害想定や防災対策の検討・取りまとめが行われたが、その後に発生した平成23年の東日本大震災の教訓や最新の知見を踏まえ、見直しを行う必要がある。
このため、令和4年11月に地震学や地震工学等の有識者で構成される「中部圏・近畿圏直下地震モデル検討会」を内閣府で開催し、現時点の最新の科学的知見を踏まえ、従来の中部圏・近畿圏直下地震モデルを見直し、あらゆる可能性を考慮した新たな地震モデルを構築するための検討を進めている。本検討会で、中部圏・近畿圏直下地震が発生した場合に想定される震度分布等の推計を行った後、被害想定や防災対策の検討を行う予定である。
(参照:https://www.bousai.go.jp/jishin/chubu_kinki/kentokai/index.html)

「南海トラフ地震臨時情報」と「北海道・三陸沖後発地震注意情報」
南海トラフ沿いでは、規模の大きな地震が発生した後、その地震に引き続いて大規模地震(後発地震)が発生した事例が確認されている。例えば、1854年の安政東海地震の約32時間後に安政南海地震が、1944年の昭和東南海地震の約2年後の1946年に昭和南海地震が発生した。このため、後発地震への注意を促す情報として「南海トラフ地震臨時情報」の運用を令和元年5月31日から開始した。
「南海トラフ地震臨時情報」は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始したことをお知らせする「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」、有識者による「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の評価結果に応じて「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」、「南海トラフ地震臨時情報(調査終了)」が発表される。「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された場合には、その後、政府や自治体からあらかじめ指定された地域の住民等に対して1週間の事前避難などの防災対応が呼び掛けられる。
(参照:https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/rinji/index.html)

令和6年8月8日に日向灘を震源とするモーメントマグニチュード7.0の地震が発生し、運用開始以降、初めて「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表された。臨時情報の発表を踏まえ、政府としては、日頃からの地震への備えの再確認やすぐに逃げられる態勢の維持など、1週間の「特別な注意」の呼び掛けを行った。政府、自治体及び事業者等の臨時情報発表時の一連の対応や社会の反応等を振り返り、今後の臨時情報発表時の防災対応に生かすべく、「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」において検証を行い、令和6年12月20日に「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表を受けての防災対応に関する検証と改善方策」を取りまとめた。
(参照:https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/rinji_kaizen241220.pdf)

「南海トラフ地震臨時情報」と同様に後発地震への注意を促す情報として、令和4年12月から「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の運用を開始した。この情報は、モーメントマグニチュード7.0以上の地震が、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の想定震源域とその領域に影響を与える外側のエリアで発生した場合に発表される。この際、防災対応をとるべきエリアの市町村においては、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」と同様に、地震発生後1週間、後発地震の発生に注意し、揺れを感じた際や津波警報等が発表された際に直ちに避難できる態勢の準備を行う、日頃からの備えを再確認するなど、地震への備えを徹底するよう呼び掛けられる。
(参照:https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/hokkaido/index.html)

「南海トラフ地震臨時情報」も「北海道・三陸沖後発地震注意情報」も、大規模地震の発生可能性が平時と比べて相対的に高まっていることをお知らせするものであり、特定の期間中に大規模地震が必ず発生するということをお知らせするものではないが、一人でも多くの人の命を救うためには、後発地震への注意を促す情報を発表し、地震発生に備えた防災行動を取ることが重要である。
南海トラフ及び日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震のような大規模地震は、先発地震を伴わず突発的に発生する場合もあることから、揺れ、津波、火災、そして避難後の二次災害等に備えるため、日頃から、
- 津波等から迅速避難を行うための避難場所・避難経路の確認
- 大地震が発生したときには家具は必ず倒れるものと考え、家具の固定等の転倒防止対策の確認
- 電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合を想定し、飲料水、食料品等の避難生活等に備えた備蓄・装備の確認
等を徹底することが重要であり、これらの日頃からの地震への備えが後発地震への注意を促す情報が発表された際の備えにつながる。