第6章 避難活動
第1節 計画の主旨
この計画は、警戒宣言が発令された際、地域住民が迅速かつ安全に避難し、生命の安全が確保できるよう避難対策の基本を定めるものとする。
第2節 避難の勧告、指示及び誘導
1 避難対策の基本方針
市が、地震防災強化計画において明らかにした津波の浸水及び山・崖崩れの発生が予想される地域(以下「避難対象地区」という。)の住民等は、警戒宣言が発令された時は速やかに危険地域以外のあらかじめ定められた避難地へ避難する。
避難地では、自主防災組織の単位で行動するものとする。
その他の地域の住民等は、居住する建物の耐震性、地盤等の状況に応じて、必要がある場合、自主防災組織等が定める付近の安全な空地等へ避難する。
又、漁港に停泊、又はけい留中の船舶は、漁港管理者の指示に基づき、緊急連絡網及び漁業無線により連絡し、港外に避難するものとする。港外にいる船舶には、漁業無線により連絡する。
2 避難のための勧告及び指示
(1) 勧告、指示の基準
市長は、原則として「避難の勧告」を行うものとし、急を要する時は「避難の指示」を行うものとする。
(2) 勧告、指示の伝達方法
市長は、警戒宣言発令後速やかに避難対象地区の住民等に対し、同報無線、広報車等により避難の勧告、指示を行うものとする。また、警察官、海上保安庁に対し、避難の勧告、指示の伝達について協力を要請するものとする。なお、市長は必要に応じ避難の勧告、指示に関する放送を県に依頼する。
3 東海地震が予知された場合及び突発地震が発生した場合の避難対策計画
(1) 警戒宣言発令時の避難方法(表1)
(2) 突発地震発生時における避難方法(表2)
東海地震が予知された場合及び突発地震が発生した場合の避難対策計画
警戒宣言発令時の避難先としては、まず個々の家庭が安全な地域に居住する知人等の家庭に避難することを優先させ、この様な手段がとれない避難者のために市が指定する避難地を準備する。
避難地は、警戒宣言発令→地震発生→災害拡大→災害終結の過程において、住民の生命と安全を確保するための防災空間であると共に、応急救護等の活動拠点となる場所であるのに対し、避難所は地震災害により、居住場所を確保できなくなった者等を収容する場所であり、かつ救護、復旧等の活動を行うため拠点となる場所である。
表1 警戒宣言発令時の避難方法
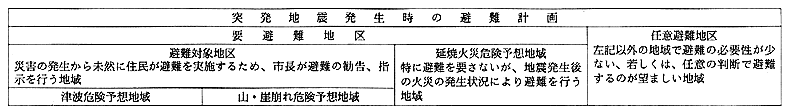 | |
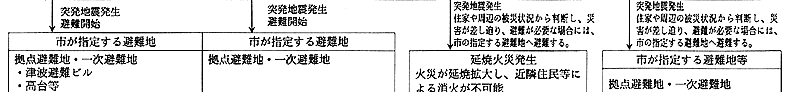 | |
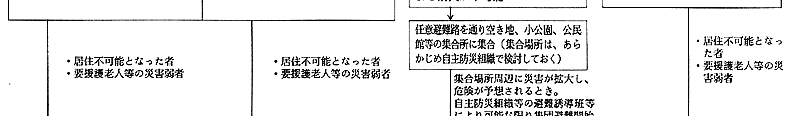 | |
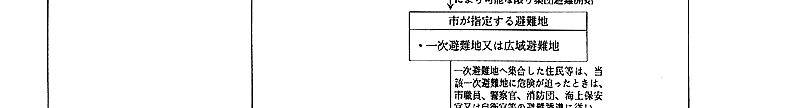 | |
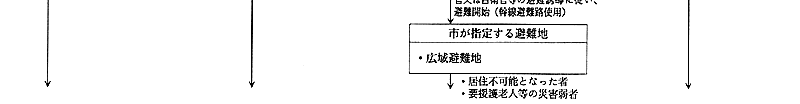 | |
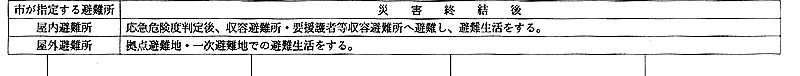 | |
表2 突発地震発生時における避難方法
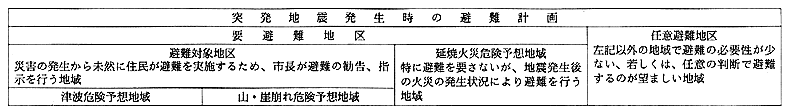 | |
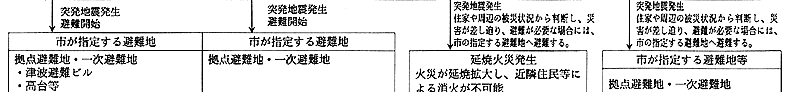 | |
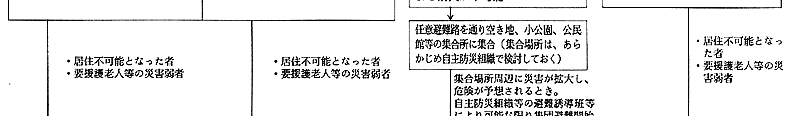 | |
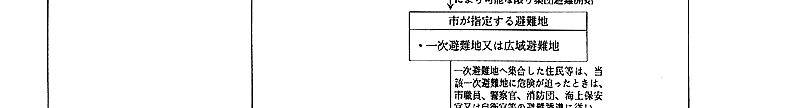 | |
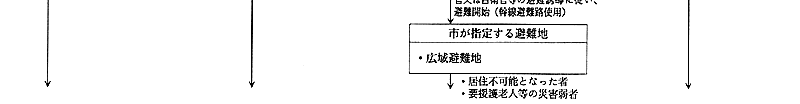 | |
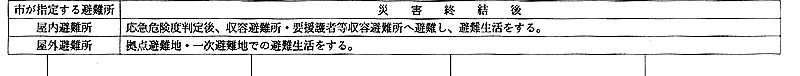 | |
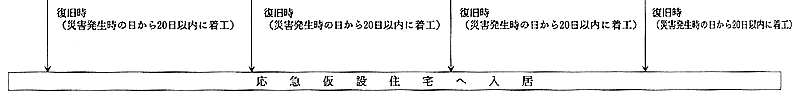 |
第3節 避難に際しての周知事項
避難対象地域住民に対しては、日頃から次の事項についてパンフレット等で周知を図るとともに、警戒宣言が発令されたときの伝達は同報無線をもって行うものとする。
1 避難対象地域の地域名
2 出火防止措置、消火器の点検、貯水、家具等の転倒防止措置等の地震防災応急対策の実施
3 避難経路及び避難先
4 避難する時期
5 避難に際しての服装、携行品及び非常食糧の持出し等
6 避難行動における注意事項
第4節 警戒区域の設定
避難対象地域のうち、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第26条において準用する災害対策基本法第63条(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、警戒区域として設定すべき地域を別に定める。警戒区域の範囲の周知及び警戒本部のとる措置は前節に準じて行う。
警戒宣言が発せられたときは、速やかに警戒区域の設定を行い、当該住民の退去又は立入禁止の措置をとるとともに、関係機関の協力を得て退去の確認を行うものとする。
第5節 避難計画の作成指導
避難の実施等措置者はそれぞれ、避難地、避難路、避難方法、避難誘導責任者及び避難開始時期等を内容とする避難計画を作成し、地区住民、施設の利用者等に周知徹底し、避難の円滑化を図るものとする。
第6節 避難状況の報告
警戒本部長は、自主防災組織の長又は避難の実施責任者から、直接又は所轄警察署を通じて次の報告を求める。
1 避難の経過に関する報告
2 避難の完了に関する報告
第7節 避難地における避難生活の確保
市は、避難を必要とする者のために避難地を設置するとともに、自主防災組織及び避難地の学校等施設の管理者と協力して必要最小限の避難生活を確保するために必要な措置を講ずる。
1 避難地の設置及び避難生活
(1) 避難生活者
避難地で避難生活をする者は、津波や山・崖崩れ危険予想地域に住む者、帰宅不能者等で居住する場所を確保できない者とする。
(2) 設置場所
ア 津波や山・崖崩れの危険のない場所に設置する。
イ 原則として公園、学校のグラウンド等の屋外に設置する。
(3) 設置機関
警戒宣言が発令されてから警戒宣言が解除されるまで又は地震が発生し、避難所が設置されるまでの期間とする。
(4) 避難地の運営
ア 市は、自主防災組織及び避難地の学校等施設の管理者と協力して避難地を運営する。
イ 避難地には避難地の運営を行うために、市職員を派遣するとともに、避難生活に必要な物資を配置する。
ウ 自主防災組織は、避難地の運営に関して市に協力するとともに「避難所業務マニュアル」等に基づき役割分担を確立し、相互扶助の精神により自主的に秩序ある避難生活を送るように努める。
エ 避難生活基本計画
2 食糧等の生活必需品は、各人が一週間分を準備することを原則とする。
3 市は、帰宅不能者等の物資不足者に対して物資をあっせんする。
