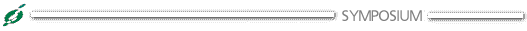
伊藤 いまボランティアの抱えている問題点を整理してお話しくださったわけですが、いま西川さんのお話の最初のところで、これはボランティアとは直接関係ない、電話がふさがってしまうというお話がありましたね。
実は、災害が発生するといつもこの電話の輻輳が起きるのです。そこで、最近NTTが、災害用の伝言ダイヤルというのを立ち上げました。これは被災地の人が、例えば、自分の家は大丈夫ですよというメッセージを被災地外の人に伝えるときに、まず171、次に1をプッシュして、そのあとに自分の家の電話番号をプッシュして、最後に伝言を30秒以内に収めて入れておくのです。
そうすると、被災地外の人たちがその人の安否を知りたいときには、171、それから2をプッシュして、同じ電話番号を回すと、その人のメッセージが聞けるという仕組みになっていて、去年の3月31日から立ち上げております。
これは実際、去年の関東地方の水害のときにも効果を発揮しましたし、それから震度6弱以上の地震があったときには自動的に立ち上げるようにしておりますので、ぜひこれは皆さん覚えておいていただきたい。そうすれば、電話の輻輳などを避けることができますし、被災地に住む知人や親戚の安否をたずねることもできるということです。
それでは次に、笠原さんに、いままでいろいろ皆さんのお話をお聞きになって、ボランティアの専門家としてきっといろいろご意見もあるのではないかと思いますが、今後の問題も含めてお話しいただければと思います。笠原 私は大きく分けて2つの総論的なことをお話しさせていただきたいと思います。
まず、第1点目ですけれども、やはり阪神・淡路大震災でのボランティア活動というのは、我が国のボランティア活動の全体の中ではすごく大きな影響を与えたと思います。市民がボランティア活動に参加しつつある中で、さらに大きな扉を開けたというか、みんなが「あれ」っという感じでボランティアに注目したことだと思います。
そういった中で、ボランティア活動に阪神・淡路大震災がどのような影響を与えたかということを、大きく10点に分けてそれぞれお話しさせていただきます。
簡単に申し上げます。第1点目は、やはりボランティア活動に対する社会的評価を高めたということです。行政とは異なる独自の意義が確認されたように思います。
第2点目は、参加層の拡大です。私も学生のときに大阪府の社会福祉協議会から大学の研究室に依頼がございまして、報告書をまとめました。これは、府社協がボランティア保険に加入された約3万7000人の方の中で、7分の1を抽出して、郵送で調査した結果をまとめたものです。その中でも、やはり学生のボランティアの参加が非常に増えております。それから、初めてボランティアに参加した人も、半分以上ありました。地域での平常時のボランティアというのは、中高年の主婦層が一番多いのですが、学生が増えたなということです。それから「初めての(おつかいじゃないですけど)ボランティア」が増えたというのが非常に大きな影響だと思います。
第3点目は、コーディネーターの重要性が確認されました。4点目は、ボランティアの活動には拠点が必要だということが確認されたと思います。何もなしでポッと行っただけでは、何をしたらよいのか、とまどってしまいます。
5点目は、ボランティアのグループ間、団体間のネットワークの必要性が確認されました。さらに、ボランティア団体だけじゃなくて、企業のフィランソロフィーと言われている活動、それから労働組合とか、生協、農協、福祉団体といったところも含めた諸団体の連携が必要だということが確認されました。
6点目は、情報の重要性です。先程の調査によりましても明らかにされました。
7点目が、行政とボランティアの連携のあり方です。これまで、あまり議論されるチャンスがなかったように思いますね。くすぶっていた状態が、やはりしっかり議論する場を持つようになったのではないかなと思います。
8点目は、コミュニティづくりの重要性。先ほど、関係者の方々とお話ししていまして、「隣組なんて復活した方がいいのではないか」という意見がありました。隣のおばあちゃんがどこに寝てはるかとかいうのがわかっていたら、家がペシャンコになったとき、どこから、くずれてしまった柱を上げてよいかすぐわかると。そういったコミュニティづくりの重要性。
9点目が、市民活動の基本的条件整備が進められました。具体的には、ボランティアの問題に関する関係省庁の連絡会議というのが設置されまして、法人制度のあり方とか税制度のあり方について検討されるようになり、昨年の3月にはNPO法といって特定非営利活動促進法という法律が成立いたしました。
最後に、10点目というのは、基本条件整備と併せまして、ボランティア活動の社会的支援策。「震災がつなぐ全国ネットワーク」といった組織が存在するようになったと思いますし、ボランティアの支援セクターへの支援ですね。それから、あわせてボランティア活動に参加しやすくするためのボランティア休暇とか、そういったいろいろな条件整備の検討が進められたと思います。
いま10点申し上げたのは、非常にテキスト的で、阪神・淡路大震災の影響を肯定的に申し上げました。私のようにおばさんになってきますと、それを100%素直に受け取るのではなくて、ちょっとはすかいに構えてもう一度考えたりします。やはり一見追い風に乗っているようにも見えるボランティア活動ですけれど、楽観的に受けとめるのではなくて、学校の学生さんなどのボランティアの生の声を反映したところの、ボランティア活動の今日的な課題というものを、2点目に少し申し上げたいと思います。
本校の学生とともに、ボランティア活動について授業などで議論することがあります。「ボランティアというのは、自分のやりたいこととか好きなことを選ぶことに尽きるんとちがうか。嫌なことをやってたらボランティアと違うもんねえ」というように学生は言います。
けれども、自分の好きなことを探すのってなかなか難しいですね。ボランティアっていうのは「自分探し」なのかなあ。「先生、ボランティアってどこまでするの」「ボランティアっていうのは、常に初心者やと思わんとあかんのんとちがうかなあ」などと。
学生は介護の専門職になる勉強をしたり、理学療法士や作業療法士になる専門家としての勉強をしていますけれども、やっぱりボランティアというのはプロじゃないと思う。障害者よりも障害のことについて知っているというのは、ちょっとボランティアと違うのではないでしょうか。「ボランティアってどこまでしたらいいの」と学生さんが聞くのですけれども、「自分がどこまでしたいかということを考えたら」っていうようにアドバイスします。 したくないときはボランティアをやめたらよいし、どこまでしたらよいかとか考えると、「どこまでやってもいいし、しんどかったらやらなくてもいいよ」と、そんな「すべき論」ではないと思うのだけれどって。一生懸命まじめに熱心な人ほどしんどいし、つぶれてしまうのではないかと思います。
また、心構えで言うと、自分のしていることはよいことなんだと思い込むと、ちょっとややこしくなってきます。それは、悪いことをしているとは思いませんけれども、よいことをしているという全面評価をしますと、ボランティアしていない人のことを否定することになってしまいます。
ですから、ボランティアというのは、そんなに肩肘張ってするのではなくて、肩の力抜いて、さまざまなレベルで関わるのが、一番よいし、そのように関われる「いつでもウエルカム」っていう基本があるし、あってほしいと思います。
ですから「もうどっぷり浸かったら大変ですから、私もささやかにしてます。そのささやかで片足ずつ、半身ぐらい入ったらどうですか。半身だけだったらいつでも抜け出せるしね。どっぷり両足入ってしまったら、ちょっと疲れるね」というように。このような話をしつつ、学生ボランティア活動について、学生とともに学んでいます。
どなたでも経験があるのではないかなあと思うのですけれど、人から頼まれて成り行きで、引き受けざるを得ないという場合がたまにあります。そんなとき私たちの心の中では、「仕方ないから」っていう意識があります。
そういう意識があると、頼んだ方はもっと恐縮しています。「やってもらう」っていう態度になってしまうのですね。この二者の間には、一時的でも力関係が生まれると思います。力関係で自分が下の立場にいるときは、気持ちよくないので、「借りは返さないと」とか、そういうことができなければ、見える形でお礼をして、力関係を清算したいと思ってしまう。そうならないように、「したいこと」と「したくないこと」、「できること」と「できないこと」というのは常にはっきりしないといけないと学生さんたちに話します。
強者と弱者の上下関係ではなくて、痛みを共有する並列関係に発展していることがすごく大事だと思います。それは、みんなが卒業して、介護福祉士になったり、理学療法士になったり、作業療法士になったりする。必ず何か痛みを持っていらっしゃる方を相手にする仕事です。「そういった人たちを相手にする仕事、自分がいつも優位に立ってるとか、上下関係にあるって思ってたら、仕事できなくなると思うのよ」というように。
ですから、ボランティア活動というのは、これから将来、自分の仕事をする上において、「ウォーミングアップ」と言ったらちょっと失礼かもしれませんけれども、そういった実体験をするという意味で非常に有意義なことだなあというように考えています。
彼や彼女たちがそういったボランティア活動を学生時代に体験するというのは非常に大切だなあと思います。しかし、青少年のボランティア活動が、いま青少年を取りまく問題解決への特効薬になったり、ボランティア活動に継続的に参加をするようになるというような楽観的な認識というのは、やはり現実的ではないと考えます。
もちろん、知的な理解だけでなくて、実践を通じた体験によるふれあいというのはすごく大事だし、有効だと思いますけれども、あまりボランティア活動を高く評価しすぎるというのもちょっと心配だなあというようにも思います。
実際、学生さんと毎日接してそういうように感じるのですけれども。ですから、ボランティア活動のすべてを疑いなくそのまま受け入れるのではなくて、まず学校の垣根(というんですか)を低くして、学校の中での教育と学校外での教育を有機的に連携していくことが、一番求められると思います。
教室の中で「社会福祉概論30点しか取れなかった」という子が、ボランティア活動を通して、すてきな姿を見せてくれることがあります。
学校では、情報を提供するだけで、学生さんは掲示を見て個人でボランティアに参加しています。学校の中と違う姿も見ることができ、私も楽しく活動をしているのです。やはり大事な一つの要素としてあせらずぼちぼち展開されていくのがよろしいんじゃないかなと、日頃、学生さんと接して感じております。
伊藤 ありがとうございました。
その「ぼちぼち」というのは、さっき石井さんが言われた「できること」を「できるとき」に「できる範囲で」ということと、共通していると思います。
では最後になりました、山田さん、お願いいたします。
山田 いま笠原さんから、だいたいボランティア活動の方向なり、条件、環境については説明があったと思います。
私は、ボランティア活動はいま2つの大きな変化の時期にきているのだろうと思います。一つは、毎日新聞の栃木版という地方版で、記者がずっと「市民社会の行方」という形でレポートを書きました。
その中で、私も取材を受けたのですが、ボランティアに対する信頼感が高まってきたということです。これは行政の変化だと思います。どうもいままで、行政とボランティアというのは敵対するみたいな部分があったのではないか。ボランティアは様々な要求をしていくが、行政はできない、という形での軋轢があったのではないだろうか。
しかし、現在はそうでもない。例えば、今回の那須町の水害のときには町の公民館を行政が貸してくれたし、しかも電話や活動資材を提供してくれた。また、黒磯市では、公民館や消費生活センターが入っている建物を民間の人に宿舎として、あるいはボランティア拠点として貸してくれた。そういうような変化があります。
このように、ボランティア活動に対して行政の変化というのが、阪神・淡路大震災あるいは今回の水害を契機に認識が大きく変わってきた。それは、首長さんがボランティアの人たちに対して、「失ったものは大きいが、皆さんのおかげで立ち直れるよ」と言うところまできたというところがあるのだろうと思うのです。
もう一つは、やはりボランティア活動自身の変化だと思います。それは、皆さんがおっしゃっているように、従来のボランティアは、主婦あるいはシルバー層や、時間的に余裕のある人が、ということがありましたけれども、高校生あるいは大学生が非常に積極的に参加をするようになり、また、そういう意識が高まってきたということです。
ただ、そういう参加意識を受けとめる受け皿というものが、本当にいま、地域の中で整備されているのだろうか。善意や、やりたい、頑張りたいというものに対しての条件整備があまりないのではないだろうか。
それは、私どもの社協の弱さや、あるいはそういうボランティアを取りまく施設、その活動を評価しながらともに高まっていくという仕組みがまだまだ地域の中で整備されていないのではないだろうか。
私どもも、もちろんボランティアに関する情報や、あるいは資料など、いろいろ提供しているけれども、いまの若い人たちはパソコンなどでさまざまな情報を受けても、社協の機関誌やあるいは雑誌やニュースというものはそうは見ないのではないだろうか。
そういう意味で、今回駆けつけた人たちは、やはりラジオとか、あるいはインターネットとかテレビで駆けつけて来た。考えてみると、新聞というのは、こういうボランティア募集をしていますよといっても、翌日しか出ないわけです。でも、私が現場からFMや地元のラジオ局の直接取材で訴えますと、すぐにドーンと電話がかかってきて集まってくるという状況でした。そういう意味では、ある面ではボランティア活動を取りまく条件整備も、若者が入手しやすいような情報提供の方法だとか、活動しやすい条件を作らなければだめなのではないでしょうか。
一方では行政が変化をし、ボランティアへの評価が高まってきたけれども、そのエネルギーというものを本当に私どもが受けとめて、きっちりと活かせるのだろうか。それを災害のときだけでなくて、私はできるならば、日常生活の中で取り組んでもらうような仕組みというものを考えていかなければならないのかなと、こんなことを思っているわけです。
そういう中で、私はこの福祉の仕事は長いのですが、私はいつもボランティア活動はやはり「体験するもう一つの学校だ」と言ってきました。
いわゆる試験もなければ、授業料も、若干あるかもしれませんが、ない。学校は知識や技術を学ぶところだけれども、ボランティアというのは体験しかないと。体験がまず前提だろう、というように思っています。
それからもう一つは、ボランティア活動というのは「行政に対する市民参加の一つの形態」ではないかと言っています。住民参加といいながら、行政に対して口出しできるのは、議員さんか、行政委員会の委員さんか、監査委員とか、何かならないとなかなか行政に対して意見が言えないだろう。
しかし、ボランティア活動というのは、さまざまな支援活動を通しながら、その町に住む住民の安全や安心や生きがいというものを充実していくものであるならば、それはまさに街づくりの重要な担い手になるのではないだろうかと。
行政から頼まれてやるというのではなく、私たち住民が主体となって、社協もそうですが、住民主体、住民参加の組織ということならば、もう少し街づくりに対して積極的に考えていくべきだろう。そういう意味では、行政に敵対するという意味ではなくて、こうあったら、こうして欲しいというものを、活動を通しながら、体験をしながら訴えていくという、こういう部分が大事だと思っています。
そのつなぎは、やはり私は社協がやらなければいけないと思っていますが、まだちょっと、力が弱いということは事実であります。
もう一つは、私は福祉サービスの受け手がすべて受け手だけではないということだと思います。どういうことかと言いますと、実は私は、この職場の前は県の児童家庭課に勤務し、子育て環境づくり推進担当主幹という仕事を担当していました。いわゆる子育てのための環境づくり、それから子どもたちがどんな条件の中でも健やかに育っていく環境をつくっていこうとする子育ち環境づくりを推進してきました。
ちょうどその頃(昨年ですが)、栃木県では中学生の女性教師刺殺事件が起き、そのあと子どもの虐待が数件起き、非常に殺伐とした状況がありました。
そういう中で、私はボランティア活動と子育て・子育ち環境づくりは関係があり、特に子育ち環境づくりが大事ということを考えまして、ひとつ事業を考えました。それは、青少年の子育て体験事業だったのです。
中・高校生に夏休みに保育園へ行ってもらって、子どもを抱っこしてもらおう。そういう中で、命の重みや温かさなどを感じてもらったり、おむつ交換をやってもらおうかという事業です。約600人ぐらいの中高生が夏休みに保育園に行きました。
これは黒磯市だったのですが、体験発表会があり、そこに私も参加をいたしまして、感想を聞きました。感想にコメントしたのですが、ある高校生はこう言っていました。「先生、私は将来絶対保母になろうと決心をしました」と。中学生の頃から考えていたようです。しかし、まだはっきり決まっていなかった。でも、3ヶ月の赤ちゃんを抱っこして、笑顔を見て、さわってみてあたたかかった。丸かった。何というか、弾力があったというのか、そう言っていました。
「あなた偉いね」と私は誉めました。しかし、「あなたはボランティアで行ったかもしれないけれども、3ヶ月の子どもがあなたに、あなたの生き方を示してくれる。あるいはそのヒントをくれたということは、非常に素晴らしいことだよ」と。だから、私たちはボランティア活動を受け手と供給、受け手と担い手というとらえ方をしてきたけれども、決してそうではない。常に担い手になり得るし、受け手にもなり得るだろうと。そういう意味でボランティア活動を考えていかなければならないと思っています。
私は、いま年間だいたい50回ぐらい市町村社協、行政、ボランティア活動、シルバー大学校や家庭教育学級へ行っています。また、高校・中学校にも行っているのですが、私の講演のテーマに面白いものがありまして、「サッカーと社会福祉」というのが大部分です。
私は右手がないのですが、サッカーをずっとやっておりまして、神戸でやったフェスピックのサッカーにも出場しました。よく話をしますが、サッカーと福祉の共通点は目の高さ、あるいはパスだと言っています。サッカーというのは1つのボールを11人がつないで、シュートを相手のゴールに入れるわけです。そのときにパスというのは、ただ「オーイ、蹴るよ」ではないはずだ。そのパスは、味方が一番蹴りやすいように、蹴りやすい角度に、あるいはスピードに。それで、シュートできるように思いと願いを込めて出すのがパスなんだ。ただ、蹴ればよいというものではないんだよと。たった1個のボールだけれども、そこにはさまざまな関わりが出てくる。
それから、味方のミスを非難している暇はないはずだと。それは、身体を張ってカバーしなければならない。それから、もう一つは「俺が、俺が」じゃ絶対に勝てないってことです。どんなにエースストライカーがいたって勝てない、これは。いろいろな人が、それぞれの持ち味を持ってプレーするということなのです。
もう辞めましたけれども、日本サッカー協会会長の古河電工出身の長沼健さんが、こういうことを言っていました。金属というのは純粋になればなるほど弱いのだそうです。だから、いろいろなものを混ぜ合わせて合金を作って強くしていくのだそうです。サッカーも同じだと言っていました。私は福祉の営みも同じだろうと思っています。
この前、男子高校へ行ったのですが、正面きっての福祉の話はあまりよくわかってもらえないけれども、こういう話から入っていくと、だいたい1時間10分ぐらいもちますね。うなずいてくれます。「そうだよ」ってうなずいてくれるのです。
それからもう一つは、相手の立場になろう、と言ってきました。これは、今回の震災でもそうなのですが、他者のために汗を流すという、そういう体験を彼らは聞き、被災者の生活実態を実際に目で見た。ビデオとか映画じゃなくて、自分で見た。そこにかかわってきたという、そういう部分がありました。
講演の最後によく言うことですが、PK戦、ペナルティキック戦の状況です。みんな手をつないで、味方のキックを待っている。たまたま、味方が外して負けた。外した選手は、恥かしくて悲しくてなかなか味方の方に戻って来られないという場があるわけです。
それをみんな誰も批判はしない。仕方がない。むしろ、戻れない仲間を迎えに行って、肩を抱いて帰ってくるじゃないか。そういう見方で日常生活、学校生活を楽しんだらよいではないか。もっと端的に言えば、自分が嫌がることは人にしなければよい、ということです。これがあれば、いじめなんかあるはずがないと。
自分がしてもらいたいことを他人にしてあげればよいわけです。この話を小学校で言うとわかりますね。
そういう意味で、私は、これからの若い人たちは21世紀で、少子・高齢社会が進む中でこの社会を背負っていくのは君たちだと。だから、他人の痛みというものを少し受けとめながら、頑張っていこうよと言ってきました。若い人たちは、なかなか一人では行動できない。やりたいのだけれどもできない。あるいは、ものすごく素直で、明るくて、エネルギッシュなのだけれども、誰かがいないと何か不安でしょうがないという、そういう集団への帰属意識とか仲間意識というのを非常に求めていると思います。
そういうものを、一番充足できて、一緒に楽しめるというのはボランティア活動ではないのかなと、災害だけではなくて。 最近、高校生が高校生の悩みを聞くという電話を、県のボランティア連絡協議会に設置をいたしました。かつて登校拒否の経験のある女の子が、いま相談を受けていますが、「そんなこと言ったって頑張んなよ」とか言っています。
それから3月には、高校生1,000人集会をやろうということになっています。だけれども活動資金がないと。『風の歌が聴きたい』という映画を上映して、1,000人集めて活動資金にあてようとしています。私も少しはカンパすることになっているのですが、そういう形でいま、やっています。
ただし、私たちは手は出さないようにしよう、高校生たちが集まって、大人たちは必要に応じて相談にのろうと。こうしろ、ああしろとは言わないで、少しやってみようかと思っています。
チラシとチケットができたら、教育委員会とか福祉関係の部・課長にはカンパを頼みに行こうという話をしています。その他、JCとか災害で付き合ってくれた企業も結構ありますので、まず持って行けば協力してくれるだろうと。
そういうことで、災害でさまざまなことがありましたけれども、私は栃木県の場合、那須や黒磯での活動で、そのまま高校生たちがすぐには育つとは思っていません。ただ、ああいう状況の中で、いま失いがちな連帯感やあるいは痛みというものをわかりあってくれるならば、いつか何かのときに気がついて、よい街づくりに彼らのエネルギーが活かされていく、そのとき、それを受けとめる行政も社協もしっかりしなければならない、そんなことを考えているところです。
まだまだ言いたいことがあるのですが、こんなところでとりあえず発言を終わりにさせていただきます。
伊藤 それではここで、皆さんからご質問、ご意見などございましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。
会場 お役に立つかどうか、今日の話と関係するかどうかわかりませんが、昨日でしょうか、テレビで、ボランティアが行き詰まってるような感じの、経済的にか何か分かりませんが、放送がありましたので、何か心配だなあと思いました。
伊藤 その放送を私は見ていないのですが、どういうふうに行き詰まってるというのですか、経済的にでしょうか。石井さん、何か思いあたることがあればお話しください。
石井 全体として被災地のボランティア活動は、4年たって存続が難しくなっている団体も多いですね。
震災の翌年度から3年間、県ですとか社協さんなどから、色々な形で支援をいただいていたのですが、この3月で支援が終わるというものが多いらしくて、この4月以降活動が継続できないと言っているボランティアグループは増えてきていますね。もしかしたら、そのような話が紹介されたのではないでしょうか。
伊藤 他にいかがでしょうか。
会場 今日はどうもありがとうございます。
勤務先の方から、今年2ヶ月ぐらいヨーロッパに防火・防災に関する研修に行かせていただけるようなプログラムをいただきました。何かの参考にと思って、今日参加させていただいたのです。
私の研修課題というのは、ヨーロッパ各国における自主的な防火・防災活動の取り組み方であるとか、それから青少年に対する防火・防災教育であるとか、それからボランティアスピリットそのものの啓蒙なんかも、学校教育の中で行われているというようなことをお伺いしたので、そういうことを皆さま方のお話されていたようなことから何か実現するヒントを得たいと思いまして、研修課題に選んでおります。
一応、行く国はイギリスとフランスとドイツとイタリアとジュネーブなんですけれども、どこの国のどういうとこへ研修に行けば一番、研修効果が効率的であるのか、よろしかったら具体的なアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いします。
伊藤 これは、やはり室崎さんいかがでしょうか。
室崎 ヨーロッパでは、特別に特色を持っている国というのはほとんどないです。スイス、ドイツあたりもどこもほとんど同じ発想法でやっていますから、どこも同じだと思いますね。
ただ、日本と違うのは、やはりそういうボランティア活動というか、特に防災とかに携わるということは、シビルディフェンスといって市民の義務(責務)として位置づけられていますから、それが当たり前のようにみんな思っているわけですね。
だから、日本とやはりそういうヨーロッパの土壌というか、ずいぶん違いますから、そこをしっかりご覧になっていただければよいのではないかなというように思います。
会場 ありがとうございます。イタリアも。
室崎 イタリアも同じです。
会場 同じですか。はい、ありがとうございます。
伊藤 それでは最後に、まだ、言い足りない方もおられると思うので、一言ずつ皆さんからいただきたいと思います。
では、笠原さんから。
笠原 ボランティア活動の基本的な考え方を述べます。大阪市立大学の山縣先生が教えてくださいました。1点目「非まじめの思想」と言っているのですけれども、まじめになりすぎず、不まじめになりすぎず、ボランティア活動をする者と受け入れる者との強者・弱者の関係を排除するという、「非まじめ」という思想です。 それから、「ほどほど」。詰め込みすぎて、プログラムの消化に力点が置かれ、振り返りや立ち止まりのゆとりが失われないように、ほどほどにしましょうという「ほどほどの思想」です。 それから3点目が「ぼちぼちの思想」。性急な評価を求めず、求めたいですけれども、変化を大切にする。 4点目が「ニコニコ」で、緊張を強いるようなプログラムではなくて、楽しさを前提とする。 5点目は「うーんの思想」という。何が「うーん」かといいますと、参加者が考える時間を大切にするという思想です。
伊藤 はい、では西川さん。
西川 私は今日、基調講演でおっしゃっていました小山内先生の、災害から逃れられない、迎え撃つのだという中で、災害への備えということで、身近なものは自分自身でやっていくことが一番大事ではないか。特に今日この会場に参加された皆様に、自分がいつも実践していることで一つ、ホイッスル(ホイッスルを吹き、ピーッという音)、もう一つこのライト(点灯する動作)ですね。いまちょっと接触不良でありますけれども、これは胸に付けて両手が使えますので、いわゆる常にどこへ行くにも携帯しております。特にここは地下でありますので、非常災害時、停電があります。でも、誘導灯は建築基準法、消防法で義務づけられておりますけれども、災害時は何が起きるかわからないということで、自分自身を自ら守るということが防災の基本であると思います。以上です。
伊藤 はい、では室崎さん。
室崎 私は、心情的には大きなことをボランティアに期待したいのですけれども、防災をやる立場からしますと、あんまり期待しないようにしようと思っています。 それは、なぜかと言うと、緊急時というのは、ボランティアの人が本当にあてになるのか、あてにならないのか識別する必要がある。やはりそういう意味で、きちっと責任を果たしてもらわないと困るからであります。
その線の引き方が非常に難しい。だから、じゃあ参加するなというように言えないわけですね。ですから、そこが非常に難しいところで、やはりあてになる戦力とあてにならない戦力の境目をどうやって見極めていくのかということを考えて。ちょっと水を差すようなことで申し訳ないのですけど、そういう一面もある。
緊急時のボランティアというのは、やっぱり責任を果たすという、そういう意味で教育という場からすると、責任感をどうやって育てるかということを同時にやらないとうまくいかないというように思います。
伊藤 次は山田さん、お願いします。
山田 特にありません。これからも頑張ってやっていきたいなと思っているだけです。
伊藤 そうですか。では石井さん、お願いします。
石井 はい、先ほど笠原さんがおっしゃったことですが、若い方の時期はそういうことでよいと思っているのですが、ここにおられる皆さんはそういった若い人たちが、人生のこれからのときにやっていくところ、支える側のお立場というか、年代というか、そういう部分もあるような気がします。ですから、若い人たちのボランティア活動はそんなものだという前提でそのよさを一緒に味わったり、時には発言もしたり、その環境を作ったり、そんなことを少し認識していかないと仕方がないのかなあというのが何となく思っていることです、はい。
伊藤 ありがとうございました。
皆さんから多彩なお話、そして貴重なお話をいただきまして、私が整理をしなくても、皆さんのお話一つひとつが全部整理されておりましたので、あえてまとめを行いませんけれども、阪神・淡路大震災をはじめとするいろいろな災害でボランティア活動をしてきた若者たちも、おそらくその活動を通じてさまざまなことを学んだと思います。
というのは、例えば、人の温かさであるとか、あるいは相手の立場に立ってものを考えるということの大切さを学んだと思いますし、そんな中で、やはりもう一人の自分というのを発見してきたかもしれないし、それとともに、いろいろな意味で社会的な視野を広げてきたのではないかと思います。
こういう活動を通じて学んだ貴重な体験を、社会に向けて、さらには先ほど小山内さんがカンボジアのお話をなさいましたけれども、広く世界の国々に向けて発信をしてほしいと思うわけです。
それとともに、社会の側もそうしたボランティアの若者が活動しやすいような社会の仕組みや環境を作っていくことが、これから求められていくのではないのかと、感じた次第です。
壇上の皆さん、長い時間、ありがとうございました。会場の皆さんもありがとうございました。これで終わらせていただきます(拍手)。
