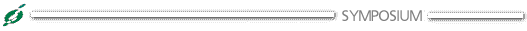
伊藤 それでは、次に石井さんにお願いをいたします。石井さんは、先ほど高校生おふたりの司会をしてくださったわけですが、昨日のスクール(高校生防災ボランティアスクール in OSAKA)の報告も含めてお話をお願いします。
石井 まず、昨日の報告をさせていただこうと思います。皆さん(38名の高校生の方)が9時15分にオオサカサンパレスに集合されて、そこでオリエンテーションを受け、バスで兵庫県西宮市の高須町復興住宅というところへ移動をして、10時半ぐらいに到着しました。
それから、2時半まで炊き出しと、子どもが遊んだりできるゲームのコーナーを運営をして、それと最後にちょっとした清掃ですね、復興住宅の敷地内を清掃して、またバスに乗り、帰りのバスの中では救急救命法と、それからロープの使い方の講習を受けて、3時半ぐらいにまたオオサカサンパレスに戻りました。
約1時間、ディスカッションというか、反省会というか。今日何がよかったか、どんなことを自分たちの地域に持って帰ろうかというような話し合いの場を持って、それでそれぞれ各地のご自分のおうちに帰って行かれました。だいたい、全体はこんな感じだったのですが、そういう中で、38人が大きく4つの作業に分かれました。10人、10人、8人、5人、5人という班に分かれて、10人はまず炊き込みご飯の班。10人と8人がそれぞれ豚汁を作りました。鍋が2つありましたので、2班に分かれて作業したわけです。5人が子どものコーナーの担当。そして、5人が復興住宅での呼び込みの活動をしました。
といいますのは、復興住宅は400世帯ほどの、仮設住宅からの入居の方がほとんどという新築の非常にきれいな高層住宅なのですが、そのうち60世帯がシルバー世帯ということで、要介護世帯です。住宅の方々には、ご自分たちで自発的に炊き出しをしている集会場のようなところに来て食べていただくようにと考えて、チラシはまいてあったのですが、要介護世帯の方は、それだけではたぶんお見えにならないだろうということで、その方たちに「どうぞ来てください」というふれあい訪問的な声かけをする班を作りました。ですから子どもの班とお年寄りに声をかけて、もし来てくださるというときは介助をする、そのような役割を担っている人が5人ずついました。 その声かけですが、LSA(ライフサポートアドバイザー)という方がおふたりで、その復興住宅にお住まいの高齢者、障害者のケアを担当されています。その方たちがついていて、きちんと高校生たちを紹介してくださって、もしものときはお助けするというような、そういう形で、お年寄りへの介助的なことを行いました。
また、先ほど申し上げました、10人、10人、8人の炊き出しの炊き込みご飯と豚汁の人たちですが、この人たちはその合間をぬって、手の空いてる人が炊き出しを食べていただくための会場設営、それから受付接待、そういったこともみんなでやるということが役割分担になっていました。
その割り振りと役割分担をどうするかということの話し合いは、行きのバスの中で、全員で合意を取る方法を探して、最終的にはジャンケンをして、自分はこの班ということを納得した形で行ってもらいました。
10時半から2時半の作業で、250食分の材料は用意しておいたのですが、150人くらいいらっしゃったと思います。要介護世帯からは、16名来てくださいました。その中で3名、車いすの方がいらっしゃいました。車いす補助は、先ほどの5人の参加者がやってくださいました。
そんな感じで進んでいったのでかなり忙しかったですね。しかもその10時半から2時半のうちの1時過ぎから2時頃までは、被災者の方のお話を聞くということで、4名の住民の方に当時の話を振り返っていただく時間を持ちましたので、その間は子どもたちは全員全く手を止めて、椅子に座って話を聞くという設定だったのです。10時半から2時半はもう大急ぎで、実は最初から設定に無理がありました。これは現場の運営サイド、私どもお世話させていただいた側の見解ですけれども。
250食の炊き込みご飯と豚汁と、給仕も片づけも全部というのを、38人の会ったこともない高校生たちが初めてのところにやって来て、さてできるのかというのは、よっぽど経験があって、敏速であれば可能かもしれませんが、基本的に不可能でしょう。それは、断った方がよいとまで言ったリーダーもいたくらいです。当日は6人のリーダーがサポートに回りましたが、事前の打ち合わせの段階で基本的に無理だというように判断していました。
それで、何があっても、どんな事故があっても完了させるプランを組みました。できるだけ作業は高校生の人たちにやってもらうのだけれども、入念な下準備と間に合わないときの補助のやり方というのを、いく通りもリーダーの方に考えていただいたのです。
ですが、残念ながら、高校生たちは、当日、復興住宅に到着しバスを降りた途端にだらだらと歩き始めたのですね。6人のリーダーと私は全員目配せで、覚悟を決めまして、そこからはもう残念なのですが、トップダウン系の「ほら、そこ動いて」という形で「はい、あんたこっち、一班こっち、ほらそこ手が止まってる」というような感じでした。ドゥアーッとまくしたてるというやり方で、怒涛の如く2時半まで一気にいったという感じなので、たぶん高校生は、あれだけよかった、よかったと言ってくれていますけれど、もうわけわからなかったというのが現実だったのではないかなという気がします。
強烈なリーダーに引っ張られて、言われるままに動く、これでさあボランティア体験なのだと言ってよいのかどうかというぐらいの現状だったと思います。戦場でした。 おまけにマスコミの方が大変たくさんいらっしゃいまして、「どいてください」と言ってもどいてくれないのですね。一番熱い鍋を高校生が持ってて、「そ こどいてください、危ないですその子」って言っても、「あっ、ちょっとお願いします」「お願いしますじゃないでしょう、どきなさい」と言って、言ってもどかないのですね。さすがに、後からそのことの苦情が高校生たちからも出ました。
そんな中での作業だったので、現場をご覧になったら大変殺気立っていたのですね。ビデオは非常に何かよいムードで進んでいましたが、その中で非常によく動きました、高校生は。なので、一体感があったのではないかと思います。やり遂げたという一体感があったのではないかと思います。
どうしてこういうことを申し上げたかというと、私たちも考えたのです。果たして、本当にこれで防災ボランティア体験をしていただいたことになるのだろうかと。 一応、会場は復興住宅ですから、何となく災害がからんでいますけれど、4年もたつと防災を復興支援と考えていただけるのであれば防災ボランティアかもしれないけど、それはよくわからない。防災ボランティア体験をしてもらうなら、避難訓練でも行った方がよいのではないかといったリーダーもおりました。
ですが、あえて復興住宅で被災の体験者と出会っていただくという設定の、しかも限られた時間の中で、与えられた役割の中で自発的に行動し、自分で考え、周りととりあえず輪を組むということができたのであれば、これでも十分一つの体験としました。高校生が、自分で決める、行動するということに多くの制約がつくからこそ、枠の中でやれることを皆さんにやっていただければ、よいのではないかというところで、リーダーたちも納得し、今回の機会となったのです。
感想云々は先ほどご覧いただきましたので、その中で子どもたちはああいったことを受け止めてくれたようです。ただ、非常に観念論が多かったですね。最初、感想はというと「ふれあえた」「わかりあえた」「被災者の人と出会えた」「納得できた」。「ふれあえた」と、それから「わかりあえた」がものすごく多かったですね。
何に「ふれあえた」と感じて、何に「出会えた」と「わかりあえた」と感じたのか。相手を尊重し、相手の目線でものが言えたというように、そんなコメントが後から出てくるわけですが、どんな体験からそう思ったのか、ということがなかなか出にくかったです。
それと、状況説明をきちんとできる子が少なかったです。「あなた何したの」って聞いたら「ええ、炊き出し」。でも、実はネギを切って、大根を切ってって、1日の仕事の流れはいろいろとあったわけですが、そのあたりを認識しにくいようでした。 どちらかというと思いの部分。そこで自分が何を感じて、何を思ってというところに非常に関心の高い子が多かったなあというのが実感でした。それは、よい悪いではなくて、ただ事実としてそうだったのだなあというように感じただけです。 そういうところをお手伝いさせていただいたのが、私が日頃一緒にやってる仲間たちでした。
伊藤 ひとまわりパネリストの皆さんからのご発言が終わりましたので、それではこれから2巡目に入りたいと思いますが、阪神・淡路大震災の後のボランティア活動でもいろいろな問題点、反省点があったと思います。
例えば、全国から善意の人々が駆けつけたけれども、受入側の態勢が全くできていなかったとか、駆けつけたのはよいのだが、何をやってよいのかわからなかったとか、あるいはボランティアに行って何をやったかというと、荷物の仕分けにほとんどの時間を割いてしまったとか、いろいろな言葉を聞きました。
それから、やはり行政側がどうも「ボランティアを使う」というような意識になってしまっている。ボランティアを、単なる労働力としか考えていないというような批判も出てきたと思っております。
やはり、ボランティアというのは行政とも対等であるし、被災者とも対等の立場でなければいけないと思っています。
そこで、今後ボランティア活動を、どのように組織化していくか、今後の発展のためにどのような方向性を与えていくかなどについて、2巡目として皆さんから伺いたいと思います。
では、最初は室崎さんからお願いしたいと思います。よろしくお願いします。室崎 少しトップバッターは荷が重いのですけれども、私なりに感じたり、考えていることを少しお話をさせていただきたいなと思っています。 4つのことが大切かなというように思っているのですね。一つは時間に関する問題、時間の問題です。
阪神・淡路大震災のときに、たくさんの若者が応援に来てくれました。若者が応援に来てくれた、やはり若者が一番正義感、感受性、行動力を持ってると。まさに、だからこそ若者が多かったのですが、もう一つだけ理由があったのですね。 それは、2月、3月は比較的、「若者にとって」時間のある(受験生は知りませんけれども)春休みにかかった。春休みにずいぶんたくさんの若者が来てくれたわけです。
それは時間ができたからなのですね。もし、あれがまた別の季節、例えば、中間テストとか、何か非常に大切なときだったらどれだけの若者が来ただろうかというように思うわけです。
ともかく日本人は、若者から年寄りまで、みんながみんなと言うとちょっと極端ですけど、時間がない。これは若者だけではなくて、例えば、我々の世代でも、やはり何とかしてあげたい、会社を休んででも行きたい。会社の上司に「阪神・淡路にボランティアに行きたい」と言ったら「君の仕事はどうなるんだ」というようなことで許可が下りない。「いや、年休を取って」「年休もだめだ」というような感じですよね。 要するに、仕事と勉強、いろいろそういうものでがんじがらめになっていて、やっぱり自分の時間でありながら自由にできる時間がないという。
これはボランティアだけに限ったことではないですけれども、やはりもう少しゆとりのある時間というものを、うまく社会的に作り出していっておかないと、たぶんボランティアというのはそううまくいかない。
だから、阪神・淡路大震災のとき、非常に僕はかわいそうだったと思ったのは、一生懸命やって、ただその成果が見えないままみんな途中で、後ろ髪を引かれる思いで帰って行くわけです。学校が始まりますから、新学期になって帰って行く。僕は非常につらい気持ちだ。もっとやっておりたいと思った。夏休みになるとまた帰って来てくれるわけですけれども。
やはりそういうときに当然、会社でも特別休暇を与えていただければよいし、学校においても学校以上の勉強ができるわけですから、それは何か別の読み方をして、やはりそういうボランティア活動というのをその若者に保障してあげる必要があるのではないかと思います。
それから2つ目が、これはいま伊藤さんが言われたことと関係するのですけれども、受け入れる側の問題というのは非常に大きいのですよ。被災地でもずいぶんこういう気持ちが強い。要するに「人様に助けてもらうな」というところ。家の中で困っていても、「いや、人の力は借りたくない」というか、何かそういう「武士は食わねど高楊枝」みたいな何かそういうところが、行政にもありますし、それから地域のコミュニティにもあります。
要するに、人の温かい心をうまく受け入れる、そういう心というものを持ち合わせていない。それは、そういうトレーニング、訓練というか、お互いに助け合ったり、支え合ったりする経験がないわけですね。
この2つ目に言っていることは、僕は空間の問題と言っているのですが、空間の問題というのは物理的な空間ではなくて、お父さんの居場所がないと、我が家なんかときどき言うのですけれど、同じ居場所です。どこに居てたらよいのかという。 ボランティアが被災地に来て、ボランティアの居場所がなかった。みんなすごく場所があって、すぐやれたわけでなくて、かなりのボランティアの若者がかなり傷ついて帰りました。
善意でやってやろうとせっかく来たのに、働く場所がないというか、何かうまく被災地の人の心とマッチングしないで失意のままにというか、「こんなんだったら来るんじゃなかった」と。
それは、たぶん来たボランティアに原因があるのではなくて、ボランティアを受け入れる地域社会の方にそういう問題があったように思いますね。
だから、このボランティアの問題というのは、ボランティアの行く側、ボランティアをどう組織したらよいかとか、どう作ったらよいかということばかり考えてるのではなくて、ボランティアの人たちと地域社会(災害を受けた社会)が、どううまく打ち解けていくかというか、受け入れていくかという、要するに心を開く地域社会というものを作っていかないといけない。
僕は、それはやっぱりコミュニティというものが、もう少し新しい段階というか、もっといろいろな地域の人たち、いろいろな世界の、これは国際交流ということとも一緒なのですけど、やっぱり窓口、心を開くような社会であったりする必要があると。これはいろいろな意味で国際交流の話でもそうですけども、日本というのはちょっと苦手ですね、鎖国だったものですから。
だから、やっぱりその心を開くという、心を開く地域社会、これもひょっとしたら抽象的だっていうようにお叱り受けるかもしれませんけれども。だから、コミュニティがもっと開かれたコミュニティというか、そういう地域社会というので少ししっかり考えていかないといけないのではないかというのが、僕は2つ目のポイントかなというように思っています。
3つ目は、時間、空間とくると、もう一つ「間」がつくやつがある。これは人間の問題なのですね、人間。
人間というのは、これはいろいろな意味の人間というのがあるのですけれど、ここで申し上げるのは、やっぱりボランティア自身というか、ボランティア活動に参加するというか、ボランティアというよりは、日本の一人ひとりの人間がいろいろな意味での技術、技能っていうものを身につけないといけないというように思います。
被災地に行って、いろいろお手伝いをしたり、やっぱり被災地の復旧にプラスになるようにするわけですから、プラスになっていこうと思うと、助ける人も、要するに、いやこう言うたらまた怒られるかもわかりませんが、足手まといになってはいけないのです。テキパキと動かないといけないし、相手の求めることをしっかりやっていかないといけないし。
極端に言って、被災地に行ったけれど、「いやご飯は炊けません」「いや大きい、重たい物は運べません」「いや行って話はできません」「あれはできません。でも何かやりたいです」というように来られたときには、たまったものではないですね。 そういう意味で言うと、やっぱり人と話をする技能、人と人とのふれあう技術、技能、それからご飯を作る。特にこの辺だと、例えば、そういう心肺蘇生法なんかの技術を知っている人たちが日本にどれだけいるかというと、大昔の人たちは当然、ご飯も炊けたりいろいろなことができるのですけれど、だんだんいまの若者はできないことが多いって言いますか。逆に言って、いや、被災地に行ってご飯を炊けるようになったからよかったと言われたら、僕はたまったものではない。それもよいのですけれど、ご飯の炊く勉強をしにボランティアに来てもらうわけでは、まあ、それも一つのメリットだと思いますけれども。
ただ、やはりこういうことで、人と人とが一緒にやっていく技術、最低限の生きていく、生まれていく技術から始まって、できればそういう通信とか、それぞれの取り柄、医療だとか、怪我した人を助ける技術だとか、火が出たら水バケツで火を消す技術だとか、そういう最低限、生きていくための基礎的な技術を人間としてみんなが身につけていっておかないと、何か心だけあって、今度は能力がついていかないということがあります。そういうことを鍛練したり、トレーニングしたりする場が、やっぱり非常にいま欠けている。
だから、教育なのか、あるいはコミュニティの中でそういう技術を身につけるのか、どこで身につけるのかということですけれども、やはりそういうためのいろいろなトレーニングの場、あるいは学校、あるいはそういったところでしっかりと最低限の生活技術というものを身につけるようにして、やっぱりだからこれはボランティアを育てるという意味ではなくて、素晴らしい人間をこの日本の社会で育てていくということをしっかり、その延長線上に僕はボランティアというものがあるように思います。 それから、4つ目。もうこれは「間」がないですね。4つあると言って、ああ困ったなと思うのですけど、4つ目は人と時と空間というか、人間と空間と時間という3つの間というか、間をつなぐもの、情報ネットワークという結びつけるものというのが4つ目だろうと思います。
ネットワークというのはいろいろあります。全国のボランティアネットワークって、だんだん整備されてきましたけれども、いろんな形で人を結びつける、あるいは、ボランティアがいろいろやろうと思ったら、そのうち必要な情報のネットワークが張り巡らされていて、いろいろな情報が平等にみんなに提供される。そういう意味での結びつきというか、そういう意味では結びつきというのは、だからボランティアとボランティア、あるいは被災地と非被災地という、あるいはそういうところに溝を作るのではなくて、手と手をつないでいくようなシステムをもっと日本の中に網の目のように作っていくというようなことが必要で、以上の4つがやっぱりこれからもっとボランティアというものをうまく受け入れ、うまくボランティアが活動できるような社会を作るために必要ではないかというように思っております。
伊藤 ありがとうございました。
いま「教育」という言葉が出てきましたけれども、日本では学校教育の中にボランティアというのが位置づけられていないのです。
1985年にメキシコで大地震があって、メキシコシティで大きな被害が出た。その取材で見た光景ですが、大勢の若者たちが交通整理をやったり、あるいは潰れた建物の瓦礫を片づけているのですね。
そういう姿を見てたいへん感動したのですが、聞いてみたら、メキシコでは高等学校の教科の中にボランティアという科目があるのだそうです。
その頃はまだ日本では、ボランティアというものが大きくクローズアップされていない時代でした。今後は、学校教育の中などでボランティアの心を位置づけていくことも大切なのではないかと思います。
そこで、教育という点では、石井さんも、昨日は高校生に対して大切な教育をなさったのではないかと思います。
石井さん、いかがですか。昨日の感想も含めて今後の課題、あるいは全国ネットワーク事務局の課題として、将来に向かっての思いがあれば、話していただけませんか。
石井 まず昨日に関して申し上げると、環境準備をして、みんなが動きやすいように、先ほど「こら」とかって言いましたけど、そういう叱咤激励も含めて、直接彼らにいろいろな環境を提示してくれたのは、うちのリーダーたち6人でした。
一方、私は国土庁をはじめとするスクールの主催者の方ですとか、高校生の方ですとか、いろいろな方たちが、とりあえず折り合うところのお手伝いをさせていただいた。それが私の立場だったのですね。
そして今、私がここに座らせていただいている理由があるとすれば、それは震災。震災のとき、実は私の家は全壊していまして、たまたま小さな学習塾を経営してたのですが、そこが緊急救援センターになりまして、何千人、もしかしたら何万人に届くぐらいのボランティアをしたいとおっしゃる方を小さな塾でお預かりしたことだと思います。
そういったところで、常に被災された方であるとか、ボランティア活動を受けたいという方と、ボランティア活動をやってみたいという方の思いのずれですとか、困難である事項のずれですとか、そういったところの調整業務をひたすらやり続けた4年だったというか、そんなようなことをしてきたのですね。
被災者も自分が何に困ってて、どういう支援を得れば自立再建できるかということを伝えるのは下手です。私も含めて、とても下手です。
それで、ボランティアに来られる方も、ご自分がどうしたいのか、どこまでできるのか、どうしようかということを相談しながら、相手の気持ちとも折り合ってやっていくということはあまりお上手じゃなかったというのが、阪神・淡路大震災で感じたことの一部です。
もちろんそれだけではなくて、よいことはもう皆さんがおっしゃってくださったので、私は、そこの部分だけ取り上げるので、誤解しないでいただきたいのですが、そんなようなことが常に困難とかトラブルの方を調整してますので、どうしても悲観的な部分が毎日の中でも出がちなのですけれども、今回も、震災時もひどかったです。上手くいかないこと、本質を見失うことの連続。
ただ、その結果、県外から来て帰っていかれる方は、もちろん後ろ髪を引かれる思いもあったかもしれませんが、ものすごい達成感と幸福感をお感じになって、また新しい人生を頑張って生きていこう、ぐらいの人は多かったようですね。若いボランティアさんの中に、職業を決めて帰った高校生、大学生がいっぱいいました。
何千人という高校生、大学生の方をお世話させていただきましたが、その方たちは、被災地に来て風邪も引くし、お金もないしみたいな体験をしながら、彼らはその体験の中でやっぱり何かを得ていく素晴らしいことなのだということもわかりましたし、基本的に被災者の方もボランティアの方も、皆さんやっぱり自分が大事、自己実現であるとか、自分の暮らしであるとかの充実を求めて動いていらっしゃるんだということもよくわかったのですね。
で、そのすべて全部ひっくるめて、とりあえず災害というものは出会いのきっかけになるというのが、4年間で私がとりあえず認識したことです。
防災ボランティアがどうあるべきかはわかりませんが、特に緊急救援時、那須の水害は約1か月間で、たぶんセンターを閉められたのではないかと思いますが、そういう緊急救援時の人と人との出会い、そこで起こる出来事というのは、いろいろな方の一生を左右するような出来事になるような気がしますので、その日そのときそれからまあ何か月かというところで、どんな人の出会いとどういう具体的作業の共有があるかというのは、工夫すればよいのではないかなあということを思いました。
今日はそういった視点から「震災がつなぐ全国ネットワーク」の事務局長というのが今日の私の肩書なのですけれども、資料の中にそこの資料を入れさせていただいておりまして、ちょっとこのイメージだけ伝えて、その私のお答えというようにさせていただきたいと思います。
できることを、できるときに、できる範囲でという、一応無償で、特に緊急救援時に心を持って、災害に遭った方の支援にあたるということを考えた場合に、できたらあんまりそれぞれの方の日常とかけ離れたことよりは、得意なことであるとか、手をつけやすいところで関わっていただいた方がスムーズかなというのが感じたことでした。
やっぱり、小さなものをいじったりする作業が上手な人に人間のコーディネートをしろというよりは、その方には何かちょっと壊れたものの修理とか、そういうことをお願いした方がご本人の混乱も少ないですし、受ける側の驚きも少ないというようなことを感じたのですね。
ただ、自分がせっかくの機会だから、いままで全くやったことのないことをやってみたいとか、昨日のように包丁を握ったことのない子が包丁を握って料理がしたくなったということももちろん状況の中であるのはよいのですが、どこかで災害が起こった時、特に緊急を要する発災直後の3日間にさあみんなで力を合わせようというときは、すっと乗りやすいことが何なのかをご本人たちも持っておいてくださったらよりよいと思います。
「バザーならできるよ」とか、「とりあえずじゃあ雑巾を何千枚か用意することは自分たちのグループでできるよ」とか、「100人の人間であればすぐ現地に派遣できます。そのときに土木作業が得意です。いや、心のケアが得意なんです」みたいな提案が欲しいですね。そして日常活動でのテーマと緊急時にそのことを持ち込んで被災地に行けますよという内容がうまく折り合ったら、みんな楽に災害の活動に参加してもらえるのではないかということをいま考えています。それらの力を合わせると、緊急時にこんなふうに支え合えるということを作っていこうというのがこの「震災がつなぐ全国ネットワーク」です。
阪神・淡路大震災の体験者たちが地元に帰られて、この体験を次に活かす仕掛けをどう残そうというところで浮かび上がってきた案なので、だからちょっと残念なのですが、災害があってくれてなんぼのものなのですね、これは。
去年の夏はありがたいことに(?)3つも水害が、高知、那須、福島と起こりましたので、その3地域で民間の支援センターの立ち上げというのを実験的にお手伝いさせていただきました。物資は止めてくれと言われたら、全国の人に物資を送るなという発信をするのが仕事になることもあります。
発災時に、できる人とやってほしいことがうまく回っていくように、平常時には、元々物資を送りたい人のところにこんな物資がほしいという案内がうまく流れるようにというか、そういう調整をしていく仕事をやっていく人間、つまりコーディネーターの養成もやってみています。
そして、皆さんにもそこからの情報を受け取ってもらいやすいようにしようと。できるだけ、その人たちが顔の見える関係で、そのときだけの関係にならないようにしていこうというのが、この「震災がつなぐ全国ネットワーク」の取り組みです。
なぜ顔の見える関係、友だち関係の方がよいかというと、緊急時に「何々、今日これで送りますから」と言ったときに、例えば、私が「すいませんが、それはちょっと1週間ほどお待ちいただけませんか」と。「うちのいまの現状では、ちょっと何とも申し上げにくくて」などという場合、この「何とも申し上げにくい」ということの理由をきちっと説明したり、そこの整合性を求めるのが、その時はじめて会って、その上、思いの熱い方なのですね。
ところが、ある程度おつきあいがあって、「どうしてもなんです」と言えば、信頼関係で「じゃあいま1時間はこの人は理由が言える状況じゃないな」というようなムードが察し合いやすいというか・・・。少しでもコミュニケーションを楽にしたければ、表現の癖も含めて、緊急時のどういうときに石井さんは驚いてパニックになるかというようなこともわかっている仲間の方が「あっ、あれはちょっといま何か特別にあったんだろうから、じゃあ3日おいて電話したらよい情報が得られるかもしれない」となりやすいでしょう。なので、日常からそういったことをできるだけわかっていくように心がける前提で何かイベントをやってみるとよいと思います。そして、何かの災害があったらとりあえず一緒に共同作業をしてみる。そこで出会った友だち関係がまた次の災害に少しずつ生きていくように。
災害があるたびにネットワークが深くなって、次の災害時にいろいろな形での敏速な対応ができるようにというのを作っていこうとしてるのが、この「震災がつなぐ全国ネットワーク」の内容です。
なので、普通の一般会員のようなものと自由選択会員というのがあって、自由選択会員は「私は災害時にこんなことならできますよ」という自発的な名乗りをします。いわゆる登録ではないので、情報発信はかなりできたとしても、NOと言えるかということに関してのかなりの保障があります。その代わり、曖昧に登録だけをした「登録したのにボランティアできなかった。声かけがない」ということはおっしゃっていただけないようになります。
一応、とりあえず緊急時にはまずこれをやりますということを決めていただかなければいけないので、そのあたりではボランティアとしての登録をするようなものですけれども、ちょっと違うのですね。イメージを持って登録をしていただこうというような仕掛けです。
そんなものを作りながら、次の災害時に、また、災害の混乱ができるだけ少なくなるように作っていく、そのお世話役も必要だというようなことがいま4年経ってわかってきたことです。
伊藤 災害があるたびにネットワークが深まっていくというのは、少々皮肉なことかもしれませんが、実は、地震学でも大きな地震がなければ進展しないのでありまして、悲しいことかもしれませんが、よく似た構図になっていると思います。 それでは、西川さんもいろいろな意味で若者と関わり合ってこられたということで、ご提案があるのではないかと思いますが、よろしくお願いします。西川 はい。私は、まず阪神・淡路大震災のときにどんな活動をしておったのかということでありますけれども、自分はあの当時、揺れた朝、6時半から職場に入りまして、その当時はまだこちらの神戸の状態というのはテレビに映ってなかったのですよね。空白で、状態がわからない。大阪で震度4とか5とかいう、非常に大変な状態だなということだけしかわかっていなかった。
職場に入りまして、だんだんだんだんいろいろな映像がテレビから出てくるわけですね。それによって、これは大変なことだなと。
日本赤十字社愛知県支部へ電話して、自分が活動するかどうかという判断を仰いだのですけれども、14回か15回かけてもつながらないのですよね。「なんでなんだろうな、おかしいな」ということで災害対応電話に電話したら「いや実はこうなんだよ」ということで、非常災害時における電話のかけ方、これを皆さん方、特に私がボランティアだから言えることですけれども、災害、あるいは防災機関に災害時における、嫌がらせ電話はやめていただきたい。本人としては嫌がらせではないと考えているかもしれないけれど、私が愛知県支部で受け取った電話の中に、何本かそういう電話があるのですね。いわゆる災害時における救護活動を混乱させる。言い方は悪いですけれど、邪魔をするというね。
それぞれの組織が持っている電話回線の数は限りがありますね。それらがふさがってしまうと、緊急に連絡したくても、その人が受話器を置いて切らない限りできない。同じようなことが、聞いてみますと、消防にもあるし、警察にもあるのだと。 消防、警察においては、発信元がわかるわけですね。携帯であれば誰から入ってる、加入電話であればどこそこの誰々さんからの電話と。ただし、公衆電話においては、何々町何番地の何番の電話からとしか分からない。かけてる人が、嫌がらせであっても誰かわからないということです。自分もあくる日、日赤愛知県支部へ行って、とにかく情報収集担当ということでやった中では、そういう災害救護機関における余分な電話ですね、どうしても緊急でしなければならない電話は必要なのですけど、そうでない不要な電話が多いということが、阪神・淡路大震災の中で自分が経験したことです。これは非常に困ることだなということで、良識ある人であったら絶対そういうことはやってもらいたくないと思いました。
また、義援金については、まだその頃、阪神・淡路大震災という命名ではなくて、兵庫県南部地震ということで私も何十枚か義援金の領収書を切って仮設窓口で(大きいロビーの仮設窓口ですね)対応しました。その当時、日赤愛知県支部というのは愛知県庁の大きな建物ではなくて、別の合同庁舎の中に一緒に入っておりましたので、大通りからわかりにくい。
そういう中で、若い人たちの動きとして高校生なり大学生が義援金として出してくれたり、あるいは一番私が感動したのは一人のお年寄りですね。あるおばあちゃんが茶封筒を出して「私はなんにもできんけど、これで役に立つかねえ」ということでポンと封筒を出したのですね。その茶封筒というのは立つのですよね。中を開けますと、某銀行の帯封の付いたお金なのですね。
ですから、ものすごく私はその志については感動しましてね、そういうお年寄りがこの非常災害時のときに、このように心を痛めて見えるのだなということで、そういう全国からの大きな気持ちがこの阪神・淡路大震災に向けて復興を励ましているのだなというように感じましたけれども。
ただ、特に若い人に向けてどうかと言いますと、私はいままで各先生方のお話にもありますように、私が若い人に望むことというのは、構えるのではなくて素直に活動に入っていってもらえればよいのではないかな。何かやろうとして行くのではなくて、ためらうことなく、人間としての真心からすっと素直に入ってもらえればよいのではないかなあと。そうすれば一緒に活動できるのではないかなあというように思うのですね。
ただ、その背景として、私が感じることは、そういう若い人たちの育てられた環境、あるいは経験したこと、それによってものすごく違うのではないかなあと思います。自分もボーイスカウトのリーダーを15年ほど務めた中で体得したことでありますけれども、特に、いまの私どもの年代と、20歳前後の若い人たちの間というのはもう30年の年代の開きがあるわけですので、そういう中で、その子たちが育ってきた環境がですね、全然違うのですね。
私どもが生まれた時代というのは、まだ真空管ラジオでしたものでね、道も舗装されておりません。そういう年代において、ボランティアって何だとかって言うと、その当時、町内における道普請なのですね。みんなが通る道をみんなで直す。行政も貧しい時代でしたので、みんなが自分の通る道を自分たちで直す。これは勤労奉仕なのですけどね、そういうことをやっていた時代です。
いまはどうかといいますと、赤ちゃんを出産するのは、その当時はみんながほとんどが家庭内出産でしたですね。それが現在は、ホテルのような素晴らしい病院でオギャアと生まれて、すべて医療機関によって管理されている。すぐさま映像と言葉が、家にいるお父さんのところへ伝わるというような、もう恐ろしい電子情報の氾濫してる状態の中で育っていくわけです。
そういう中において、いまの私どもと若い子との間に何が違うかということは、その人たちが育ってきている生活環境が違うのではないかなというように思います。
また、その若い人たちもそういう環境の中で生まれて、例えば、ボーイスカウト活動、あるいはガールスカウト活動、海洋少年団活動、あるいは緑の少年団といったいろいろな組織に入って成長してきた若者と、全くそういうものに所属しないで、いわゆるフリーで学校だけで、あるいは大学までお受験だけで成長して、いざ社会へ出たら「ボランティアって何だ」ということなのですね。
ですから、そういう環境の中で、当然その若い人たちの育ってきた経過によって、人間の形成における多感な、若い年代における非常に感受性の高いときにそういう教育を受けたか受けないかによっても違うということで、これはこれから社会の仕組みとして若い人たちをいかに社会が見守って育てるかということですね。これが最終的には、そのボランティア活動に対する考え方をも左右するのではないかなというように私はとらえております。
では実際に、その若い人たちがどんなことについて嬉々として取り組むのかなということについて、自分なりの活動の中で思うことを述べますと、まず、やろうとしていることが、その若者たちにとって自発的な活動であることですね、自分から進んでやること。親や先生に指示されてやる活動ではないということですね。
そして、しかもいまの若い人たちというのは、もう非常にさばけていますので、すぐ結果が現れるもの、ゲームなんかでもそうですけれど。だから、実際にやってみて「ああ俺がやったんだ」というやりがいのあること、あるいは、その活動を通して、自分が充実感を味わえること。先ほど来、石井先生の中にもありましたけれども、そういう活動をやって満足すると言いますかね、そういうやりがいのある活動。 では具体的に何かと言うと、例えば、私も経験があるのですけれども、街頭における募金活動なんかで、目に見える活動なんていうのは最初は嫌がるのですけれども、いざやり始めるとのめり込んで、本当に真剣になって活動する。
何かと言うと、友だちとの競争も入るのですけれども、「うちの募金箱にこんなに入ったよ」と。そういう、いわゆる他を凌いで、優越感を味わえること。そういうことに対しては、非常にどん欲に活動をする。
また、障害者ボランティア、いわゆる福祉ボランティアで経験していることは、障害のある方と高校生などがお話しをして、すぐにレスポンス(応答)があるわけですね。「ここ痛い、どうですか」ってね。そういうことをやって、あるいは知的障害のある同じ年代の人を高校生が見ている場合なんかね、通じない部分があっても、それを本当にかみ砕いて、人間として対応する。
私は見ていて素晴らしいことだなと思うのですけれども、それもその場で実践で、人に教えを得ることなく、自分が体験する。そういうことが非常に、若い人の中でよい部分だなというように思っているのですけれども、そういうすぐ応答のあることについては真剣にやるのですね。
ただ、この中で私が思うに、何がどうなるかなあという中で、若者がボランティアの活動に引きつけられる動機、そういうものが何であるかなというように思いますと、何かをやろうといういわゆる若者が持っている特殊性ですね。自発活動に基づく若者特有の強い正義感であるとか、あるいは自分が持っているそういう精神の根源を揺さぶるようなこと。あるいは他を凌ぐ、他の人を凌ぐ優越感を味わえる。そういう行動をとって、自分がやったんだという充実感が味わえることについては、もう非常に若者としてそういう意気と言いますかね、そういうものを感じてやるのではないかなあということですね。
そういう中で、よい面ですね。活動やっていて、若い人たちが素晴らしいなと思うことは何だろうかなということで、一人で行動するという中においては、若干問題がある。なぜか。それは当然なのですね。情緒不安定な年代において、一人で完璧なことができるわけがないということで、それについては周りの人々がフォローしなければいけない。
何人かでグループを持って、2人、3人、4人、5人、そういう中で、グループとして活動する場合には、その中にリーダーを作って責任を持たせることができるのですね。
「君たちはこれこれこうだから、こうしなさいよ」ということでやる。あるいは「これについてどう思う」ということで回答をもらって、そのことに対して活動をさせる。そうすると、非常に結果がよいのですね。
また、そういういろいろなことに対して、非常に正義感が強いですね。例えば、一日ボランティアの高校生などの中では、車いすの取扱いには慣れていなくて、初めて体験するのですね、一日ボランティアの高校生というのは。その場で初めて車いすを押して「ああ、これは大変なんだなあ。でこぼこ道はこれは後ろから押さないけないんだなあ。前は上がるときにはこうしなきゃいけないんだな」。
障害者の方にとって一番よい体勢を作るにはどうするのだろうか。非常に真剣にやるのですけれども、そういう中で、強い正義感がある年代ですので、自分がやらなけりゃという使命感に燃えてやるのは非常によい結果が出るのですね。
だけれども、これが自発的な活動でなくて、精神的に不安定な状態の中では、周りの動きに流されてしまう。その少年たちがやろうとしてることと周りのことを比較して、「あっちのグループの方がいいな」と思うと、それらを誹謗したりする場合があるのですね。
これは若い年代の特徴だと思うのですけれども、そういう中で、大人が近くにいて適切なフォローをする、いわゆる指導者が必要であるなというように私は見ております。
あと私の思う中には、若い人たちの中で、先ほど石井先生もおっしゃっていましたけれども、自分に合った活動メニューであれば真剣になってやるけれども、どうしても合わないことというのはあるのですね。
私が日頃から思っている中で、非常災害時における防災ボランティア活動と、普段における日常の活動の中での福祉ボランティアとはおのずから違うというのはそこなのですね。
非常災害時には自分自身も危険、周りも非常に殺伐として危険な状態、そういう中での活動と、普段何の問題もなく一ボランティアとしてそういう体験をする場、あるいは日常の福祉ボランティアの活動とはおのずから違うということで、災害時におけるボランティア活動というのは、きちっと管理された状態ではなく危険と情報の混乱した防災活動の一部といえる内容であり、そういう災害時に対するボランティアの指導と言いますか、注意と言いますか、そういうことを与えてから活動に出すということで、災害時のボランティアにとっては、特にボランティア自身の安全とそれから、そのボランティア活動の秩序の維持、これを私は痛切に感じます。
特に、先ほどいろいろ暴言があったというお話を聞いた中で思い出したのですけれども、災害に遭われた方というのは、もう災害でうちひしがれている中で、さらに周りからの押し寄せた人的な被害を受けるわけですね。あえて「被害」と言いますけれども。そういうことが非常に、被災を受けた方の神経を逆なでしてるわけですね。
しかし、そういうこともきちっとしなければいけないということで、私はボランティア活動において、責任は当然なのですけども、ボランティア活動の秩序と、あとは安全管理ですね。ボランティアへ行った人がボランティアされてはだめなので、ボランティア活動の秩序と安全を管理しなければならないというように思っております。 これからの若者へ私が望むことは何かと申し上げますと、先ほど来申し上げましたけれども、人間として真心から活動に参加してほしい。何も構えることなく、普段の姿勢で入ってもらえればよいのではないかなと思います。
それから、若い人たちというのは、私たち以降の次の世代を背負って立つ人たちなのです。非常に大事な人たちなのですね。だからこそ期待することは一杯あるし、先ほど来、室崎先生のお話にありましたように、これからの若者の活動ステージはいっぱいあるのだよと。しかも、若者のパワーと現在持っているいろいろな現代感覚のそういう研ぎすまされた感性、そういったものが非常災害時には特に有効に働く。または、普段のボランティア活動においても、十分それが活かされるということで、若者のパワーと現代感覚の研ぎすまされた感性が必要であるというように思います。 最後に申し上げたいことは、特にいつも、どんなときにおいても、ボランティア活動においては自己完結、自分のことは自分で責任を持って自分で始末する。被災地においては、被災地にお世話にならない。あるいは福祉ボランティアにおいては、福祉の現場において自分がお世話にならないとい
う形で、常に自己完結で活動してほしい。
最後に、先ほど冒頭、大阪府知事が挨拶されました、「ボランティアさわやか」。この言葉に私は非常に感銘を受けるのですけれども、いわゆる防災ボランティア、いわゆる災害時において人間の心がすさんだ中で、ボランティア活動というのは大変なことだと思うのですね。
そういう中で、昔の私の年代は知っておるのですけれども、「どこの誰かは知らないけれど、疾風のように現れて、疾風のように去っていく」、いわゆる月光仮面の年代でありますが、災害時において必要なときに、ワッとボランティアが集まって必要なことをしていただく。やがて、災害が復旧して復興の鎚音がたてば、だれかれ言われることなく、自分の身を整えて、現場に生きる望みを与えて去っていく。非常にこの「ボランティアさわやか」という言葉、大阪府知事がおっしゃいましたけれど、私はすごく重みのある言葉だととらえております。
私の「ボランティア、若者たちに望むこと」という考え方の中で申し上げたいことは、以上であります。
伊藤 ありがとうございました。
●「パネルディスカッション」PAGE1へ● ●「パネルディスカッション」PAGE3へ●
●「パネルディスカッション」メインぺージに戻る●
●「シンポジウム」メインぺージに戻る● ●HOME●
