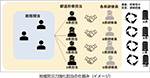第4節 令和6年能登半島地震の経験・教訓等を踏まえた予算・組織の拡充
(1)内閣府防災担当の予算拡充による災害対応体制の強化
内閣府防災担当では、令和6年度補正予算に350.5億円(災害救助費等(288.5億円)を含み、新地方創生交付金を含まず)を計上し、南海トラフ地震や首都直下地震などの次なる大規模災害も見据え、令和6年度能登半島地震の教訓も踏まえつつ、避難所の生活環境改善を始めとした災害対応体制の強化を進めている。また、令和8年度中の防災庁の設置を見据え、事前防災の充実を始めとする災害対応力の強化、災害対応の司令塔機能の強化を進めることとし、令和7年度当初予算を倍増(約146億円)し、令和6年度補正予算の執行とも連動させつつ、以下の取組等により、避難生活環境の抜本的改善や官民連携による人材育成の推進、防災DXの推進等に取り組んでいる。
(主な取組)
・新地方創生交付金(地域防災緊急整備型) 1,000億円の内数(令和6年度補正予算)
避難所の生活環境改善を始めとする地方公共団体の先進的な防災の取組の支援により、トイレカー、キッチン資機材、パーティション等の資機材の備蓄を推進することとしており、令和6年度事業として、都道府県、市区町村等における計783件、141億円の事業を採択し、資機材整備の支援を実施している。
・プッシュ型支援における内閣府備蓄物資の分散備蓄 13.6億円(令和6年度補正予算)
立川防災合同庁舎を含む、全国8地域に段ボールベッド等の簡易ベッドやパーティション、簡易トイレ、温かい食事を提供するための資機材や入浴のための資機材等、調達に時間を要するため一定の備蓄が必要なものについて、購入・分散備蓄を実施している。
・災害時に活用可能なキッチンカー・トレーラーハウス・トイレカー等に係る登録制度の創設 1.0億円(令和6年度補正予算及び令和7年度当初予算)
発災時における迅速な支援を可能とするため、キッチンカー・トレーラーハウス・トイレカー等の平時からの登録・データベース化を進めている。
・被災者支援団体への活動経費助成事業 4.7億円(令和6年度補正予算及び令和7年度当初予算)
NPO・ボランティア団体等が被災地支援に駆けつけるための交通費補助事業を令和7年1月に創設し、令和6年度は計214件、約4,000万円の交付決定を行った。令和7年度事業についても4月から開始している。
また、令和7年通常国会に提出した災害対策基本法等の改正法案への対応のため、NPO等の登録・管理データベースの整備、団体登録制度の周知を図る普及啓発等を行うこととしている。
・新総合防災情報システム(SOBO-WEB)の整備等 23.6億円(令和6年度補正予算)
防災デジタルプラットフォームの実現に向けた新総合防災情報システム(SOBO-WEB)の機能や連携の強化、及び災害時の迅速・効率的な物資支援を実現するために新物資システム(B-PLo)の機能強化や新総合防災情報システム(SOBO-WEB)との連携の早期実現に向けて推進している。
・防災情報システムの効果的な利活用促進 約2.2億円(令和7年度当初予算)
新物資システム(B-PLo)の利活用促進の研修・訓練や、新総合防災情報システム(SOBO-WEB)を活用した実践的な机上演習を推進することとしている。
・関係省庁による事前防災対策を推進する仕組みの創設(事前防災対策総合推進費) 約17億円(令和7年度当初予算)
関係省庁による事前防災対策を推進するため「事前防災対策総合推進費」を創設し、事前防災の強化につながる調査・研究開発、関係省庁と地方自治体等が連携して行う事前防災の強化の取組を推進することとしている。
(2)内閣府防災担当の組織・定員の拡充
風水害の発生が頻発化・激甚化するとともに、首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの大規模災害の発生が危惧される中、人命最優先に「防災立国」を構築する必要がある。このため、令和8年度中に防災庁を設置すべく内閣官房防災庁設置準備室を中心に準備を進めているところであるが、まずは、政府の災害対応の司令塔機能を担う内閣府防災担当の機能を予算・人事の両面で抜本的に強化するため、令和7年度に、地域防災力強化担当を創設するなど、定員を110人から220人へ大幅に拡充した。また、今後新たに「防災監」を創設することとしている。
(主な機能強化)
・「防災監」の新設
頻発化・激甚化する風水害や切迫する南海トラフ巨大地震等の大規模災害への対応強化のため、事前防災、災害応急対策から復旧・復興までの災害対応全般の司令塔として、対応を総括する事務次官級職員を新設することとしている。
・地域防災力の強化促進
令和7年4月に内閣府防災担当に地域防災力強化担当を創設し、各都道府県のカウンターパートとなる職員を配置した。備蓄促進や訓練研修、ボランティアとの連携などを促進するとともに、発災時には直ちに現地に入り、被災状況の把握や避難所環境の確保に従事することとしている。