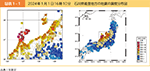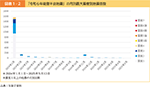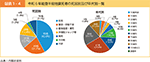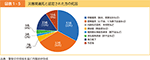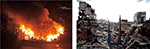第1章 令和6年能登半島地震等の概要
第1節 令和6年能登半島地震の概要と被害状況
(1)地震の概要
令和6年1月1日16時10分、石川県能登地方の深さ16km(暫定値)を震源とするマグニチュード7.6(暫定値)の地震(以下本特集において「本地震」という。)が発生し、石川県の輪島市及び志賀町で震度7を観測したほか、北海道から九州地方にかけて震度6強から1を観測した(図表1-1)。気象庁は、同日に、本地震及び令和2年12月以降の一連の地震活動について、名称を「令和6年能登半島地震」と定めた。
本地震の発生当初に比べ、地震活動は低下してきているものの、地震活動は依然として活発な状態が継続しており、令和6年1月1日16時から令和7年5月13日24時までの間に、最大震度1以上を観測した地震は2,185回発生している(図表1-2)。
(2)被害の概要
図表1-3は、「能登半島地震」の被害状況等について、阪神・淡路大震災、東日本大震災及び熊本地震と比較したものである。
<1>人的被害
本地震により多数の家屋倒壊が発生し、死者・行方不明者594名(うち災害関連死364名)の被害をもたらした。死者は石川県で581名(輪島市207名(行方不明者2名)、珠洲市170名、能登町66名、七尾市53名、穴水町49名、志賀町20名、内灘町6名、羽咋市5名、小松市1名、白山市1名、中能登町2名、金沢市1名)、新潟県で6名(新潟市4名、上越市2名)、富山県で5名(富山市1名、高岡市2名、氷見市1名、射水市1名)の犠牲者が発生した(令和7年5月13日時点)。
警察庁情報(令和7年2月末時点。石川県が発表した死者(災害関連死を除く。)のうち、警察が取り扱った226名を対象としたもの。)によると、直接死の死因の約4割が「圧死」、約2割が「窒息・呼吸不全」で、多くの人が倒壊した建物の下敷きとなったとみられる。また、寒さが影響して亡くなった「低体温症・凍死」が1割強と続いた。死者の年代別では70代が61名と最多で、80代50名、90代26名が続き、70代以上が約6割を占めた(図表1-4)。
また、直接死は輪島市と珠洲市に集中して犠牲者が発生した(それぞれ100名、97名)のに対し、災害関連死は広域で犠牲者が発生し、石川県で255名(輪島市80名、珠洲市54名、能登町49名、七尾市37名、穴水町22名、志賀町17名、内灘町5名、羽咋市3名、小松市1名、白山市1名、中能登町1名)、新潟県で4名(新潟市)、富山県で2名(高岡市)の261名となっている。
災害関連死による犠牲者のうち年齢が公表されている136名の死亡時の年齢の内訳は、90代以上が47名、80代が62名、70代が16名、60代が10名、50代が1名であり、80代以上が全体の約8割を占め、これまでの災害に比べ高齢者の割合が高い。また、死亡した経緯が公表されている158名の死因の内訳は、循環器系疾患が53名(約34%)、呼吸器系疾患が52名(約33%)で全体の約60%を占めており、体力低下も23名(約15%)となっている(令和6年11月21日時点)(図表1-5)。
<2>建物被害
住家被害は、秋田県、福島県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、京都府、兵庫県の1府10県で発生し、全壊が6,520棟(石川県6,151棟、富山県258棟、新潟県111棟)、半壊・一部破損が158,120棟(秋田県1棟(一部破損のみ)、福島県1棟(一部破損のみ)、埼玉県2棟(一部破損のみ)、石川県109,907棟、新潟県24,797棟、富山県22,544棟、福井県842棟、長野県21棟(一部破損のみ)、岐阜県2棟(一部破損のみ)、京都府2棟(一部損壊のみ)、兵庫県1棟(一部破損のみ))、床上・床下浸水が25棟(新潟県14棟、石川県11棟)となり、被災地全体で約16万5千棟の住家被害が発生した(令和7年5月13日時点)。また、石川県における非住家被害は約3万8千棟とされている(令和7年5月13日時点1。)。
(3)火災の発生状況と消火活動
火災は、石川県で11件、富山県で5件、新潟県で1件発生し、地元消防本部と消防団が消火活動に当たった。特に、石川県輪島市では、本地震直後に日本三大朝市の一つである輪島朝市で焼損棟数約240棟、焼失面積約49,000m2に及ぶ火災が発生した。本火災は、延焼しやすい木造密集地域で発生したもので、地震に伴い、断水による消火栓が使用できず、建物倒壊により一部の防火水槽が使用できないなど、消火活動が困難な状況の中で地元消防本部と消防団が消火活動を行い、2日7時30分に鎮圧し、6日17時10分に鎮火した。
その後、輪島朝市周辺では焼失し建物性が失われた倒壊家屋等について法務局による滅失登記を行い面的に公費解体が進められ、令和6年9月にはがれきの撤去がおおむね完了した。令和7年2月26日に輪島市が策定した「輪島市復興まちづくり計画」では、輪島朝市周辺を輪島市における復興のシンボルとして再建し、防災対策を強化しながら輪島朝市と商店街及び住まいの共生を目指した市街地整備を行う方針を掲げている。
「輪島市復興まちづくり計画」
https://www.city.wajima.ishikawa.jp/article/2024052800027/file_contents/honbu_2_siryou.pdf
(4)志賀原子力発電所における対応
政府は、本地震の発生を受けて、1月1日16時19分に原子力規制委員会・内閣府原子力事故合同警戒本部を設置し、北陸電力株式会社志賀原子力発電所等の情報発信等を行った。北陸電力株式会社志賀原子力発電所においては、使用済燃料プールの波打ち現象(スロッシング)による溢水(いっすい)、一部の変圧器故障による油漏れ等が発生したが、使用済燃料の冷却や電源等、必要とされる安全機能は確保されていることを確認した。
また、周辺の一部モニタリングポストにおいて測定が確認できない状況が生じたが、敷地近傍のモニタリングポスト指示値等に異常は認められず、発電所の安全確保に影響のある問題が生じていないことを確認した。その後、原子力規制委員会は、通信の信頼性向上に向けた対策を実施するとともに、無人機を用いた航空機モニタリング等によりモニタリング体制の機動力を強化し放射線モニタリングの多様化を図っている。今後、より強靱で機動的な放射線モニタリングシステムを構築するべく、迅速かつきめ細かい原子力災害対応を実現するための機動的なモニタリングや、複合災害時に機能維持するための強靱で多様な手段を備えたモニタリング、モニタリングの省人化・コスト削減・DX化の実現に資する、最新の技術・知見を取り入れた取組を進めていく。
1 石川県ホームページ「被害等の状況について(第204報)」
(参照:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/documents/higaihou_204.pdf)