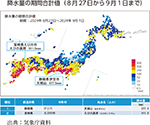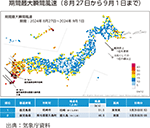第2節 令和6年台風第10号による災害
(1)概要
令和6年8月22日3時にマリアナ諸島近海で発生した台風第10号は、24日にかけて発達しながら北へ進み、25日には進路を北西へ変えて日本の南の海上を進んだ。台風は日本付近で動きが遅くなり、27日に非常に強い勢力となって奄美地方に接近し、その後進路を北に変えて九州南部に接近した。台風は、29日8時頃に強い勢力で鹿児島県薩摩川内市付近に上陸し、その後は比較的遅い速度で勢力を弱めながら九州北部地方から四国地方へ進み、30日21時に四国地方で熱帯低気圧に変わった。その後、台風から変わった熱帯低気圧は9月1日にかけて東海道沖へ進んだ。
動きの遅い台風第10号や太平洋高気圧の縁を回る暖かく湿った空気の影響が長く続いたため、26日以降、西日本から東日本にかけて太平洋側を中心に記録的な大雨となり、台風が西日本に接近・通過した28日から31日の間に鹿児島県(奄美地方を除く。)、宮崎県、大分県、徳島県、香川県、兵庫県及び三重県では線状降水帯が発生した。8月27日から9月1日にかけて総降水量は、九州南部や東海地方の多い所で900mmを超える大雨となったほか、九州北部地方や四国地方でも多い所で600mmを超える大雨となり、総降水量が平年の8月の月降水量の2倍以上となった所があった。
台風が非常に強い勢力で九州に接近したため、8月27日から29日にかけて鹿児島県では風速30m/sを超える猛烈な風を観測したほか、九州南部・奄美地方や九州北部地方では風速20m/sを超える非常に強い風を観測し、暴風となった所があった。また、期間中の最大風速では観測史上1位や8月の1位の観測値を更新した所があった。台風が数十年に一度の強さで北上し、鹿児島県にかなり接近する可能性が高まったことから、気象庁は28日に鹿児島県(奄美地方を除く。)の市町村に暴風、波浪、高潮の特別警報を発表した。
台風の接近に伴い、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んだため大気の状態が非常に不安定となり、宮崎県、鳥取県、埼玉県及び岐阜県で竜巻などの激しい突風による被害が発生した。
(2)被害状況
令和6年台風第10号により、1都10県において、国・都県管理の43河川が氾濫し、浸水被害が発生した。人的被害は、死者が8名(愛知県3名、徳島県1名、福岡県2名、佐賀県1名、鹿児島県1名)、重傷者が11名、軽傷者が120名となった。住家被害は、全壊が19棟、半壊・一部破損が2,991棟、床上・床下浸水が2,925棟となった(消防庁情報、令和7年3月24日時点)。
水道については最大断水戸数3,508戸、電力については全国各地で停電が発生し、九州電力送配電株式会社管内で最大停電戸数が約264,720戸に及ぶなど、ライフラインにも被害が発生した。また、高速道路での通行止めや鉄道の運休等により交通関係に大きな影響を与えたほか、路肩崩壊や落橋等により熊本県、大分県などにおいて一時孤立が発生した。
(3)政府の対応
政府は、令和6年8月26日15時に官邸に情報連絡室を設置し、関係省庁災害警戒会議を開催した。その後、28日8時に災害が発生するおそれがある段階で特定災害対策本部が設置され、情報連絡室は官邸対策室に改組された。同日9時に特定災害対策本部会議(第1回)が開催され(同月30日までに同会議を計3回開催)、本部長である松村内閣府特命担当大臣(防災)(当時)から、関係省庁に最大限の緊張感を持って対応することを要請したほか、各県へは被災するおそれのある県で災害救助法の適用ができること、国民へは躊躇なく避難することについて呼び掛けが行われた。また、8月29日には岸田内閣総理大臣(当時)出席の下、関係閣僚会議が開催された。
災害救助法については、災害が発生するおそれがある段階で、6県175市町村に適用された。その後、住家に被害が生じた7県22市町に、改めて災害救助法が適用された。また、激甚災害の指定については、令和6年8月26日から9月3日までの間の暴風雨及び豪雨による災害として、令和6年10月25日に指定政令の閣議決定を行い、同月30日に公布・施行された。