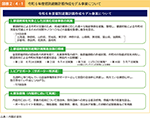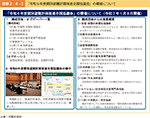2-4 個別避難計画の作成
近年の災害において多くの高齢者や障害者等が被災している。このため、「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」(以下「高齢者SWG」という。)の最終取りまとめ等において、自ら避難することが困難な高齢者・障害者等の避難行動要支援者ごとの避難支援等を実施するための計画である個別避難計画の作成を一層推進することにより、高齢者等の円滑かつ迅速な避難を図る必要があるとの指摘を受けた。そして、一部の市町村において作成が進められている個別避難計画について、全国的に作成を推進する観点から、個別避難計画の作成を市町村の努力義務とすることが適当とされた。
高齢者SWGからの提言を踏まえ、災害対策基本法が令和3年5月に改正・施行されたことを受け、市町村における個別避難計画の円滑な作成を推進するため、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を改定・公表し、市町村が優先度が高いと判断する避難行動要支援者について、おおむね5年程度で個別避難計画の作成に取り組むことや個別避難計画の作成手順などを示した。
個別避難計画作成の所要経費については、令和3年度に新たに地方交付税措置を講ずることとされ、令和7年度においても引き続き講ずることとされている。
個別避難計画を作成する市町村により、災害の態様やハザードの状況、気候に加え、人口規模、年齢構成、避難先の確保状況など、地域の状況が異なり、個別避難計画の作成に当たって課題となる事柄は様々である。
このため、個別避難計画作成モデル事業を通じて、令和6年度71自治体(令和3年度以降延べ235自治体)を支援し、個別避難計画の効果的・効率的な作成手法を構築して、全国の自治体に対し、計画作成のプロセス及びノウハウの共有を図った(図表2-4-1)。
令和6年度からは、個別避難計画推進全国協議会を開催し、防災、福祉、保健等の関係者との協力の下、自治体における個別避難計画作成の取組の加速化を図っている(図表2-4-2)。
また、「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ」の取りまとめでは、実施すべき取組として、避難支援等の実施に当たっては、避難支援等関係者自身やその家族の安全が優先されること、屋内安全確保も避難であること、自宅が安全な場合に避難行動要支援者は自宅にとどまることができること、避難支援等実施者が避難支援等を実施できない場合であって現に要支援者が救助を必要としている場合には消防機関等に救助を求める連絡ができることに留意が必要であることなどが示された。
また、令和5年1月に作成した、個別避難計画の作成に取り組む市町村職員や関係者に作成手順の例を分かりやすくまとめた「個別避難計画の作成に取り組むみなさまへ」の見直しを行い、避難行動要支援者が最寄りの避難先や自宅の災害リスクを知ることが避難の可能性を高めるものであることなどの観点について追補を行った。これらの取組により、避難行動要支援者の避難の実効性を確保し、個別避難計画の全国的な作成推進を図った。
(参照:https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/r6kohou.html)