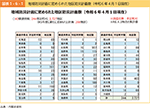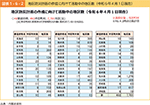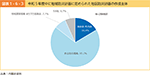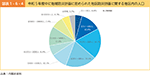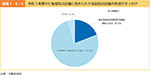1-6 住民主体の取組(地区防災計画の推進)
地区防災計画制度は、平成25年の災害対策基本法の改正により、地区居住者等(居住する住民及び事業所を有する事業者)が市町村と連携しながら、「自助」・「共助」による自発的な防災活動を推進し、地域の防災力を高めるために創設された制度である。これによって地区居住者等が地区防災計画(素案)を作成し、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めるよう、市町村防災会議に提案できることとされている。
地区防災計画は、地区内の住民、事業所、福祉関係者など様々な主体が、地域の災害リスクや、平時・災害時の防災行動、防災活動について話し合い、計画の素案の内容を自由に定め、その後、市町村地域防災計画に位置付けられることで、「自助」・「共助」と「公助」をつなげるものである。計画内容はもとより、地区住民等が話し合いを重ねることなど、作成過程も共助の力を強くする上で重要である。
令和6年4月1日現在、43都道府県244市区町村の2,727地区の地区防災計画が地域防災計画に定められ、さらに46都道府県463市区町村の7,701地区で地区防災計画の策定に向けた活動が行われている。制度創設から10年以上が経過し、地区防災計画が更に浸透していくことが期待される(図表1-6-1、図表1-6-2)。
(1)地区防災計画の動向
内閣府において、令和5年度中に地域防災計画に定められた298地区の地区防災計画の事例等を分析したところ、以下のような特徴がみられた(図表1-6-3、図表1-6-4、図表1-6-5)。
<1> 地区防災計画の作成主体は、69.1%が自主防災組織、16.4%が自治会・町内会であった。
<2> 地区内の人口については、「201~500人」(19.5%)が最も多く、「101~200人」(19.1%)が二番目に多かった。これらを合わせると101~500人の地区が約4割を占めた。
<3> 地区防災計画策定のきっかけは、76.2%の地区は「行政側からの働き掛けによるもの」であった。
このことから、地区防災計画の策定には行政による後押しが重要であると考えられる。
(2)地区防災計画の策定促進に向けた内閣府の取組
内閣府は、地区防災計画の策定促進のため、「地区防災計画ガイドライン」等の地区防災計画の策定の参考になる資料を作成し、また、地区防災計画を地域別・テーマ別に一覧できる「地区防災計画ライブラリ」を整備している。また、令和7年4月4日には、新たに「地区防災計画ガイドブック」を公表したほか、以下のとおりフォーラムや研修等を開催した。
(参照:https://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/index.html)

<1> 地区防災計画フォーラム2024「熊本地震とその後の地区防災計画づくり」及び「火山災害とコミュニティの防災活動」の開催
各地における地区防災計画づくりに関する事例や経験の共有を図り、地区防災計画の策定を促進するため、地区防災計画フォーラム2024「熊本地震とその後の地区防災計画づくり」を令和6年10月19日に、「火山災害とコミュニティの防災活動」を令和6年10月20日に、いずれも「防災推進国民大会(ぼうさいこくたい)2024」のセッションとして開催した。本フォーラムでは、熊本地震後の地区防災計画づくり、火山防災に向けた各地の地区防災計画づくりを踏まえて、有識者と内閣府担当官による議論が行われた。また、本フォーラムのアーカイブ動画を公開した。
<2> 地区防災計画の作成に関する基礎研修会の開催
地区防災計画づくりに取り組もうとしている住民やそれを支援する自治体職員を主な対象として、「地区防災計画の作成に関する基礎研修会」を令和6年11月13日に、「地区防災計画の作成に関する基礎研修会(応用編)」を令和7年1月24日に、オンラインで開催した。これらの研修会では、内閣府から基礎的説明を行い、内閣府や地区防災計画学会の地区防災計画モデル事業の対象地区等で先進的な取組を行っている住民、自治体職員、アドバイザーである大学教員等が登壇して、その取組について報告するとともに、パネルディスカッション形式による議論が行われた。
<3> 地区防災計画に関するモデル事業
内閣府は、平成26年度から地区防災計画の作成の支援のためのモデル事業を実施している。令和6年度は、千葉県富里市日吉台小学校区、愛知県西尾市上羽角町自主防災会、長崎県島原市安中地区及び沖縄県石垣市白保地区の4地区が対象となり、有識者や内閣府担当官の支援の下、地区防災計画づくりを進めた。
<4> 学術研究団体、事業者団体等との連携シンポジウムの開催
内閣府は、新たな取組として、地区防災計画を担当する自治体職員等で構成されている地区防災計画を推進するネットワーク(地区防’z)及び地区防災計画学会と連携して、令和6年7月27日に「能登半島地震等の教訓を踏まえた地区防災計画」をテーマに、オンラインでシンポジウムを開催した。地区防災計画づくりに精通した3団体の関係者が、能登半島地震等の教訓を踏まえた地区防災計画制度の在り方について議論を行った。また、同様に防災推進協議会及び地区防災計画学会と連携して近年の共助の防災活動の動きを踏まえ、令和7年3月1日に「企業とコミュニティの防災活動―能登半島地震、南海トラフ地震臨時情報発令等を受けた最近の共助の防災活動の動きを踏まえて―」をテーマに、オンラインでシンポジウムを開催した。2つの新しい連携シンポジウムは、それぞれ1,000人以上が参加した。