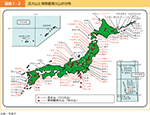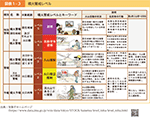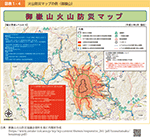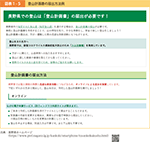第3節 登山者等の備え
平成26年(2014年)の御嶽山噴火災害の教訓を踏まえ、平成27年(2015年)には活火山法の改正により、登山者は自らの身を守る備えをするよう努めることとされた。登山時のみならず、観光で訪れる際にも以下のポイントを踏まえて行動することが望ましい1。
<1> 火山情報を集める
かつては、現在活動している、つまり噴火している火山は「活火山」、現在噴火していない火山は「休火山」あるいは「死火山」と呼ばれていた。しかし、火山の活動の寿命は長く、数百年程度の休止期間はほんのつかの間の眠りでしかないということから、噴火記録のある火山や今後噴火する可能性がある火山を全て「活火山」と分類する考え方が主流となった。
この考え方を踏まえ、平成15年(2003年)に火山噴火予知連絡会は「概ね過去1万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」を活火山として定義し直し、令和6年(2024年)4月時点で、火山調査研究推進本部政策委員会によって111の活火山が選定されている。2
活火山のうち50火山について、気象庁は、噴火の前兆等を捉えるために、地震計、監視カメラ等を整備し、関係機関(大学等研究機関や自治体・防災機関)からのデータ提供も受けながら、火山活動を24時間体制で観測・監視している(以下「常時観測火山」という。)。また、その他の火山も含めて計画的かつ必要に応じて機動的に観測を行うなどして、噴火警報・予報(噴火警戒レベル)等を的確に発表している。これから訪れようとする山が活火山であれば、事前にこれらの情報を確認することが大切である3。
噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と住民等が「とるべき防災対応」を5段階に区分して発表する指標であり、常時観測火山のうち、周辺に住民や登山者等が存在しない硫黄島を除く49火山全てにおいて運用が開始されている。また、火山災害要因(大きな噴石、火砕流など)の影響が及ぶおそれのある範囲を地図上に特定し、視覚的に分かりやすく描画した火山ハザードマップに、防災上必要な情報として、避難先、避難経路、避難手段等に関する情報のほか、住民や一時滞在者等への情報伝達手段等を付加して作成された火山防災マップを確認し、噴火時の避難場所などを確認しておくことも重要である。
<2> 登山届を提出する
御嶽山噴火時には、登山届を提出していない登山者が多かったこともあり、行方不明者の特定に時間を要した4。入山時に登山届の提出を徹底することは、自らの命を守るだけでなく、災害時の救助・救出活動全体の迅速化にもつながる。このことから、活火山法に登山届の努力義務規定が追加され、さらに、オンラインによる登山届の導入等、登山届提出が容易となるように地方公共団体が配慮することが盛り込まれた。既にオンライン申請や他の提出方法を導入している地方公共団体もあるため、活火山への登山を予定している場合には、事前に登山を行う地域の地方公共団体ホームページ等を確認することが望ましい。
<3> 火山防災対策グッズを持参する
御嶽山噴火により命を落とした方の多くが、噴石が頭や体に当たったことに伴う外傷性ショックによる「損傷死」であった。このことからも、自分の身を守るためにヘルメットを携行することは大切である。また、噴火後は空気中に火山灰の細かい粒子が漂い、目を開けづらくなることも想定される。降灰対策としてゴーグルやマスク、さらには、火山灰により日の光が届かなくなり、周囲が暗くなってしまうおそれがあることから、ヘッドライトも持参すると良い。
雨具、タオル、非常食、飲料水、携帯電話等の通信機器・予備電源、登山地図、コンパスなどの携帯必需品は、火山災害のみならず、予期せぬ事態への備えとして持参することが望ましい。
<4> 登山中も常に注意する
まずは、噴気孔や火口周辺のくぼ地などの危険な場所には近づかないようにする。異常を発見した場合には、下山するとともに、市町村や警察などに速やかに連絡する。
また、御嶽山噴火の災害教訓を踏まえ、中央防災会議「防災対策実行会議」の下に「火山防災対策推進ワーキンググループ」が設置され、その中で退避壕(ごう)・退避舎等の避難施設の整備の在り方についても言及されており、御嶽山噴火で火口周辺に降り注いだ噴石に対し、身を守る上で山小屋等に退避する行動が有効であったとされている5。そのため、火山防災マップなどを活用し、噴火時に避難する場所を事前に確認しておくことが重要である。気象庁では、噴火発生時に登山者や住民が身を守る行動を取れるよう、噴火が発生したことを端的にいち早く伝える噴火速報を発表している。もし、登山中に噴火速報が発表されたときや噴火に巻き込まれた際は、近くの山小屋や退避壕(ごう)、岩陰など、頭や体を守れる場所に一時避難することが重要である。
1 内閣府ホームページ「火山への登山のそなえ」
(参照:https://www.bousai.go.jp/kazan/kazan_sonae/index.html)

2 気象庁ホームページ「活火山とは」
(参照:https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/katsukazan_toha/katsukazan_toha.html)

3 気象庁が発表する噴火警報・予報(噴火警戒レベル)をはじめとする各火山情報は、「火山登山者向けの情報提供ページ」で確認することができる。
(参照:https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/map_0.html)

4 内閣府ホームページ「御嶽山噴火を踏まえた今後の火山防災対策の推進について(報告)」(中央防災会議 防災対策実行会議 火山防災対策推進ワーキンググループ)(平成27年3月26日)
(参照:https://www.bousai.go.jp/kazan/suishinworking/pdf/20150326_hokoku.pdf)

5 内閣府(2015)「活火山における退避壕等の充実に向けた手引き」
(参照:https://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/pdf/201512_hinan_tebiki3.pdf)