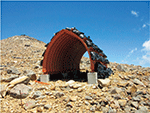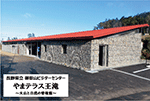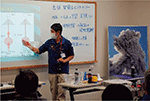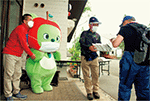第2節 御嶽山噴火の教訓を踏まえた火山防災対策について
平成26年(2014年)の御嶽山噴火では、予測困難な水蒸気噴火が突如発生し、火口周辺で多くの登山者が犠牲となった。御嶽山の麓の地方公共団体では、噴火警戒レベルが1に引き下げられた以降も必要な安全対策が整うまでの間、立入規制を実施してきた。その後、避難施設や防災行政無線の整備など、登山者に対する安全対策が講じられたことから、令和5年(2023年)7月29日、平成26年(2014年)の噴火から9年ぶりに御嶽山の王滝頂上と剣ヶ峰を結ぶ登山道の立入規制が解除され、長野、岐阜両県いずれの登山口からも登頂が可能となった。長野県、木曽町及び王滝村では、御嶽山噴火の教訓を踏まえ、火山防災力・防災意識の向上に向けて以下の取組を実施している。
(ハード及びソフト対策に係る取組)
長野県、木曽町及び王滝村は、御嶽山が活火山であることの十分な理解と認識のもと、ハード・ソフト両面の安全性を着実に向上させていくことを目的に、平成30年(2018年)に「御嶽山防災力強化計画」を策定した。本計画に基づき、以下の取組を行っている。
- 突発的な噴火に備えて、剣ヶ峰山頂及び八丁ダルミに消防防災施設整備費補助金等を活用し、避難施設(退避壕(ごう)等)を整備するとともに、山小屋の屋根等を衝撃耐久力のある高機能繊維織物で補強
- 避難促進施設を指定し、当該施設における避難確保計画の策定を支援
- 登山道は、避難路としての安全性を確保するため、整地やロープ設置を実施。また、規制状況や避難路の伝達、注意喚起のための標識等を設置
- 山頂部の登山者に対する情報伝達手段を確保するため、防災行政無線スピーカーを整備するとともに、登山シーズン中の一定期間、パトロール員の常駐などを実施
(火山防災意識の向上に向けた取組)
長野県では、御嶽山噴火災害を踏まえ、火山と共生するために必要な啓発の方向性やその具体策を検討するため、平成28年(2016年)6月に「長野県火山防災のあり方検討会」を設置し、「ビジターセンター等での情報発信」と「人材を活用した火山防災の普及啓発制度」の2点について検討が行われた。
「ビジターセンター等での情報発信」については、御嶽山噴火災害の記録と記憶の伝承とともに、登山者への火山情報発信の拠点として、令和4年(2022年)8月に、2つの「御嶽山ビジターセンター」(長野県が王滝村田の原に整備した「やまテラス王滝」、木曽町が町内三岳地区に整備した「さとテラス三岳」の2施設)が開館した。
「人材を活用した火山防災の普及啓発制度」については、御嶽山地域で登山者、観光客への情報発信の強化や噴火災害の記憶を語り継ぐことの重要性を踏まえ、火山防災のための人材活用の新たな取組として、長野県が平成29年度(2017年度)に「御嶽山火山マイスター制度」を創設した。令和6年(2024年)3月現在、28名の火山マイスターが認定されており、御嶽山ビジターセンターを拠点に防災教育等の普及啓発や地域振興につながる活動など、様々な取組を実施している。
(火山研究の推進)
平成28年(2016年)、長野県、木曽町及び王滝村は、御嶽山の火山防災対策の強化を図るため、研究施設の設置を名古屋大学に要請した。これを受け、名古屋大学は平成29年(2017年)7月に木曽町三岳支所内に御嶽山火山研究施設を開設した(現在は、木曽町御嶽山ビジターセンター内に移動)。本施設は、最新の火山研究を通じた御嶽山火山活動の評価力の向上、地域の防災力向上と火山防災人材の育成と知見の普及などの役割を担っている。