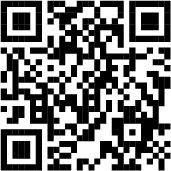「防災推進国民大会2023」の開催報告 次の100年への備え~過去に学び、次世代へつなぐ~
内閣府(防災担当) 普及啓発・連携担当

今年は、関東大震災発生から100年の節目の年であることから、防災推進国民大会(ぼうさいこくたい)は、関東大震災の震源地である神奈川県で、9月17日、18日に開催されました。大震災の記憶の継承、災害への「備え」と「助け合い」の大切さを次世代につなぐ機会にするため、「次の100年への備え~過去に学び、次世代へつなぐ~」を大会のテーマとしました。
「ぼうさいこくたい」とは
平成27年3月に開催された「第3回国連防災世界会議」で採択された国連の「仙台防災枠組2015−2030」では、自助・共助の重要性が国際的な共通認識とされました。これを踏まえ、平成27年9月、中央防災会議会長である内閣総理大臣の呼びかけにより、各界各層の有識者からなる「防災推進国民会議」が発足しました。この防災推進国民会議と、主に業界団体からなる「防災推進協議会」、そして内閣府の三者が主催者となり平成28年から「ぼうさいこくたい」を実施しています。産官学、NPO、市民団体や国民の皆様が日頃から行っている防災活動を、全国的な規模で発表、交流する日本最大級の防災イベントとして、今年で8回目の開催となりました。
オープニングセッション・ハイレベルセッション
オープニングセッションでは、松村祥史防災担当大臣からの主催者挨拶で、関東大震災は、その発生日である9月1日が「防災の日」と定められているように、近代日本における災害対策の出発点となった未曾有の災害であること、災害の多い我が国で、その被害を最小限に抑えるためには、行政による「公助」に加え、国民一人ひとりが、自らの命は自らが守る「自助」と地域で助け合う「共助」を組み合わせることが重要であることを伝えるとともに、災害の経験と教訓を次世代に語り継いでいくことで、防災意識の向上や、防災の担い手の育成につなげて欲しいとのメッセージがありました。同じく主催者である清家篤防災推進国民会議議長(日本赤十字社社長)、開催地の黒岩祐治神奈川県知事及び山中竹春横浜市長からも挨拶がありました。
今年のぼうさいこくたいでは、関東大震災から100年の記念すべき大会であることを踏まえ、「震源地・神奈川の傷跡と教訓」をテーマとする映像が流されたほか、立命館大学歴史都市防災研究所の北原糸子客員研究員による「関東大震災-救護・救済を中心に」をテーマとする基調講演が行われ、関東大震災がどんな災害であったかを振り返りました。
それを受け、続くハイレベルセッションでは、「次の100年に向けて、来るべき巨大地震に備えるため、それぞれの立場からどう取り組むか」をテーマに、黒岩祐治神奈川県知事、大久保智子横浜副市長、上村昇内閣府大臣官房審議官、入江さやか松本大学教授、大木聖子慶応大学准教授、阪本真由美兵庫県立大学教授が登壇してディスカッションを行い、モデレータの福和伸夫名古屋大学名誉教授が全体を取りまとめ、災害の備えの大切さを見つめ直しました。

松村防災担当大臣による開会挨拶

黒岩神奈川県知事による挨拶

オープニングセッション 北原客員研究員による基調講演

ハイレベルセッション
セッション・ワークショップ・展示等
今大会では、防災の活動を実践する多様な団体が出展し、様々な取組や知見を発信・共有しました。出展タイプとしては、講義やパネルディスカッションを通して参加者と一緒に考えるセッション、参加者を楽しく学ばせるための体験型ワークショップ、ブースでの説明やポスター展示により各団体の取組をアピールするためのプレゼンテーションやポスターセッション、ステージでの発表により各団体の取組をアピールするイグナイトステージ、こどもに特に人気のある車両等の屋外展示といった従来型のものに加え、出展者に自由に企画していただく「オリジナルセッション」が初めて加わりました。そして、出展団体数は約400、来場者は2日間で約16,000人、オンライン視聴数は約11,000回になりました。いずれも過去最多であり歴史的な大会となりました。
多くの出展団体に恵まれ、過去最高の来場者数となったのは、大会の準備から開催まで、地元神奈川県の防災活動に取り組む企業、団体や行政関係者が、「現地情報共有・連携会議」を開催し、出展者が互いに知り合う機会を提供したり、その様子を県庁ホームページ内の特設ページに紹介することで、出展者同士の結びつきを深めたことが影響しました。
クロージングセッション
クロージングセッションでは、大会全体をダイジェスト動画で振り返った後、ぼうさいこくたい2023のテーマ「次の100年への備え~過去に学び、次世代へつなぐ~」の“次世代へつなぐ”にフォーカスし、大学の研究室やサークルに所属する学生が、ぼうさいこくたいに出展しての感想、今後の防災への想い等未来に向けた力強いメッセージを発信しました。
それを受け、秋本敏文防災推進国民会議副議長(日本消防協会会長)、荏本孝久神奈川大学名誉教授(ぼうさいこくたい2023現地情報共有・連携会議)、佐々木修防災推進協議会運営委員会委員長(日本損害保険協会業務企画部長)、蒲島郁夫熊本県知事、堀井学内閣府副大臣が挨拶を行い、関東大震災から100年の記念すべき大会の幕を閉じました。
次回大会について
次の「ぼうさいこくたい」は、令和6年10月19日及び20日に熊本県で開催する予定です。ぼうさいこくたいが、九州地区で開催されるのは、初めてになります。熊本県は、平成28年の熊本地震、令和2年7月の九州豪雨と過去10年で大きな災害を2度も経験しましたが、「新しいくまもと」の実現に向け、力強い復旧・復興を遂げています。熊本県から、災害を教訓とした防災の取組、創造的復興への取組を発信することで、九州そして国民全体の防災意識の向上を図る機会にしたいと考えています。
おわりに
近年、災害が頻発化、激甚化していますが、災害が発生したときに、その災害を自分事として捉え、「自分の命は自分で守ると」いう意識を一人ひとりに持っていただくことが大変重要です。そのためには、国民の皆様が防災に主体的に参加できるようなきっかけづくりが非常に大切で、内閣府防災担当では、そうしたきっかけづくりを主体的に担うとともに、きっかけづくりへの支援も引き続き行って参りたいと考えています。
ぼうさいこくたい2023が、多くの方にとって、関東大震災をはじめとする過去の大災害の教訓を改めて学ぶきっかけとなり、防災意識、防災力向上に寄与できたならば幸いです。

プレゼンテーション

ポスターセッション

ワークショップ

オリジナルセッション

堀井副大臣による閉会挨拶

クロージングセッション

クロージングセッション後のくまモンとの集合写真(©2010熊本県くまモン)
ぼうさいこくたい2023ホームページ