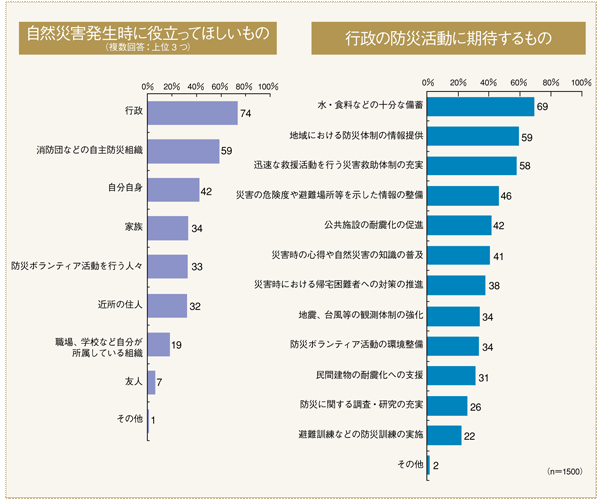2 災害リスクの変化と国民意識
近年の自然現象や社会環境の変化により新たな防災上の課題が生じてきている中で、これらの災害リスクについて国民がどのように認識し、どのように対応しているのか等を把握するため、内閣府では、インターネットを利用した国民意識調査を実施しました。
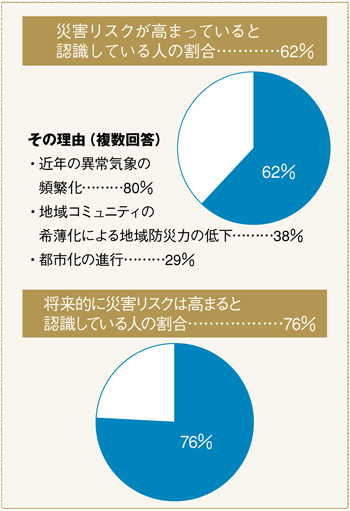
[1]災害リスクの変化についての認識
意識調査では、最近の災害リスクの変化について、約6割の人がリスクは高まっていると認識しています。また、将来については、75%以上の人が災害リスクは高まると認識しているという結果となりました。その理由として、8割の人が「近年の異常気象の頻繁化」を理由に挙げており、昨今の異常気象に対応した災害対策が求められているといえます。
[2]災害発生時に役に立つ主体、役に立ってほしい主体
自然災害発生時に実際に役立つと思う主体としては「家族」74%、「自分自身」64%と身近な存在を挙げる人が多く、自らの身は自分で守ると考えている人が多い結果となりました。逆に、役に立ってほしい主体については「行政」をあげる人が74%と最も多くなっています。
しかしながら、実際に講じている対策をみると、「家族間での連絡方法を決めている」は19%、「近くの学校や公園など避難する場所、経路を決めている」も24%と、災害発生時には自分自身や家族を頼りにしているものの、必ずしも具体の手段が伴われていない実態が明らかになりました。
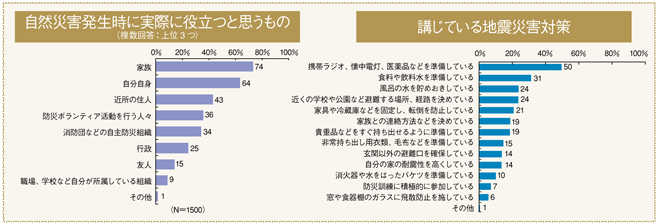
[3]地域の防災活動への関心、参加
地域の防災活動への参加については、「既に参加している」という人は6%にとどまりますが、「今後参加したい」「条件が整えば参加したい」といった潜在的な参加意向を加えると70%を超えました。参加の条件としては、「活動の曜日や時間が参加しやすいものであれば参加したい」が59%、次いで「活動内容や役割を選べれば参加したい」が36%となりました。
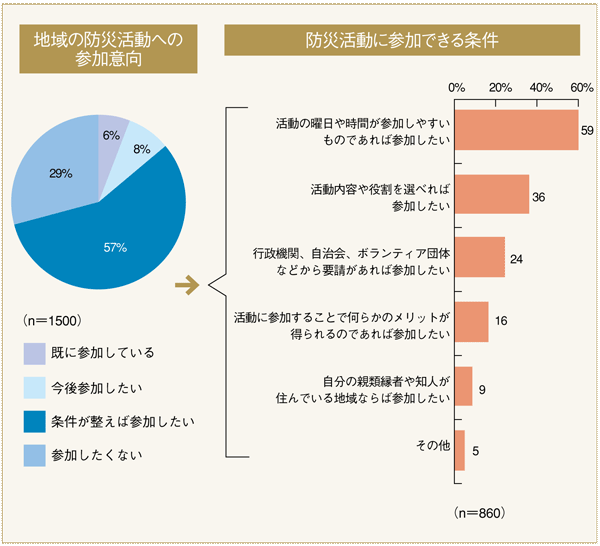
[4]行政に期待する防災活動
災害発生時に役に立ってほしい主体として、74%の人が「行政」を考えています。行政に期待する活動としては、水・食料の備蓄、防災体制の情報提供、災害危険度や避難場所等を示した情報の整備など多岐に渡ります。