「稲むらの火」普及プロジェクト
子どもたちの教材として海外で役立てられています。
日本の民話が世界へ! 津波からアジアの命を守る
アジア防災センター(ADRC)は2005年から2006年にかけて、NGOアジア防災・災害救援ネットワーク(ADRRN)と協力し、アジアの8カ国に向けて、9言語による津波啓発の教材を作成した。バングラデシュ向けのベンガル語版、インド向けのヒンディ語とタミル語版、インドネシア向けのインドネシア語版、マレーシア向けのマレー語版、ネパール向けのネパール語版、フィリピン向けの英語版(大人用)とタガログ語版(子ども用)、シンガポール向けの英語版、スリランカ向けのシンハラ語版の大人用と子ども用の合計18種類がある。
この教材では、日本で津波防災教育のために民話を基に作成された「稲むらの火」のお話を、各国の風俗や習慣を取り入れて少しずつ変更しながら紹介している。例えば、主人公や登場人物の名前や顔、衣服は、配布国の子どもたちが違和感を抱かずに物語の中に入っていけるよう、アレンジされている。
この教材の優れたところは、物語を読み進めば、津波防災の知識を自然な形で吸収できる点。「稲むらの火」は、1854年12月24日に日本で起津きた巨大な津波被害を題材として作成された小学生向けの教材で、災害の教訓から学ぶこと、そしてそれを伝えていくことの重要性、災害時の迅速な判断と行動の必要性について教えている。
作成に協力したADRRNのメンバー団体は、ADRCと協力し、それぞれが実施しているコミュニティレベルでの津波復興や防災プログラムを通して、この教材を各国で配布している。アジア防災センターは、この教材が各国や地域のコミュニティにおいて、将来の津波発生時の被害を軽減する手助けとなることを願っている。

インド

インドネシア
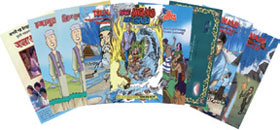
1854年、安政南海地震津波が紀州広村(現・和歌山県広川町)を襲った際、浜口梧陵は稲を積み上げた「稲むら」に火を放ち、暗闇で逃げ惑う村人を高台の神社に導いた。
この実話を基にラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は作品「A Living God」の挿話を書き、これを分かりやすく短編化したものが「稲むらの火」である。
