もし、1日前に戻れたら…
私たち(被災者)から皆さんに伝えたいこと
家の中でも靴がなければ動けない(東松島市 50代 女性)
4階建てのアパートの1階に住んでいますが、とにかく、その瞬間というのは、動くことができませんでした。もうア然として、例えば火のもとを消しにいったりすることなどできない状況でした。
アパートの方たちは、みんなすぐには外に出ませんでしたね。ちょっと揺れがおさまってから外に出たような感じでした。すぐ外に出ると、飛んでくるものがあるんじゃないかって思っていたみたいです。
揺れがだいぶ落ちついてから、あと片づけのために家の中に戻りましたが、悲惨な状況でした。割れた食器などが散乱していて、危険な感じでした。
地震のときは、家の中でも靴をはいて動かないと危ないっていうことを、初めて体感しましたね。

水が使えず、お皿にラップ(石巻市 70代 男性)
私のうちは地震後92時間、3日半ぐらい水が出なかったのね。トイレはすぐ近くの病院ですませました。病院は自家発電で大丈夫だったから。
水がなくて一番困るのは、何でも洗うことができないということなんですよね。で、アウトドアでやったのを思い出して、ご飯を食べるときもコーヒーを飲むときもラップを敷いて使いました。
友達が多いものだから、食べる物がないだろうからって、豚の角煮だのいろいろと持ってきてくれるのです。ああいうのって油っぽいから、洗うのは大変ですよね。だけど、ラップを敷くやり方だと、汚れたらラップさえ取り替えればいいわけです。水が出るまでの間、ずっとそうやっていました。

中学生の「防災学」(宮城郡 30代 男性 役場職員)
地震の被害があった後、耐震診断の授業を受けた子どもたちが先生となって地域で講習会をやったんです。参加するおじいちゃん、おばあちゃん世代の人も、孫世代から言われると身にしみるのか、耐震の大切さを実感されたようです。
地場産品を販売する産業祭の中でも、中学生の子供たちが一つのテントを持って、模型やパネルを置いて、お客さんたちに耐震の大切さというのを一生懸命アピールしていました。
これをきっかけに、地元の中学校で「松島防災学」が始まりました。図上訓練をやってみたところ、いろんな意見が出て時間が足りませんでした。来年は図上訓練だけを、半日ぐらいかけてやろうかなと思っています。
これから大人になる中学生たちに防災の正しい知識を身につけてもらうことは、とても大切なことだと思います。
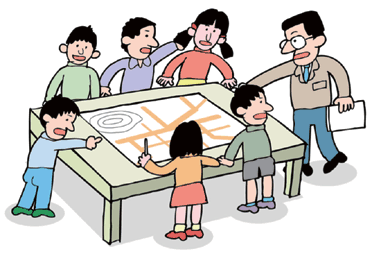
被災者の実体験を聞くことができる『一日前プロジェクト』は左記HPでも見ることができます。家庭はもちろん、地域や職場など、さまざまな話が掲載されていますので、企業の「社内報」や地域での「広報」に幅広く活用してください。
