太古から続く地球の営みから分かる 地震が起こるメカニズム
そこで、地震が起こるしくみと研究成果を、(独)防災科学技術研究所の堀貞喜氏にうかがいました。
今も動き続けている地球の表面
地球の表面は、海や陸など十数枚に分かれた、厚さ数10〜200kmのプレート(岩盤)で覆われています。海の下では新しいプレートが生まれ、年間数cmの速さで広がって陸のプレートに押し寄せます。海のプレートは陸のプレートより重いため、その下に入り込みます。この圧力によってプレートにひずみがたまり、それが限界に達すると、亀裂が入ったり大きく動いたりします。 これが地震なのです。地震が起こるとひずみはいったん解放されますが、プレートの動きは一定なので、定期的にひずみがたまって地震は繰り返されます。
日本列島は、海と陸の4枚のプレート境界に位置しています。東北日本には、年間約10cmの速さで移動する太平洋プレートの力がかかり、西南日本は太平洋プレートと年間約4cmの速さで移動するフィリピン海プレートの力が同時にかかっています。常に日本はほぼ東西から北西—南東方向に圧縮されているため、世界でも有数の地震が多い国なのです。
海と陸のプレート境界は「海溝」と呼ばれる水深6000m以上の深い溝になっており、ここで起こる地震が「海溝型地震 」(タイプ1)。
陸のプレート内の弱い場所がずれて起こる地震が「活断層による地震 」(タイプ2)となります。
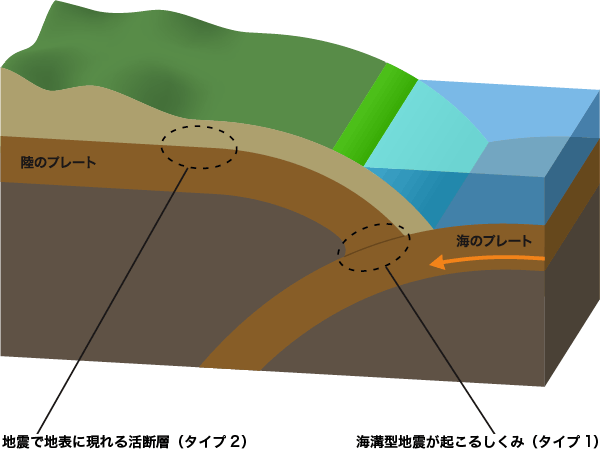
海溝型地震が起こるしくみ(タイプ1)
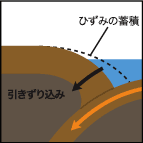
陸のプレートの先端が引きずり込まれ、ひずみが蓄積する


ひずみが元に戻ろうとして地震が発生。津波を伴う場合もある
地震で地表に現れる活断層(タイプ2)
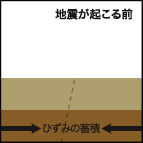
プレートの動きによる圧力がかかり、岩盤の弱い所にひずみが蓄積

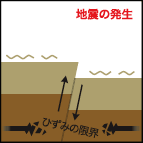
ひずみが限界に達すると弱い所がずれて、地震が発生

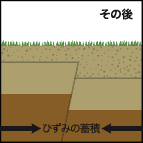
長い年月をかけて別の地層が堆積し、断層のずれが分からなくなる

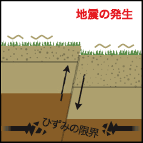
再びひずみが限界に達して断層がずれ、地震が発生する
海溝型地震の長期的予測
以前の地震予測は、前兆現象をとらえれば発生時期も分かる、というものでした。それが平成11年から、地震発生のメカニズムが分からないと予測はできないという方向に変わったのです。その結果、余震の分布や地殻変動などの観測データから、地震でずれ動いた領域(アスペリティと言う)の広がりなどが明らかになりました。現在、海溝型地震については、発生場所と規模の予測に一定の見通しが立っています。 一方、発生時期は長期的な予測で、過去に起こった地震の記録より、数十年から数百年という間隔で、地震が必ず繰り返すことが分かっています。
主な活断層を調査する
なぜ、そこに活断層ができたのかはよく分かっていません。現段階では、地表に見える活断層を実際に掘り、過去にいつ、どれくらい、何回動いたかを調査して、数千年単位の間隔で地震が起きていることははっきりしています。すでに110の活断層が調査されていますが、地震が起きて分かる活断層もあります。
堀 貞喜
昭和59年3月、名古屋大学大学院理学研究科博士課程中退(地球科学専攻)後、4月に科学技術庁国立防災科学技術センター(現・独立行政法人防災科学技術研究所)に入所し、現在に至る。専門および主な研究テーマは、スラブ内部の微細構造、地震発生のメカニズムなど。理学博士。政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会委員なども務める。
