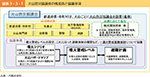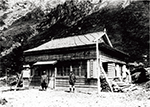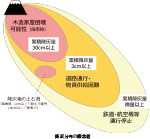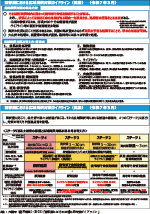3-3 火山災害対策
我が国は、111の活火山を抱える世界有数の火山国である。火山は、私たちの生活に恵みを与えてくれる一方で、噴火に伴って発生する火砕流や大きな噴石等の現象は、避難までの時間的猶予がほとんどなく、生命に対する危険の高い災害をもたらすおそれがある。
平成26年の御嶽山噴火では、火口周辺で多数の死者・負傷者が出るなど甚大な被害が発生したことから、火山活動の変化をいち早く捉え、伝達することが重要であること、住民のみならず、登山者も対象とした警戒避難体制の整備が必要であり、そのためには、専門的知見を取り入れた火山ごとの検討が必要不可欠であることなど、火山防災対策に関する様々な課題が改めて認識された。この災害の教訓等を踏まえ、平成27年に活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)が改正され、火山地域の住民だけでなく登山者の安全確保についても明記されるとともに、警戒避難体制の整備などのソフト対策の充実も図られ、これまで講じられてきたハード対策と合わせて、より総合的に活動火山対策を進める法律となった。本改正によって、火山災害警戒地域に指定された地方公共団体(令和6年度現在、23都道県179市町村)が、火山地域の関係機関等で構成される「火山防災協議会」において検討された「火山単位の統一的な避難計画」に基づき、警戒避難体制の整備に関する具体的かつ詳細な事項を地域防災計画に定めること、集客施設など不特定多数の利用者がいる施設や要配慮者が利用する施設等のうち、市町村が指定する施設(避難促進施設)の所有者等に対して、施設利用者の円滑な避難を確保するため、「避難確保計画」の作成や計画に基づく訓練の実施等を義務付けることなどが規定された(図表3-3-1)。
令和5年には、近年の国内火山をめぐる状況に鑑み、噴火災害が発生する前の予防的な観点から、活動火山対策の更なる強化を図るため、同法が再度改正された。これにより、市町村が火山防災協議会の助言も得ながら、避難確保計画の作成等に必要な情報の提供や助言、その他の援助ができるようになったほか、地方公共団体が登山届を始めとする登山者等の情報提供を容易にするために配慮することや、国や地方公共団体が火山に関する専門人材の育成や継続的な確保に努めることなどについて、規定が強化された。くわえて、火山に関する観測、測量、調査及び研究を一元的に推進するため、文部科学省に特別な機関として「火山調査研究推進本部」を設置すること、また、明治44年に日本で最初の火山観測所が浅間山に設置され、観測が始まった8月26日を「火山防災の日」とし、火山防災の日には、火山防災訓練等の行事を実施するように努めることも新たに規定された。この法改正を受けて、中央防災会議からの答申等を踏まえ、令和6年8月に法第2条に基づく「活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針」を改正するとともに、中之島(鹿児島県十島村)が監視・観測体制の充実等が必要な火山として追加されたことから、鹿児島県及び十島村を新たに火山災害警戒地域として指定した。
このように、活動火山対策を推進するための措置は着実に講じられてきているものの、実際に噴火を経験したことのある職員は限られており、また、火山ごとに想定される噴火の規模や地域の特性などには様々な違いがあることから、各種計画の検討等に課題を抱える地方公共団体等も少なくない。このため、内閣府では、計画検討の具体の手順や留意事項などについて取りまとめた手引きの作成や、地方公共団体等と協働検討することで得られた知見や成果を反映した手引きの改定や取組事例集の作成を行うとともに、地方公共団体等で火山防災の主導的な役割を担った経験のある実務者を「火山防災エキスパート」として火山地域に派遣するなど、全国の火山防災対策の推進に取り組んでいる。
また、「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ」が令和2年に取りまとめた大規模噴火時における降灰の影響や対策の基本的な考え方等を踏まえ、令和6年度には「首都圏における広域降灰対策検討会」を開催し、その検討を踏まえ、広域降灰対策に係る考え方や留意点等を「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」として令和7年3月に取りまとめた。
首都圏における広域降灰対策検討会について
富士山で大規模噴火が発生した場合、首都圏を含む地域が広く降灰に見舞われ、国民生活や社会経済活動に大きな影響を及ぼすことが懸念される。このため、内閣府では、富士山で大規模噴火が発生した場合の首都圏をモデルケースとして、「首都圏における広域降灰対策検討会」を開催し、その検討を踏まえ、広域降灰対策に係る考え方や留意点等を「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」として令和7年3月に取りまとめた。
本ガイドラインでは、緊急的・直接的な命の危険性は低いという降灰の特徴、首都圏の人口の多さ、予測の不確実性を踏まえ、広域降灰に対する住民の基本的な行動は、「できる限り降灰域内に留まって自宅等で生活を継続する」ことを基本とすることとした1。
降灰域内に留まって生活を継続するために、日頃からの十分な備蓄等、自助による対応のほか輸送手段やライフライン等の維持等公的な支援が優先事項となる。また、降灰の状況に応じて対応をとるため、実測の降灰量のみならず降灰の予測も活用することで、早めの対応が可能となる。さらに、火山灰の処理には、仮置場の確保が重要であり、最終的には様々な手段を用いて処理する必要がある。
本ガイドラインを踏まえ、引き続き具体的な地域における対策の検討等を進めるとともに、このような大規模噴火はいつ発生するか分からないことから、住民や関係機関においては、いざという時に備え、実施できる内容から対策を着実に推進していくことが必要である。
1 生活の継続が困難な場合は、避難の必要性も考慮する必要がある。