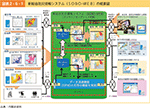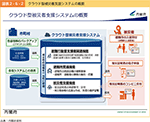2-6 防災におけるデジタル技術の活用等
(1)災害時の情報の集約化
災害発生時には、国・地方公共団体、民間企業の各機関がそれぞれ収集している、被害状況や避難者の動向、物資の状況などの情報を共有することが重要である。このため、平成29年度から「国と地方・民間の『災害情報ハブ』推進チーム」を立ち上げ、情報のやりとり等について検討を進めてきた。
(参照:https://www.bousai.go.jp/kaigirep/saigaijyouhouhub/index.html)

この検討を踏まえ、令和元年度から、災害時情報集約支援チーム(ISUT(アイサット)(Information Support Team))という大規模災害時に被災情報や避難所などの情報を集約・地図化・提供して、地方公共団体等の災害対応を支援する現地派遣チームの運用を開始した。災害現場では、被害状況や災害廃棄物の情報等、時々刻々と変化し、事前にデータで共有する体制が整えられないもの(動的な情報)も存在する。ISUTがそのような情報を収集・整理・地図化し、電子地図を表示するためのサイトである、新総合防災情報システム(SOBO-WEB)(令和6年4月運用開始)において体系的に整理するとともに、関係機関(行政機関、指定公共機関等)へ共有することで、災害対応機関の迅速かつ的確な意思決定を支援することができる(図表2-6-1)。
これまでISUTは、令和元年東日本台風や、令和6年能登半島地震において、道路規制・通行止め状況、避難所状況、福祉施設状況等の情報を共有するなど、ISUTサイトによる災害対応機関への情報支援を実施した。なおISUTサイトはSOBO-WEBの前身のシステムであり、ISUTが令和5年度まで運用をしていた。
また、ISUTがより迅速かつ効果的な活動を行うため、令和3年度から地図化などの業務の一部について民間事業者へ委託し、体制強化を図るとともにSOBO-WEB等の地理空間情報システムの活用に関する研修プログラムなども実施した。
(2)デジタル・防災技術ワーキンググループでの提言を踏まえた対応
内閣府では、令和3年5月に取りまとめられた「デジタル・防災技術ワーキンググループ」の提言を踏まえ、防災DXを進めるため、以下を中心とした各種取組を推進している。
<1> 新総合防災情報システム(SOBO-WEB)の整備
令和6年4月から運用を開始した新システム(新総合防災情報システム(SOBO-WEB))は、災害情報を地理空間情報として共有し、災害時における災害対応機関の迅速・的確な意思決定の支援を目的としたシステムであるが、更なる情報収集機能等の強化が必要不可欠である本システムにおいては、国立研究開発法人防災科学技術研究所が研究開発の一環として運用しているSIP4D(Shared Information Platform for Disaster Management)の仕組みを踏まえつつ、災害時におけるシステムの冗長性確保等、実用に耐え得るよう実装し、利用対象範囲も中央省庁に加え地方公共団体や指定公共機関まで拡大した。また、情報収集・分析・加工・共有等の機能の実現・強化や他の災害対応機関とシステム連携するため、令和5年度に策定した災害対応機関が共有すべき特に重要な災害情報(災害対応基本共有情報、通称EEI:Essential Elements of Information)の細目案を作成し、関係部局との調整を行った。
<2> 「防災IoT」データを活用した災害対応の高度化
災害現場においては、各種カメラや防災ヘリ等による状況確認に加え、ドローン等による空撮なども行われている。これらを含めた各種IoTによる膨大・多様なデータを、被災自治体を含めた各防災関係機関の間において適切に取得・共有するため、データ形式や使用する機器の規格等の技術的な標準手法の整理に資する調査事業を実施し、検証システムを立ち上げ、その有効性について検証を実施した。令和6年度には、調査事業で得られたニーズを踏まえ、新総合防災情報システム(SOBO-WEB)の画像共有機能としてシステム構築を実施し、動画・画像の共有が可能となったことで、災害対応機関間で、特に発災初期の被害状況の把握が迅速に行えるようになった。
<3> 防災分野における個人情報の取扱いの検討
従来、自治体ごとの個人情報保護条例において、個人情報の取扱いの定めは様々であった(いわゆる「2,000個問題」)が、デジタル改革関連法により共通ルールが定められ、個人情報の取扱いを一元的に監視監督する体制が構築された。これを契機とし、令和4年3月に「防災分野における個人情報の取扱いに関する検討会」を開催し、令和5年3月に地方公共団体等が災害対応や、平時の準備において個人情報等の取扱いに疑義が生じることが無いように個人情報の取扱いを明確化した「防災分野における個人情報の取扱いに関する指針」を策定した。
本指針は、以下の2点を基本的な方針としている。
a 発災当初の72時間が人命救助において極めて重要な時間帯であるため、積極的な個人情報の活用を検討すべきであること。
b 一方で、個人情報の活用においては、個人情報保護法や災害対策基本法にのっとり、個人の権利利益を保護する必要があること。例えば配偶者からの暴力(DV)やストーカー行為の被害者等、特に個人の権利利益を保護する必要がある者には十分な配慮が必要であること。
内閣府では、説明会の開催等を通じて当該指針の周知を図っているところであり、引き続き、地方公共団体の防災分野における個人情報の適切な取扱いに向けて取り組む。
(3)クラウド型被災者支援システムの構築
内閣府において、平時からの個別避難計画の作成支援を始め、発災時には住基データをベースとした被災者台帳の作成、マイナンバーカードを活用した罹災証明書等のオンライン申請・コンビニ交付等が可能となる「クラウド型被災者支援システム」を令和3年度から令和4年度にかけて開発し、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)において参加市町村を募り令和4年度から運用を開始した。