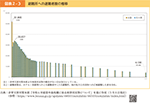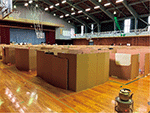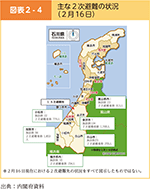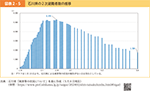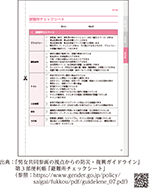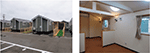第4節 被災者生活支援等
(1)避難生活(2次避難含む)
被災地では12万棟を超える住家被害が発生したため、発災直後より多くの被災者が長期にわたる避難生活を送ることとなった。発災直後(1月2日5時現在)は、1道1府9県の約1,300ヶ所の避難所が開設され、避難者数は5万人を超えた。翌3日6時現在では、新潟県、富山県、石川県の3県で約480ヶ所の避難所が開設され、約3万人が避難していた。避難所には食料・衣料等の生活必需品や、段ボールベッド、パーティション、仮設トイレ等の避難所環境整備に必要な資材がプッシュ型支援により届けられたほか、水道の断水のためトイレトレーラーの派遣や水循環型のシャワー設備等が設置された。また、一般的な避難所では生活に支障が想定される、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)などを受け入れる福祉避難所も開設された。
避難所運営は、被災した地方公共団体の職員が担うほか、全国から応援派遣された地方公共団体職員や被災地入りしたNPO等の専門ボランティア団体等によって支援された。避難所運営を含めた支援者の宿泊環境の改善のためトレーラーハウスやコンテナハウス等も数多く被災地に届けられて活用された。被害の大きかった石川県では発災直後は約3万人が避難していたが、その後は減少し、5月8日現在では石川県の275避難所で約4千人が避難生活(2次避難等含む)を続けている(図表2-3)。
能登地域の被災地では、道路の寸断により多くの孤立集落が発生したほか、孤立していない地域においても上下水道や電気等のライフラインの被害により日常生活を送ることが困難となり、特に高齢者等の災害関連死も懸念されたため、石川県において被災者を環境が整ったホテル・旅館等に避難(2次避難)させることとなった。受入先となるホテル・旅館等を確保するため、観光庁を中心として旅行業界との調整が図られ、1月9日には約5,000人分の宿泊施設が確保され、さらに2月末までの間に全国で約31,000人分が確保された。宿泊施設の迅速な確保に向けて1泊当たりの災害救助費の利用額の基準が特例的に7,000円から10,000円に引き上げられた。また、いしかわ総合スポーツセンター(金沢市内)等に一時的な避難所(1.5次避難所)が開設され、高齢者等の要配慮者を中心に最大で367人(1月21日)の避難者を受け入れた7。2次避難所への避難に関しては、石川県において、自衛隊ヘリによる空輸支援及び国土交通省が確保したバス・タクシーも活用して1月8日までに小松市等の2次避難所に196人が避難した8ことを皮切りに、県内外の2次避難所となるホテル・旅館等に最大5,275人(2月16日)が避難した(図表2-4)9。
1.5次避難所では、高齢者や障害者などの要配慮者が安心して暮らすことができるよう、診療体制の構築や介護職員等の派遣、生活相談窓口の開設(生活福祉資金の貸付)、1.5次避難所に避難している高齢者の県内外の福祉施設への入所調整などが行われている。
避難者数は被災地のライフライン復旧や仮設住宅建設が進むにつれて減少しており、5月8日現在で、1.5次避難所では64人(累計1,495人)、2次避難所では1,729人(累計10,999人)の被災者が避難生活を続けている(図表2-5)。
被災者の医療支援を行うため、医療支援チーム(DMATやJMAT等)が被災地の医療ニーズを把握し、病院支援や医療支援などを行ってきた。また、被災県以外の都道府県及び指定都市から派遣されたDHEATが保健所等の指揮調整機能を支援するとともに、保健師、管理栄養士等が各市町で作成した住民のリストに基づき巡回訪問等を実施し、避難所や自宅等で避難生活を送る被災者の健康管理を行ってきた。
JDA-DATは、特殊栄養食品(嚥下困難者用食品、アレルゲン除去食品、液体ミルク等)が必要な方に必要な食品を提供する拠点(特殊栄養食品ステーション)を設置するとともに、避難所(1.5次避難所含む)や在宅の要配慮者等への継続的な個別の栄養アセスメントと、その結果を踏まえた栄養・食生活支援を行った。
DWATは、避難所(1.5次避難所含む)における福祉的支援と併せて、避難所を拠点として周辺の在宅避難者に対しても生活の困り事等の相談支援等も実施している。在宅高齢者・障害者等に対しては、介護支援専門員や相談支援専門員等の福祉の専門チームが、保健師等と連携しながら個別訪問を行い、状況確認を実施している。
災害に便乗した犯罪から被災者を守り、安全・安心を確保するため、警察では、全国から特別派遣部隊を派遣し、パトカー等による被災地のパトロールや避難所における警戒を実施するとともに、避難所において相談対応や防犯指導等を行ったほか、避難所等へ防犯カメラを設置した。
能登半島地震における男女共同参画の視点による取組
これまでの災害では、防災の意思決定過程や災害対応の現場への女性の参画が十分確保されず、被災者支援において女性と男性で異なるニーズに適切に対応されないといった課題が生じた。
こうした観点から、今般の令和6年能登半島地震において、内閣府男女共同参画局は発災直後から被災地方公共団体に対し、「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン」に基づく取組を要請。さらに同局職員を非常災害現地対策本部に派遣して、男女共同参画の視点に立った避難所の開設・運営について支援を行った。1.5次避難所における具体的な取組としては、ガイドラインに掲載されている「避難所チェックシート」に基づき、石川県の協力を得て、女性用トイレへの生理用品の配置及び女性避難者用休養スペース・キッズスペース・授乳室の設置等に取り組んだほか、県の主導で避難所の運営管理への女性の参画を進め、物資配布担当への女性職員の配置等を行った。
また、避難所等における性被害・性暴力や配偶者等からの暴力の防止等のため、石川県が作成したポスターの掲示等による啓発、SNSや啓発カードを活用した被害にあった場合の相談先の周知、防犯ブザーの被災市町への配布(プッシュ型支援により4,200個)等を実施した。
(2)住まいの確保
被災地では12万棟を超える住家が被害を受け、被災者の住まいの確保が喫緊の課題となった。特に甚大な被害を受けた奥能登地域では、応急仮設住宅の建設に適した平地が限られることに加え、建設工事従事者のための宿泊拠点が少なく、また、水道等のライフライン復旧にも時間を要する中、住まいの確保に向けた取組が進められた。
住宅再建の前提となる被害認定調査や罹災証明書発行のため、 内閣府では、1月13日に罹災証明書の申請や被害認定調査の実施に関する留意事項(外観調査の簡素化、写真等を活用した判定、空中写真等を活用した一括全壊判定による迅速化など)を示し、調査や交付の迅速化に関する周知を図るとともに、その後も迅速かつ適切に被害認定調査及び罹災証明書の交付が行われるよう、新潟県、富山県及び石川県内の関係市町村に対し助言した10。このほか、1.5次避難所等においても罹災証明書の交付手続ができるよう窓口が設けられたほか、マイナンバーカードを利用してマイナポータルから罹災証明書の発行を申請できるなどオンライン申請の取組が各地方公共団体で進められている11。
避難者の方々に対する応急的な住まいに関する支援としては、「応急仮設住宅(建設型)」の他に、民間賃貸住宅を借上げて供与する「賃貸型応急住宅(みなし仮設)」、「公営住宅等の提供」等があり、石川県が県内外の地方公共団体や国と連絡調整を行い、地域の実情、提供までに要する時間等を総合的に勘案しながら、順次、応急仮設住宅等を提供してきた。
<1>応急仮設住宅(建設型)
応急仮設住宅(建設型)は、1月12日に輪島市と珠洲市で、15日からは能登町と穴水町で着工した。5月8日現在で応急仮設住宅(建設型)の着工戸数は5,771戸であり、うち3,557戸が完成している。建設にあたっては、ムービングハウス、トレーラーハウス、プレハブ、木造(長屋型)など多様な応急仮設住宅の建設を進めている。また、石川県は従来型の建設を進めるとともに、里山里海景観に配慮した木造長屋タイプのまちづくり型の建設を拡大し、さらには地元集落を離れ、賃貸型応急住宅(みなし仮設)等で生活する被災者がふるさとに回帰できるように木造戸建てタイプのふるさと回帰型の建設も進めている。
<2>賃貸型応急住宅(みなし仮設)
石川県は民間賃貸住宅を活用した賃貸型応急住宅(みなし仮設)の確保を進めており、石川県において約4,500戸を確保し、5月8日現在の入居決定戸数は3,549戸となっている。また、石川県から近隣県に転居する場合の提供可能戸数は新潟県1,000戸、富山県1,500戸、福井県1,200戸となっている。
<3>公営住宅等の提供
国土交通省は、4月1日現在で、即入居可能な公営住宅等を全都道府県において約9,300戸確保し、入居済み戸数は約800戸となっている。また、高齢者が安心して暮らせるよう各種相談等に対応する「生活支援アドバイザー」を配置したUR賃貸住宅を全国で300戸確保した。
また、財務省は、4月1日現在で、北陸4県の即入居可能な国家公務員宿舎等の情報として、新潟県107戸、富山県188戸、石川県139戸、福井県101戸を提供しており、石川県の要請を受け、石川県の国家公務員宿舎105戸の使用を許可した。
(3)災害廃棄物の処理等
今回の地震による被災家屋からの片付けごみ、全壊・半壊建物の解体に伴う災害廃棄物の発生量は、石川県内だけでも約244万トンと推計されている12。
被災地の復旧・復興のためには損壊家屋の早期解体を進める必要があり、申請に基づき市町が所有者に代わって解体・撤去する公費解体が進められている。特に被害の大きい石川県内の6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)等では公費解体の申請受付・契約事務の加速化のために、災害廃棄物処理の知見・経験を有する環境省職員や地方公共団体職員によるマネジメント支援とともに、応援地方公共団体職員派遣により、申請受付等の支援を行っている。被災市町村の災害廃棄物処理を支援する「災害等廃棄物処理事業費補助金」について、損壊家屋等の公費解体・撤去において全壊家屋に加えて半壊家屋を特例的に支援の対象とするとともに、国庫補助の地方負担に対して95%の交付税措置を講じるほか、被災市町村の財政力に鑑みて災害廃棄物処理の財政負担が特に過大となる場合に、県が設置する基金を活用して地方負担額を特例的に軽減することにより、円滑・迅速な災害廃棄物処理に向けた支援を行っている。被災市町においては、倒壊のおそれがあるなど解体の優先度の高い家屋から公費解体が進められており、5月5日現在で石川県内356棟の解体が実施された。4月は100班規模、5月以降は500から600班規模の解体事業者が順次現地入りし、石川県災害廃棄物処理実行計画の目標年次である令和7年10月の解体工事完了を目指し、解体工事の加速化を図っている。
7 石川県ホームページ「第27回災害対策本部員会議」(p21、28)
(参照:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/documents/0121shiryo.pdf)

8 石川県ホームページ「第16回災害対策本部員会議」(p25)
(参照:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/documents/0109kaigisiryou.pdf)

9 内閣府ホームページ「令和6年能登半島地震に係る検証チーム(第3回)」(資料2、p1)
(参照:https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf)

10 内閣府ホームページ「令和6年能登半島地震に係る罹災証明書の迅速な交付に向けた留意事項等について」(令和6年1月13日事務連絡)
(参照:https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/tsuuchi_r60113_seirei.pdf)

11 デジタル庁ホームページ「【令和6年能登半島地震】罹災証明書(り災証明書)のオンライン申請について」
(参照:https://www.digital.go.jp/2024-noto-peninsula-earthquake#ishikawa)

12 石川県ホームページ「令和6年能登半島地震に係る石川県災害廃棄物処理実行計画(令和6年2月29日)」(p5)
(参照:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/documents/jikkoukeikaku.pdf)