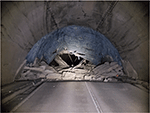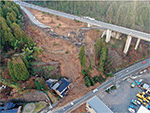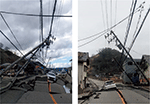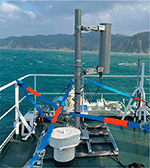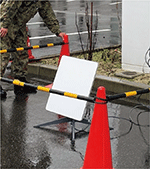第3節 インフラ・ライフライン等の被害への対応
(1)インフラ関係
<1>道路
能登半島の大動脈と言われる国道249号を始め、多くの道路に崩落、土砂崩れ、ひび割れ、段差が生じた。特に石川県においては、のと里山海道、国道249号、珠洲道路、七尾輪島線などの県管理道路で最大93か所が通行止めとなり(1月5日現在)、奥能登全体が孤立状態とも呼べるようなアクセスが困難な状態に陥った。多くの道路で通行止め等が発生した能登半島では、被災地に流入する車両が一部の道路に集中することにより、各地で渋滞が発生し、支援物資の運搬や復旧作業の支障となった。また、道路の通行止めにより33地区最大3,345人(1月5日現在)が支援を受けられない孤立状態に陥ったため、孤立集落の解消が喫緊の課題となった。
このため、国土交通省では1月2日から幹線道路の緊急復旧に着手し、24時間体制を構築して地元を中心とした各建設業協会や一般社団法人日本建設業連合会の応援を受け、緊急復旧作業を順次実施した。特に沿岸部では被災箇所が多数確認されたため、自衛隊と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復旧も進めて、13方向で通路を確保した。その結果、1月9日には緊急復旧により半島内の幹線道路の約8割が通行可となり、さらに1月15日には約9割まで進捗した。これらにより、孤立集落は1月19日に実質的に解消したところであり、引き続き、水道・電力などの要望、被災地方公共団体の要請を踏まえ、道路管理者にとらわれず、国・県・市町が役割分担しながら緊急復旧を実施している。また、1月23日には権限代行により国が石川県に代わり本格復旧を代行することを決定し、復旧を進めている。
<2>土砂災害・海岸
3月28日現在において、土砂災害が440件発生(石川県409件、新潟県18件、富山県13件)し、特に石川県では6河川(14か所)で河道閉塞等を確認した。国は石川県と連携し、TEC-FORCEによる調査や監視カメラの設置など、監視体制を構築し、地方公共団体にも監視映像を提供するなど警戒避難体制を支援している。また、土砂災害発生箇所のうち、不安定な状態で斜面や渓流に土砂・流木が堆積し、今後の降雨により二次災害が発生するおそれが高い石川県河原田川、町野川及び国道249号の沿岸部において、国による緊急的な土砂災害対策を実施している。
海岸については、石川県の12海岸において堤防護岸損壊等の施設の被災を確認した。宝立正院海岸では、復旧工事を権限代行により国土交通省が実施することとし、地域の復興まちづくり計画と整合を図りながら本復旧を進めることとしている。
<3>鉄道
発災直後、被災した各県で鉄道の運転が見合わせられたものの、北陸新幹線、JR北陸線は、1月2日から運転を再開した。レールのゆがみや支柱の傾斜等が生じたJR七尾線(津幡-和倉温泉)は、1月15日から高松-羽咋間で、1月22日から羽咋-七尾間で、2月15日から七尾-和倉温泉間で運転を再開した。大規模な土砂流入や広範にわたる路盤損傷等、被害の規模が大きかった第三セクターののと鉄道七尾線(和倉温泉-穴水)では、TEC-FORCEや独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の鉄道災害調査隊(RAIL-FORCE)を現地に派遣し、被災状況調査や事業者に対する技術的助言等の支援を行った。また、特に被害の大きな土砂流入2箇所については、並行する国道249号等の道路復旧工事との事業間連携により、土砂撤去作業の早期着手や土砂搬出作業の円滑化を実現した。これらの取組により、2月15日には和倉温泉駅-能登中島駅間で、4月6日には全線で運転を再開した。また、運転再開までの間、代替輸送の情報について国土交通省ホームページ等で発信すること等を通じ、利用者の利便性の確保を行った。
<4>港湾・港湾海岸
港湾に関しては、新潟県、富山県、石川県、福井県にある29港のうち、計22港湾(七尾港、輪島港、飯田港など)で岸壁や防波堤の損傷等の被害が確認された。特に被害が大きかった能登地域の港湾においては、石川県からの要請により七尾港、輪島港、飯田港、小木港、宇出津港、穴水港の計6港について、1月2日より「港湾法」(昭和25年法律第218号)第55条の3の3に基づき、港湾施設の一部管理を国土交通省が代行して実施することとなった。以後、各港湾で被災した施設の応急復旧等を進め、船舶による支援活動が展開されている。
また、2月1日には、石川県、富山県、七尾市からの要請により、上記6港に伏木富山港、和倉港、和倉港海岸、飯田港海岸を加えた計8港2海岸について、「大規模災害復興法」に基づき、被災した一部の港湾・海岸施設の本格的な復旧工事について、国土交通省が代行して行うこととなった。おおむね2年以内の復旧完了を目指し、取組を進めることとしている。
<5>航空
能登空港は、滑走路等に多数の亀裂及び灯火等に損傷が生じたため、発災当初より閉鎖されたが、発災翌日からは救援ヘリコプターの受入れを開始し、1月12日には、救援機の受入れ時間の拡大や滑走路の応急復旧により自衛隊固定翼機の受入れを開始した。1月27日からは能登-羽田間を1日1往復(発災前は1日2往復)、週3日での民間航空機の運航も再開され、4月15日からは毎日1日1往復で運航している(4月末現在)。今後は「大規模災害復興法」の適用による権限代行により、国土交通省が本格的な復旧工事を実施することとしている。
(2)ライフライン関係
<1>電力
北陸電力送配電株式会社管内において、電柱の倒壊や断線により、1月1日に最大約4万戸が停電した。北陸電力送配電株式会社では、発災当初より電力各社や協力企業から作業員や電源車等の応援を受け、連日千人規模で対応し、道路啓開の進捗と併せて、優先すべき場所に工事車両、人員を投入して、配電線復旧重点工事、電源車等での代替供給を開始する等により、停電の続く避難所等における早期の停電解消に努めた。こうした復旧に向けた取組の結果、4月1日現在では、安全確保等の観点から電気の利用ができない家屋等(北陸電力送配電株式会社が保安上の措置を実施)を除き復旧した。
<2>ガス
都市ガスについては、発災当初の段階で液状化の影響による導管被害等により一部で一時的に供給を停止したものの、1月5日には、ガス製造事業者や一般ガス導管事業の被害・供給支障については解消した。
ガス小売事業(旧簡易ガス)については、住宅崩壊等により復旧困難な場所を除き、供給再開している。
LPガスについては、供給基地や充填所等の設備支障があったものの、別の場所からの代替配送や被災地内の在庫のボンベの活用等により、供給面での支障が生じることはなかった。
<3>上水道・下水道
石川県を始めとして新潟県、富山県、福井県、長野県、岐阜県の6県29市7町1村にある最大約136,440戸で配水管破損、管路破損等の被害により断水が生じた。5月8日現在、石川県内の2市(輪島市、珠洲市)の約3,110戸で、なお断水が続いている。浄水場の被害に加えて、耐震化されていない水道管で損傷が生じただけでなく、耐震管でも継ぎ手部分が抜けるなどの破断が生じた。こうした断水の状況に対し、まず応急給水活動として全国から給水車等が被災地に派遣され、発災から約1か月後の1月31日現在では公益社団法人日本水道協会等から98台、自衛隊41台、国土交通省8台の計147台の給水車が被災地に派遣されていた6ほか、独立行政法人水資源機構の可搬式浄水装置が珠洲市に設置され、海上保安庁においても七尾港、輪島港岸壁に着岸した巡視船艇から自衛隊給水車等への給水を行った。水道施設の復旧に関しては、施設被害の甚大さとアクセスや宿泊拠点が制限される能登地域での支援の難しさから復旧作業は難航したものの、被害状況の調査や復旧計画の立案を行う水道事業体の技術職員が順次現地に派遣され、復旧作業が着実に進んでいる。
また、下水道に関しても、1月5日より全国の地方公共団体の下水道職員や民間事業者(公益社団法人日本下水道管路管理業協会等)が下水道管路の復旧支援を実施したほか、1月7日からは地方共同法人日本下水道事業団により、稼働停止の下水処理場、ポンプ場の緊急支援を実施した。特に被害の大きかった石川県能登地域の6市町においても、4月1日現在では既に下水処理場及びポンプ場の稼働停止は解消している。現在、水道の復旧状況に遅れることがないよう、早期復旧に向けて、令和6年4月の水道行政の厚生労働省から国土交通省への移管も踏まえ、上下水道一体となって早期復旧に向けた支援が実施されているほか、集落排水施設、浄化槽と連動した復旧作業が進められている。
<4>通信
設備の故障や停電により、携帯電話の基地局の稼働停止が発生し、1月3日には、携帯電話事業者4社の合計で839基地局が停波した。特に石川県においては、発災直後は8市町において支障エリアが発生し、被害の大きかった6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)の通信可能なエリアは、支障ピーク時において被災前の20~30%まで減少した。携帯電話事業者各社では、移動型基地局等(船上基地局、可搬型衛星アンテナ、有線給電ドローン、車載型基地局)を活用して応急復旧を進めた結果、立入困難地点を除き応急復旧がおおむね終了したことが携帯電話事業者4社より1月18日に公表された。本格復旧に関しては各社において商用電源の復旧、光ファイバーの張替、基地局の修理等が進められている。また、通信インフラが復旧していない地域においては、総務省による調整を通じて通信事業者から衛星通信機器が避難所などに提供され、インターネット通信に活用された。
固定電話については、他のライフラインと比較すれば発災後比較的速やかに復旧したものの、輪島市の一部では、4月1日現在でも固定電話や光回線を使ったインターネット接続サービスが利用できない状況が生じている。
<5>放送
放送インフラに関しては、地上波テレビ・ラジオが発災当初、商用電源の供給停止によって稼働していた予備電源の燃料枯渇等により一部エリアで停波となったため、被災者が信頼できる情報を入手できるよう、商用電源が復旧していない中継局への自衛隊等との連携等による燃料補給、NHK金沢局の番組の放送への衛星放送の活用、避難所等へのテレビ・アンテナの設置等の措置が取られ、その後の商用電源の復旧もあり、1月24日には全域で停波が解消している。また被災地域はケーブルテレビの依存度が高く(能登町96.4%、珠洲市70.1%等)、主センター施設までの復旧が迅速になされたほか、ケーブルの断線等による伝送路の復旧が進められている。
(3)公共施設等
<1>文教施設
新潟県、富山県、石川県を中心に国立学校32校、公立学校888校、私立学校102校、社会教育・体育・文化施設等761件の物的被害が確認された(4月1日現在)。特に被害の大きかった石川県内では冬休み明けの1月9日には公立学校86校が休校し(2月6日までに短縮授業やオンライン学習等を活用しつつ、全ての学校で一定の教育活動が再開)、輪島市や珠洲市、能登町の中学校では金沢市・白山市の施設へ集団避難が実施された。また、多くの学校が避難所として使用されることとなった。
<2>医療・社会福祉施設
医療施設については、4月1日現在で石川県内の19施設など最大計26施設で被災が確認され、2医療機関において倒壊の危険のある建物がある(建物内の患者は搬送済み)。3施設で停電が、23施設で断水が発生していたが、4月1日現在においては、石川県内全ての医療機関の断水は復旧した。被災地における医療体制確保の中心となる能登北部公立4病院においては、発災直後からDMAT等による診療・広域避難支援や看護師の応援派遣により、必要な医療機能が維持された。
社会福祉施設については、高齢者関係施設で、石川県内の191施設など最大計307施設で被災が確認され、30施設で停電が、161施設で断水が発生していた。4月1日現在において、うち71施設で断水が続いている。また、障害者関係施設においても、石川県内の41施設など最大計48施設で被災が確認され、6施設で停電が、30施設で断水が発生していた。4月1日現在において、うち1施設で停電が、28施設で断水が続いている。避難生活の長期化等を踏まえ、DMAT等が中心となり、被災地の高齢者関係施設から、被災地外の医療機関や高齢者関係施設、1.5次避難所(次節参照)に要介護高齢者等が搬送された。また、被災地における高齢者関係施設や障害者関係施設においては介護職員の応援派遣等により、介護・障害福祉サービスの提供体制確保に必要な支援を実施した。
<3>文化財
新潟県、富山県、石川県を中心に文化財等計401件(うち国宝(建造物)2件、重要文化財は建造物55件及び美術工芸品6件)が被害を受けたほか、世界遺産4件、日本遺産40件の被害も確認された(4月1日現在)。また、国の重要無形文化財である輪島塗の工房や店舗なども大きな被害を受けた。
6 厚生労働省ホームページ「石川県能登地方を震源とする地震について(第60報)」(別紙)
(参照:https://www.mhlw.go.jp/content/001200995.pdf)