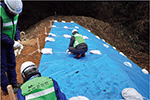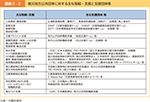第2節 発災以来の政策対応
(1)支援制度等の適用等
<1>災害救助法の適用
新潟県、富山県、石川県及び福井県の計35市11町1村に「災害救助法」(昭和22年法律第118号)が適用された(法適用日1月1日)。国庫負担により、各県が実施する応急的な救助(避難所の設置・運営、応急仮設住宅の供与等)が可能となった。
<2>激甚災害の指定
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)に基づき、1月11日に指定政令の閣議決定を行い、激甚災害(地域を限定しない本激)に指定した。これにより、公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置、中小企業信用保険法による災害関係保証の特例等、合計12の措置が適用された(2月9日の閣議決定による追加指定含む)。
<3>特定非常災害の指定
特定非常災害の指定については、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号)に基づき、1月11日に指定政令の閣議決定を行い、令和6年能登半島地震による災害を特定非常災害として指定するとともに、本特定非常災害に対し、行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置、期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置、債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置、相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置、民事調停法による調停の申立ての手数料の特例に関する措置を適用した。
<4>大規模災害復興法に基づく非常災害の指定
「大規模災害からの復興に関する法律」(平成25年法律第55号。以下「大規模災害復興法」という。)に基づき、1月19日に指定政令の閣議決定を行い、令和6年能登半島地震による災害を非常災害として指定した。これにより、被災した港湾、空港、海岸等について、地方公共団体に代わって国が権限代行により復旧工事を行うことが可能となった。
<5>生活の再建に向けた措置
1月6日に石川県は全域(19市町)に「被災者生活再建支援法」(平成10年法律第66号)の適用を決定、その後も富山県(全域(15市町村))、新潟県(全域(30市町村))が同法の適用を順次決定した。これにより、住宅が全壊等の被害を受けるなど一定の要件に該当した場合に、当該住宅に居住していた被災世帯に対し、住宅の被害状況に応じて、基礎支援金(最大100万円)及び住宅の再建方法に応じた加算支援金(最大200万円)が支給されることとなった。
加えて、能登地域の6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)では、他の地域と比べて特に被災状況が深刻であるとともに、 高齢化率が著しく高いことのみならず、家屋を建設できる土地が極めて少ないなど、半島という地理的な制約があって、住み慣れた地を離れて避難を余儀なくされている方も多い。そのため、地域コミュニティの再生に向けて乗り越えるべき、大きくかつ複合的な課題があるという実情・特徴を踏まえ、当該地域において、住宅半壊以上の被災をした高齢者・障害者のいる世帯、資金の借入や返済が容易でないと見込まれる世帯を対象として、石川県が最大300万円の給付を行う新たな交付金制度(地域福祉推進支援臨時特例交付金)が創設された。
また、「災害弔慰金の支給等に関する法律」(昭和48年法律第82号)に基づき、災害による死者の遺族に災害弔慰金、災害により重度障害を負った方に災害障害見舞金が支給されるとともに、要件に該当する世帯主に災害援護資金の貸付が実施された。
(2)被災地、被災地方公共団体等への広域応援
今般の災害においては、被災者支援、被災地方公共団体支援等のため、被災地外から数多くの機関が支援に駆けつけている。
前節で述べたとおり、救急・救助等のため警察(警察災害派遣隊)、消防(緊急消防援助隊)、自衛隊、海上保安庁の各部隊が被災地に派遣されており、保健・医療・福祉分野においてもDMAT、DPAT、JMAT、日本災害歯科支援チーム(JDAT)、日本災害リハビリテーション支援協会(JRAT)、DHEAT、日本環境感染学会災害時感染制御支援チーム(DICT)、日本栄養士会災害支援チーム(以下「JDA-DAT」という。)、災害派遣福祉チーム(以下「DWAT」という。)ほか、災害支援ナース等の看護師や保健師や介護職員など医療・福祉に携わる多くの職員が被災地に派遣されている。
また、道路啓開のほか、災害復旧事業、緊急避難輸送、緊急物資輸送などの輸送の支援や被災建築物の応急危険度判定のため、TEC-FORCE(国土交通省緊急災害対策派遣隊、以下「TEC-FORCE」という。)が派遣されたほか、MAFF-SAT(農林水産省・サポート・アドバイス・チーム)など各省庁においても各分野における災害復旧や被災者支援のための専門組織が派遣されている。
被災地方公共団体に対する全国の地方公共団体からの広域応援も大規模に実施されている。被災地方公共団体の災害マネジメント支援のため能登地域の被災6市町に総括支援チームが派遣されるとともに、4月1日までに、石川県内14市町、富山県内3市及び新潟県内1市に対して、62都道府県市から対口支援方式(カウンターパート方式)による支援チームの派遣(避難所の運営・罹災証明書の交付等の災害対応業務を担う職員の派遣)を決定し、活動を行っている。また、インフラ・ライフラインの応急対応や復旧に関しても、水道、電気、通信等において全国からの応援派遣が行われたほか、被災地の水道が長期にわたり断水状態となったため、全国の地方公共団体等から給水車やトイレトレーラーの派遣も行われた。
なお、発災当初から多くの応援地方公共団体職員、復旧事業者、ボランティア等の支援者が被災地に入り、多岐にわたる支援を実施したが、被災地ではホテル・旅館等も大きな被害を受け、宿泊施設が不足した。このため、石川県等において、特別交付税措置や独立行政法人中小企業基盤整備機構の仮設施設整備支援事業等も活用し、支援者のための宿泊施設の確保・充実に努めるなど、支援者支援を実施した。
(3)支援パッケージと財政措置、税制上の対応
政府は、1月2日、内閣総理大臣決定により、内閣官房副長官を長とし、各府省庁事務次官等を構成員とする「令和6年能登半島地震被災者生活・生業再建支援チーム」を設置し、被災者の生活や生業の再建を迅速かつ円滑に支援することとした。同支援チーム等における検討の成果をもとに、1月25日に「生活の再建」「生業の再建」「災害復旧等」の分野ごとに政府として緊急に対応すべき施策を「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」(令和6年能登半島地震非常災害対策本部決定。以下「支援パッケージ」という。)として取りまとめ、公表した2。
また、政府は、発災時点において残額が4,600億円を超えていた令和5年度予算の一般予備費等を活用し、変化する財政需要に対して機動的に対応した。具体的には、まず、1月9日に当面のプッシュ型の物資支援への財政的裏付けとして予備費の使用(約47.4億円)を決定した。そして、支援パッケージの施策の実施のため必要となる財政措置として、1月26日に1,553億円、3月1日に1,167億円の予備費の使用等を決定した。さらに、令和6年度においても復旧・復興の段階に応じた切れ目ない機動的な対応が可能となるよう、1月16日に、令和6年度予算について、一般予備費を5,000億円増額して計1兆円を計上する変更を決定し、4月23日には、支援パッケージの施策の実施のため必要となる財政措置として、1,389億円の予備費の使用を決定した。
被災地方公共団体に対する地方財政措置としては、まず1月9日に石川県及び県内17市町をはじめとする51団体、さらに2月9日に石川県及び県内7市町に対して、当面の資金繰りを円滑にするため、3月に交付すべき特別交付税の一部(261億400万円)を繰り上げて交付することを決定した。その上で、3月22日には令和5年度特別交付税の交付決定を行い、このうち令和6年能登半島地震の災害関連経費分は402億円となった。また、応援職員等の宿泊場所を石川県が一元的に確保する場合の費用に対する新たな特別交付税措置や、上下水道の災害復旧事業及び隣接住宅地も含めてエリア一体的な液状化対策を講じる「宅地液状化防止事業」に対する地方財政措置の拡充なども実施した。
税制に関しては、所得税等の申告・納付等の期限の延長を講じたほか、2月21日に成立(同日公布・施行)した「令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」(令和6年法律第1号)等に基づき、住宅・家財等の資産の損失の令和5年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税の計算における雑損控除の適用、災害減免法の特例による令和5年分の所得税の減免、事業用資産の損失の令和5年分の所得税の計算上の必要経費への算入を可能とする等の措置を実施した。
このほか、個人住民税が全額免除される水準となった被災者を含む世帯について、非課税世帯等への物価高対策支援(合計10万円/世帯。こども加算5万円/人)の対象とすることとした。
(4)被災地に寄せられた善意の支援への対応
発災以降、避難所運営や重機によるがれき撤去などの被災者支援を専門とする270を超えるNPO等の専門ボランティア団体が被災地に入り、活動を行っている。また、1月2日より全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)が石川県庁に入り、専門ボランティア団体、行政、社会福祉協議会等との情報共有会議を通じた情報共有・活動調整を行っている。
また、被災地の社会福祉協議会が主体となって、各市町に災害ボランティアセンターが設置されたことにより、ボランティア希望者の受付、刻々と変化する被災者のニーズとボランティアを結びつけるマッチング等が実施され、被災した住宅の片付けや災害ゴミの分別・運搬等の活動が行われている。特に今般の災害では、発災当初は被災地へのアクセス道路が限られることによる渋滞の発生や、被災地内での宿泊場所の不足等から、一般ボランティアが直接被災地入りすることを控えていただきたい旨の呼びかけが石川県等からなされた。このため、一般ボランティアは主に金沢市内等から発着するボランティアバスによって被災地入りすることとなり、多くの被災者が2次避難等により地域外に避難したためボランティアニーズの把握が困難だったことと相まって、過去の災害に比べてボランティアの活動人数は限定されることとなった。これに対し、石川県は国や関係機関と連携しつつ被災地内における宿泊拠点の確保を進め、ボランティア等支援者の活動環境の整備に取り組んだ。5月6日までのボランティアの活動人数は石川県、富山県、新潟県分あわせて延べ約9万人であった(石川県資料3及び全国社会福祉協議会調べ)。
石川県においては、被災された方々へのお見舞いとして寄せられた義援金(4月1日現在で約564億円)を公平に配分するため、石川県令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金配分委員会を設置し、2月1日の第1回委員会以降、順次配分計画を決定した。これにより、石川県においては、第2回委員会までに、死者・行方不明者100万円、重傷者10万円、住家全壊100万円(いずれも第一次配分、第二次配分の合計)等の義援金の配分が決定された4。また、富山県においても同様に義援金配分委員会の決定に基づく義援金の配分が決定されたほか、新潟県、福井県においても予定されている。
(5)令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部の設置
政府は、1月31日に、能登半島地震からの復旧・復興を関係省庁の緊密な連携のもと政府一体となって迅速かつ強力に進めるため、内閣総理大臣を本部長、全閣僚等を本部員とする「令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部」を設置した。具体的には、1月25日の支援パッケージの取りまとめを受け、同本部において、<1>各府省の復旧・復興に向けた進捗状況の確認、<2>各府省の施策の整合性の確認、<3>予備費の執行等に係る連絡調整等を行うこととされた。同本部会議は2月1日以降計5回開催5され(5月8日現在)、被災地のニーズを受け止めながら、機動的・弾力的に予備費等を活用し、インフラ・ライフラインの復旧、被災者・被災事業者支援等により復旧・復興を推進している。
2 内閣府ホームページ「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」
(参照:https://www.bousai.go.jp/pdf/240125_shien.pdf)

3 石川県ホームページ「知事記者会見(令和6年5月8日)」
(参照:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/chiji/kisya/r6_5_8/documents/0508_kisyakaikensiryou.pdf)

4 石川県ホームページ「令和6年(2024年)能登半島地震災害義援金配分委員会について」
(参照:https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/gienkinbussi/r6notohantoujishingienkin.html)

5 内閣府ホームページ「令和6年能登半島地震 復旧・復興支援本部」
(参照:https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/hukkyuhonbu.html)