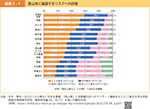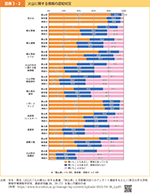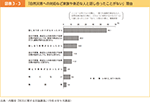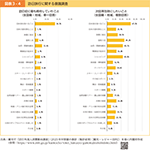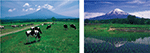第2節 「火山」との共生
火山は一旦噴火を始めると、甚大な被害をもたらし、人々の生活に大きな影響を及ぼすことがある。前節で述べたように、火山地域においては、火山災害に関する周知・啓発の取組を含めた対策が進められているものの、火山を訪れる登山者の火山防災に対する意識は必ずしも高いものではない。例えば、令和3年(2021年)に行われた登山者を対象としたWEB調査(複数回答方式)では、「火山噴火」について「とても気をつけている」と回答した人の割合は全体の17.6%と、天候の急変や熱中症など、登山時に遭遇し得る他のリスクと比べて、相対的に低い水準となっているという調査結果がある(図表3-1)。
また、火山に関する情報などの認知度について、「登山者」と「首都圏住民(東京都民、神奈川県民)」を対象としたWEB調査によれば、多くの項目で「登山者」が「首都圏住民」の認知度を上回り、噴火速報や噴火警戒レベルなどの情報に対する「首都圏住民」の認知度は、「登山者」の3分の2程度と低くなっている、という調査結果がある(図表3-2)。当文献においては、「首都圏住民」は火山の周辺に住んでいないため、このような火山情報に接する機会が少ないことが背景にある、と述べられている。
内閣府が令和4年(2022年)9月に実施した「防災に関する世論調査」において、地震、津波、火山噴火、台風や大雨などによる自然災害が起きたときに、どのように対処するかなどについて話し合ったことが「ない」と回答した者(全体の36.9%)に対して、その理由を聞いたところ(複数回答方式)、「話し合うきっかけがなかったから」の回答選択率が圧倒的に高かった(58.1%)(図表3-3)。このことから、火山情報に接する機会が少なくなれば、火山災害へ備えるきっかけも失われてしまうことが考えられる。このため、火山災害の特性や地域による違いも意識した上で、国民に働きかける取組を強化していくことが求められる。
一方で、火山は私たちに豊かな、他に代えがたい恵みをもたらす。火山活動によって造られた雄大な山体の姿、火口にできたカルデラ湖、高低差によって生まれた滝などの魅力ある風景は、訪れる人々に楽しみと憩いをもたらす。また、火山の熱によって生まれる温泉は、我が国の観光資源の一つと言える。
観光庁による訪日外国人消費動向調査によれば、訪日前に最も期待していたこと(単一回答方式)として、「自然・景勝地観光」の割合は12.4%と「日本食を食べること」に次いで高く、「温泉入浴」の割合も6.0%と一定の割合を占める。また、次回滞在時にしたいこと(複数回答方式)として「自然・景勝地観光」、「温泉入浴」の割合はいずれも50%程度と他項目に比べても高く、訪日外国人観光客にとっても火山の恵みは重要な観光資源の一つであると考えられる(図表3-4)。
また、溶岩流や山体崩壊によりできた広大な平野、降り積もった火山灰は水はけも良く、長い年月を経て農業に適した土壌となる。さらに、火山活動によって作られた地層は多くの隙間を有し、内部に多くの水を蓄える。山麓では火山がもたらす湧水や地下水は、生活用水としてだけではなく、農業や牧畜、工業などにも利用され、人々の暮らしを支えている。こうした特性から、古くから信仰の対象となっている火山もあり、歴史的・文化的な価値から火山が評価されることも多い。
このように、世界有数の火山国である我が国では、火山山麓に住む人々はもちろん、そこを訪れる観光客を始め、多くの人々が火山の恵みを享受している。周辺地域への災害の脅威と豊かな恵みの両面を併せ持つ火山と共生していくためには、私たちは火山の特性を正しく理解し、万一の噴火に備えておくことが求められており、前節で述べたように、各地域において各種火山防災に係る取組が行われている。このような各地域で開催される火山防災訓練や防災教室、ガイドツアー等の機会を活用するとともに、各種ホームページ等により情報収集を行うなど、火山について正しく知り、必要な備えを行うことが重要である。