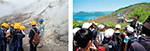第3章 「火山」と共に生きる
第1節 各地域における火山防災対策の取組
第2章第1節で述べたとおり、各火山地域では火山防災協議会を設置し、地元の地方公共団体が主体となって警戒避難体制の整備等を進めている。これは、噴火に伴って発生する現象や地形的な特性、居住地域との位置関係や観光客・登山客の往来などが火山ごとに異なり、防災体制を構築する上では、全国一律ではなく、火山ごとの特徴に応じ、検討することが重要であるためである。一方で、近年噴火を経験したことのある地域・地方公共団体は国内でも限られており、噴火の経験をしていない火山地域では、火山防災協議会における火山防災対策の取組に課題を感じているところも少なくない。
内閣府では、火山防災協議会の垣根を越えて、各火山防災協議会の構成員が一堂に会する「火山防災協議会等連絡・連携会議」を年に1回開催している。本会議では、各協議会や地方公共団体が抱える課題の共有や、先進的な取組事例の情報交換などを通じて、各火山防災協議会の中だけに留まらず、火山専門家や関係行政機関等とも火山防災対策を進める上での連携を強化することが期待される。
次に、火山噴火の経験を生かして、独自の火山防災対策の取組を進めている火山地域について、以下に紹介する。
(桜島:鹿児島県鹿児島市)
鹿児島市では、桜島で大正噴火(第2章第2節参照)級の大規模噴火が切迫しているという想定で、「桜島火山爆発総合防災訓練」を鹿児島県と共催で実施している。
この訓練は、昭和46年(1971年)から毎年実施されており、令和6年(2024年)現在までに54回開催されている。令和2年度(2020年度)以降、11月の住民避難訓練と1月の避難所体験・展示訓練に分けて実施されている。
11月の住民避難訓練では、噴火警戒レベルの引上げ前後の防災対応について、鹿児島市から桜島全域への防災行政無線による注意喚起や各町内における避難のための協議、避難指示等を受けた避難行動などが実施される。
その他、大正噴火の教訓を次世代へとつなげることを目的として、避難促進施設になっている桜島島内全ての小・中学校における訓練、消防や警察、自衛隊といった防災関係機関が連携する訓練なども併せて実施される。
1月の避難所体験・展示訓練は、桜島島内から市街地へ避難した後の生活を想定した訓練となっており、対象となる地区を変更しながら毎年実施されている。訓練会場となる避難所では、避難所体験のほか、関係機関が用意した展示の見学などもできる。
また、鹿児島市では、桜島の継続的な火山活動を受けて、市民と地域、事業者、研究機関・行政が一体となって、桜島に対する総合的な防災力の底上げを図るとともに、火山の魅力を交えながら世界に発信することにより、交流人口を含めた関係人口の拡大を図るため、「鹿児島市火山防災トップシティ構想」8を策定している。
本構想では、市民の誰もが桜島の成り立ちや火山の恵み、文化を学び、桜島への関心と愛着を育むとともに、火山災害時における対応を理解し、身につけるために、次世代に「つなぐ」火山防災教育を取組の柱の1つとして推進しており、例えば、「桜島訪問体験学習」として、市街地側の小学6年生が実際に桜島を訪れ、火山専門家等による現地説明を受けるなどの機会創出に取り組んでいる。
そのほか、「鹿児島モデル」による世界貢献として、上述の桜島火山爆発総合防災訓練などへの国内外からの視察受入れや、他の火山地域における火山災害発生時の支援体制の構築などを進めている。
(伊豆大島:伊豆大島ジオパーク、東京都大島町)
平成22年(2010年)に日本ジオパークに認定された伊豆大島ジオパークでは、地球活動の痕跡が読み取れる豊富な資源を活用することにより、ジオパークの視点から防災教育を推進している。日本ジオパークには、火山活動により形成された地形・地質が含まれる地域も多く、認定される際には、地殻変動や地震活動、火山活動等によって引き起こされた災害の経験・知見を基に、どのような防災・減災活動が行われているかについても審査されることから、ジオパーク活動の一環として、火山防災教育や火山に関する知識の普及について取り組むことは、親和性が高いと言える9。
伊豆大島ジオパークの見どころとなる「ジオサイト」は、その全てが過去の伊豆大島噴火によって生じたものであるため、各ジオサイトから、今後起こり得る噴火災害(噴火によって発生する様々な現象とその規模など)について語ることができる。地元の児童や生徒を対象とした防災教室や体験学習、観光客を対象としたガイドツアーといった取組の中で、火山がもたらす災害と豊かな恵みの両面について学び、理解する機会を提供している。このようなジオパーク活動を通じて、災害発生の危険性に対して自らの判断で行動できる力の養成や、災害文化の次世代への継承、他地域への発信を始めとする様々な効果が期待されている。
また、東京都大島町では、大島町地域防災計画の中で、伊豆大島ジオパークの活動を通じ、火山防災に関する知識・情報の普及啓発を図ることを定めている。災害に関する情報の発信は、風評被害を招くおそれがあることから、観光などのツーリズムと相反するように見られがちであるため、このような公的な計画として位置付けることは、火山防災に関する普及啓発を進める上で有効な手段であると言える。
(有珠山:洞爺湖有珠火山マイスター、北海道西胆振(いぶり)地域)
これまで数十年おきに噴火してきた有珠山のある北海道の西胆振(いぶり)地域では、火山との共生をテーマに、必ず訪れるであろう次の噴火に備えるために、火山の特性や自然について正しく学び、噴火の記憶や災害を軽減する知恵などを、世代を超えて語り継ぐ人づくりの仕組みとして、洞爺湖や有珠火山地域の自然や特性について正確な知識を有する人を地域限定の称号「洞爺湖有珠火山マイスター」に認定している。「洞爺湖有珠火山マイスター」は、地域防災のリーダーとして地域防災力の向上を図るとともに、地域の魅力発信にも活かすことを目的として、平成20年(2008年)に制度が開始し、令和5年(2023年)現在では70名の火山マイスターが認定され、防災教育や学習会などの講師やサポートなどに取り組んでいる。
有珠火山地域では、過去に発生した火山活動により、洞爺湖や昭和新山を始めとする現在の景観が形作られ、温泉を始めとする資源や産業も生み出された。火山がもたらす災害を正しく理解した上で、地元では恵みを享受し、共生の道を歩んでいる。また、たくさんの恵みがあるこの地域には、火山に普段なじみのない地域に住む観光客も数多く訪れる。このような観光客(特に修学旅行生などの学生)に対して、ガイドとともに過去の噴火災害の伝承や火山防災に対する知識の普及を行うことにより、国民が広く火山に対する関心や理解を深める一助となっている。
8 鹿児島市ホームページ「鹿児島市火山防災トップシティ構想」
(参照:https://www.city.kagoshima.lg.jp/kikikanri/kazan/topcitykousou.html)

9 日本ジオパーク委員会では、ユネスコのガイドラインに沿って日本ジオパークを認定している。日本ジオパークは、ユネスコ世界ジオパークとそれを目指す国内ジオパークからなり、令和5年(2023年)5月現在、46地域が認定されている。
(参照:日本ジオパークネットワーク https://geopark.jp/geopark/)