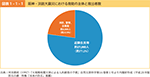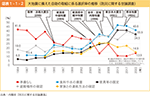第1部 我が国の災害対策の取組の状況等
我が国は、その自然的条件から各種の災害が発生しやすい特性を有しており、令和5年度においても、令和6年能登半島地震を始めとした多くの災害により被害が発生した。第1部では、最近の災害対策の施策、特に令和5年度に重点的に実施した施策の取組状況を中心に記載する。
第1章 災害対策に関する施策の取組状況
第1節 自助・共助による事前防災と多様な主体の連携による防災活動の推進
1-1 国民の防災意識の向上
我が国ではその地形や気象などの自然的条件により、従来から多くの自然災害を経験してきた。このため、平常時においては堤防の建設や耐震化など災害被害の発生を防止・軽減すること等を目的としたハード対策と、ハザードマップの作成や防災教育など災害発生時の適切な行動の実現等を目的としたソフト対策の両面から対策を講じて、万が一の災害発生に備えている。また、災害発生時には、災害発生直後の被災者の救助・救命、国・地方公共団体等職員の現地派遣による被災地への人的支援、被災地からの要請を待たずに避難所や避難者へ必要不可欠と見込まれる物資を緊急輸送するプッシュ型の物資支援、激甚災害指定や「被災者生活再建支援法」(平成10年法律第66号)等による資金的支援など、「公助」による取組を絶え間なく続けているところである。
しかし、今後発生が危惧される南海トラフ地震や日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震、さらに近年激甚化・頻発化する気象災害等によって広域的な大規模災害が発生した場合において、「公助」の限界が懸念されている。
阪神・淡路大震災では、生き埋めになった人の約8割が家族も含む「自助」や近隣住民等の「共助」により救出されており、「公助」である救助隊等による救出は約2割程度に過ぎなかったという調査結果がある(図表1-1-1)。
市町村合併による市町村エリアの広域化や地方公共団体の公務員数の減少など、地方行政を取り巻く環境が厳しさを増す中、高齢社会の下で配慮を要する者は増加傾向にある。このため、国民一人一人が災害を「他人事」ではなく「自分事」として捉え、防災・減災意識を高めて具体的な行動を起こすことにより、「自らの命は自らが守る」「地域住民で助け合う」という防災意識が醸成された地域社会を構築することが重要である。
防災・減災のための具体的な行動とは、まずは「自助」として、地域の災害リスクを理解し、家具の固定や食料の備蓄等による事前の「備え」を行うことや、避難訓練に参加して適切な避難行動を行えるように準備すること、台風の接近時などに、住民一人一人に合わせて、あらかじめ時系列で整理した自分自身の避難行動計画(マイ・タイムライン)を作成することなどが考えられる。また、発災時における近所の人との助け合い等の「共助」による災害被害軽減のための取組が必要である。
内閣府が令和4年9月に実施した「防災に関する世論調査」の結果によると、「自助」の重要性の認識や具体的な対策を講じる動きは、阪神・淡路大震災、東日本大震災といった大災害を経て、着実に国民の間に浸透している(図表1-1-2)。しかし、熊本地震が発生し、大きな被害をもたらしたにもかかわらず、その後に実施した平成29年の調査では、例えば「家具等の固定」が40.6%となるなど、「自助」の取組の実施率は頭打ち傾向にある。また、直近の令和4年の調査は、平成29年までの個別面接聴取法と異なり郵送法で実施しているため、従前の調査結果との単純比較はできないものの、総じて取組の実施率は高まっていないおそれがある。その背景として、多くの国民にとっては、災害の被害状況等を報道で見聞きするだけであり、自らが被災者となる実感が得られないことから、災害の発生を契機とした国民の防災意識の高まりが得られにくくなっているとも考えられる。
特集1第3章第2節「『火山』との共生」で述べたとおり、令和4年の調査では「自然災害への対処などを家族や身近な人と話し合ったことがない」と回答した者(全体の36.9%)に対して、その理由を新たに聞いたところ(複数回答方式)、「話し合うきっかけがなかったから」の回答選択率が圧倒的に高かった(58.1%)。このことから、着手の一歩を踏み出せていない国民に働きかける取組を強化していくことが求められる。
「共助」についても、令和元年東日本台風における長野県長野市長沼地区等のように、平時より地域の防災リーダーが主体となり、避難計画の作成や避難訓練等の「共助」の取組を行っていた地域においては効果的な避難事例がみられ、「共助」の重要性が改めて認識されたところである。
行政が「公助」の充実に不断の努力を続けていくことは今後も変わらないが、地球温暖化に伴う気象災害の激甚化・頻発化、高齢社会における支援を要する高齢者の増加等により、突発的に発生する激甚な災害に対して既存の防災施設等のハード対策や行政主導のソフト対策のみで災害を防ぎきることはますます困難になっている。行政を主とした取組だけではなく、国民全体の共通理解の下、住民の「自助」・「共助」を主体とする防災政策に転換していくことが必要である。現在、地域における防災力には差が見られるところであるが、防災意識の高い「地域コミュニティ」の取組を全国に展開し、効果的な災害対応ができる社会を構築していくことが求められている。