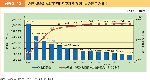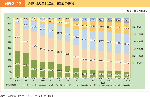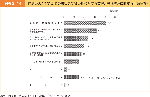4-2 「共助」の取組の進展
(地域における「共助」の取組の進展)
地域防災力の向上のためには、住民一人一人による「自助」の取組の促進に加えて、「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識を持って「共助」の防災活動を行うことが重要である。このため、コミュニティにおける自主的な防災活動を支える自主防災組織の育成が進められており、その組織数及び活動カバー率は年々上昇している。
一方で、地域防災力の中核を成す存在である消防団は、昭和40年(1965年)には約133万人だった団員数が、令和4年(2022年)には約78万人と、初めて80万人を下回った(図表2-12)。また、団員構成の高齢化も進んでおり、昭和40年には10~30代が90.4%を占めていたが、令和4年には39.3%まで減少しており(図表2-13)、女性や若者等幅広い住民の入団促進や、装備・教育訓練の充実強化に取り組んでいる。
(ボランティア活動の進展)
「ボランティア元年」といわれ、延べ約138万人のボランティアが活動した阪神・淡路大震災(平成7年(1995年))以降、災害ボランティアによる支援活動は被災地・被災者にとって欠かせない存在となっている。中越地震(平成16年(2004年))等を契機として、全国の社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを運営することが一般化し、個人ボランティアの活動環境が整備された。さらに、東日本大震災(平成23年(2011年))などを契機として、NPOや企業などの団体によるボランティア活動が活発化し、それらの活動を支援する全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)や県域レベルでの災害中間支援組織の設置が各地で進みつつある。
(幅広い形での「共助」の取組の促進が必要)
令和4年の世論調査では、ボランティアを含む被災者・被災地への支援活動の意識調査を行った(複数回答方式)。これによると、「義援金の寄付」(41.0%)、「学校、職場、NPOなどの団体が行う災害ボランティア活動に参加」(23.6%)、「災害ボランティア活動に個人として参加」(19.9%)等に並んで、「復興を支援するための被災地への旅行や地場産品の購入」(31.7%)や「ふるさと納税などによる被災した地方公共団体への寄付」(17.4%)、「NPOなどの団体への支援金の寄付」(14.2%)等の回答も多かった(図表2-14)。
このような支援活動は、広い意味での「共助」の取組であると捉えることができる。地域コミュニティによるつながりの低下が懸念されている中、このような取組を含めて、幅広い形での「共助」の取組を促していくような環境整備が求められている。