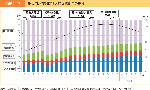第3節 人口の大都市部への集中と高齢化の進展
前章では関東大震災から今日に至る大規模災害とその対応の経緯を振り返ったが、我が国の経済社会の姿はこの100年で大きく変化している。我が国の国勢調査は、関東大震災の3年前に当たる大正9年(1920年)に開始されたことから、災害の生じた当時の経済社会状況と今日の違いを時系列的に俯瞰することが可能である。そこで、本節では、主に国勢調査のデータ8を使って、大震災発生当時の人口構造の特徴を明らかにするとともに、その後の人口構造の変化と将来動向を分析し、今後懸念が高まる人口構造上のリスクについて論じる。
3-1 人口の地域分布
(関東大震災当時の東京圏の人口は現在の4分の1以下)
令和2年(2020年)の我が国の総人口は約1億2,615万人であるが、関東大震災発生の3年前に当たる大正9年(1920年)は約5,596万人(令和2年の44.4%)であり、総人口は現在の半分に満たなかった。
また、圏域別9の人口分布をみると、令和2年の東京圏には約3,691万人が居住し、総人口の約29.3%を占めている一方、大正9年における東京圏の人口は約768万人(総人口の約13.7%)であり、現在の4分の1以下、総人口に占める割合も現在の半分程度であった(図表2-7)。
以上のことから、関東大震災の人口や経済社会活動に対する影響度合いは、現代において同様の震災が発生した場合と比べると相対的に小さかったということができる。
(大都市圏への人口急増期に起きた伊勢湾台風)
関東大震災以降、戦後の大規模災害発生時の人口構造を調べると、時代によって人口の地域分布がそれぞれ異なることが分かる。
昭和34年(1959年)の伊勢湾台風の発生は、三大都市圏への人口集中が本格化した時期に当たる。地方圏の人口は、昭和35年~40年の間に戦後初めて減少した一方で、伊勢湾台風の被害を受けた名古屋圏を含め、三大都市圏の人口がこの時期に急増した。
(東京一極集中の傾向が強まった時期に起きた阪神・淡路大震災)
平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災の発生は、バブル崩壊を経て、東京圏への一極集中の傾向が強まった時期に当たる。関西圏の人口増減率(5年間)は、平成2~7年に0.8%とほぼ横ばいになり、その後平成27年(2015年)以降はマイナスで推移している。
平成23年(2011年)の東日本大震災は、我が国の総人口が平成20年(2008年)に約1億2,808万人でピークを迎えた直後に発生した。東京一極集中の傾向は更に強まり、東京圏の人口割合は平成22年に27.8%を占めた一方、東北地方を含む地方圏の人口割合は48.9%と半分を下回った。
(今後一層進む東京一極集中傾向)
国立社会保障・人口問題研究所の地域別将来推計人口10によれば、東京圏の人口一極集中は今後更に進み、東京圏の人口割合は令和27年(2045年)には31.9%に達すると推計されている。南関東地域におけるM7クラスの地震の30年以内の発生確率が70%程度とされている中、首都直下地震等の巨大災害の発生に備えて、100年前の関東大震災当時よりも一層の対策が求められている。
8 総務省「国勢調査」
9 圏域区分は次のとおり。
東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
名古屋圏:岐阜県、愛知県、三重県
関西圏:京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
地方圏:上記以外の道県
10 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(平成30年推計)