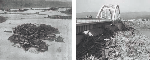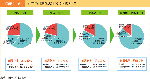第2節 防災・減災インフラの整備等による災害への対応力の向上
関東大震災が発生した大正時代と比べて、現在の防災・減災のためのインフラ(以下「防災・減災インフラ」という。)は高度に整備されてきたと言える。ここでは、河川や港湾の整備による被害軽減の実例を示すとともに、建物の耐震化を中心に、我が国の地震対策の取組とその進捗状況について確認する。また、防災・減災インフラの整備に加えて、防災意識の向上に向けた取組の必要性等についても論じる。
(治水対策や高潮対策による被害軽減)
自然災害から住民の生命・財産を守るため、我が国では全国各地において、河川整備やダム建設等の防災・減災インフラの整備が進められてきた。
まず、治水対策における防災・減災インフラの整備による被害軽減の実例について、静岡県伊豆半島を流れる狩野川を例にとって確認する。伊豆半島の天城山系の山々を水源に持ち、太平洋側では珍しく南から北に流れる狩野川は、千年以上も前から人々の暮らしの中心にあった。一方で、下流部に狭窄部を持つ地理的特徴と多雨地帯を流域に抱えていることから、古くから幾多の洪水を発生させており、特に昭和33年(1958年)9月の狩野川台風は、流域に未曾有の浸水被害をもたらした(写真7)。これを受けて、下流域の都市部を流れる狩野川本川の水位を低下させるため、中流で分流してそのまま海に注ぐ狩野川放水路が整備された。その後、この地域で大雨をもたらした令和元年東日本台風では、総降雨量が778mmを記録し、狩野川台風の総降雨量(739mm)を超える状況にあったが、狩野川放水路による洪水分派により狩野川本川の越水を防ぎ、人的・物的被害を大幅に軽減した(写真8)。
次に、高潮対策における防災・減災インフラの整備効果について、大阪市の事例を確認する。大阪市は、昭和36年(1961年)9月の第二室戸台風に伴う高潮によって大規模な浸水被害を経験しており、これを契機に、水門や高潮堤の整備、防潮堤鉄扉の設置などの高潮対策を実施してきた。第二室戸台風から半世紀以上が経った平成30年(2018年)9月の台風第21号において、大阪湾ではこれまでの最高潮位(第二室戸台風のTP+2.93m)を大幅に超過し、TP+3.29mを記録したが、大阪湾高潮対策で整備した水門、防潮堤鉄扉等の適切な操作により、大阪市街地における浸水被害は回避された(写真9)。
(建物の耐震化の進捗)
次に、建物の耐震化に着目して、我が国の地震対策の取組を確認する。第1章第1節で見たように、関東大震災では、建物の倒潰とそれにより発生した火災等によって約10万5,000人を超える犠牲者が出た。第1章第4節で見たように、耐震構造化を考慮されていないビルが多数倒潰したことを受け、法令による地震力規定が制定された。その後の阪神・淡路大震災では、耐震基準を満たさない建物に特に被害が集中していたことから、耐震基準を満たさない建物の耐震化が促進された。
このような取組を踏まえ、我が国の建物の耐震化は着実に進捗している。例えば、住宅の耐震化率7は、平成15年(2003年)が約75%、平成20年(2008年)が約79%、平成25年(2013年)が約82%、平成30年(2018年)が約87%と着実に上昇しており、東日本大震災では、耐震化された建物の多くは被害を免れているなど、耐震化の有効性が確認されている(図表2-6)。将来想定される首都直下地震等の大規模地震に備え、耐震性が不十分な住宅を令和12年(2030年)までにおおむね解消するという目標を設定し、様々な公的支援を行いながら取組を進めている。
(ハード・ソフト一体となった防災対策の推進)
激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、我が国はこの100年で着実に防災・減災インフラの整備等が進められ、維持管理がなされてきた。そのため、前述した被害軽減の事例のように、昔なら大規模な災害が発生していたと思われる大雨や地震等であっても、防災・減災インフラの整備等によって災害発生が防止・軽減された地域も多々ある。また、このような地域の安全度向上に伴って、都市部では新たな住宅開発が行われ、また、周辺部では工場のための土地開発が進められるなど、国全体で土地利用の高度化が図られ、生産性の向上に寄与したことが、我が国の経済発展の一助になったとも言える。
しかし、ハード面の整備が進むにつれ、適切な管理を行わなければ、施設の老朽化や空き家の増加といった課題が生じる。また、国民の大多数が自然災害を直接経験することが少なくなり、また、それゆえに自然災害が遠い存在となった側面がある。「自分は大丈夫」、「自分の住む地域で災害は起きない」など、自然災害を自らのことと捉えられない、又は災害が発生するまで適切な防災行動を取る必要性を実感できない国民が増加している面も否定できない。
今後も、防災・減災インフラの整備等を着実に進め、維持管理や老朽化対策を適切に実施することの必要性は論をまたないが、第1章第5節で述べたとおり、ハード・ソフトの様々な対策を組み合わせることで被害を最小化する「減災」の考え方を徹底し、防災教育や防災訓練といったソフト対策の取組についても、改めて強化していくことが求められている。
7 耐震基準(昭和56年基準)が求める耐震性を有している住宅ストックの比率