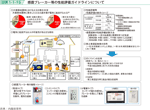2-5 大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討
平成25年12月に中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループより報告された「首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)」において、木造住宅密集市街地における同時多発延焼火災等の危険性が改めて示され、また、近年の大規模地震時における出火原因の過半数が電気を起因としていることから、その対策の必要性が指摘された。これらを受け、平成26年3月に閣議決定された「首都直下地震緊急対策推進基本計画」(以下、この項において「基本計画」という。)等において、感震ブレーカー等の有効性・信頼性を確保するための技術的検討及び普及を推進することとされた。
これらを踏まえて、平成26年9月から内閣府、消防庁、経済産業省により、「大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会」が開催され、感震ブレーカー等の性能評価の考え方や設置における留意点、今後の普及方策等についての検討や、模擬居室による振動実験が行われ、平成27年2月に、感震ブレーカー等の性能評価の考え方や設置における留意点等を取りまとめたガイドラインが公表された(図表1-1-15)。さらに、平成27年3月に検討会報告書がまとめられ、当面の普及目標として、延焼のおそれのある密集市街地のうち、特に切迫性の高い首都直下地震対策特別措置法に基づく緊急対策区域や南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく推進地域について重点的に取組を進め、10年を一つの区切りに25%以上の世帯への普及等について提言がなされた。この提言を受け、基本計画において同様の内容の減災目標が閣議決定された。
今後、基本計画及び報告書を踏まえ、木造住宅密集市街地を中心としたモデル調査等についての検討を行うとともに、関係者が一体となった大規模地震時の電気火災の発生抑制対策の推進を図ることとしている。