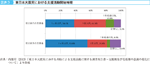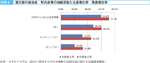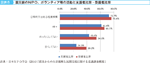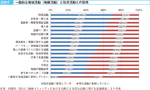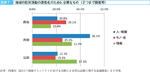2 地域コミュニティにおける共助による防災活動
現在、東日本大震災から3年以上が経過したが、被災地における支援活動は、発災直後と比較すると少なくなったといわれている。
内閣府が平成25年に実施した調査によれば、支援活動を行っている者に対して、支援活動を開始した時期についてたずねたところ、被災県外の支援者よりも被災県内の支援者のほうが、発災から1年経過以降に支援活動を実施した割合が高いことがわかっている。
これは、被災県内においては、自身が被災した者が多いことから、その対応が一段落した段階で、被災県外の支援者よりも遅れて支援活動に入った面もあると思われるが、一方で、被災した地域コミュニティに近い者(又は自身も被災者である者)のほうが、地域コミュニティの状況も踏まえながら長く支援を続けている面もあると思われる。
そして、復興においても、地域コミュニティにおける相互の助け合い(共助)が大きな役割を果たしていると思われる(図表3)。
また、東日本大震災の被災者に対する調査においては、東日本大震災前に自治会、町内会等の地縁活動への参加の程度が高い人たちほど、東日本大震災の際に、支援者として活動した比率(支援者比率)も支援を受けた比率(受援者比率)も高いという調査結果がある(図表4)。
さらに、同調査においては、東日本大震災前にNPO、ボランティア等の活動への参加の程度が高い人たちほど、東日本大震災の際に、支援者比率も受援者比率も高いという調査結果がある(図表5)。
これらを踏まえるならば、東日本大震災の前から、自治会・町内会等の地縁活動やNPO、ボランティア活動等への参加の程度が高い人ほど、大災害時にも孤立することなく、支援したり支援を受けたりすることができる可能性があるといえ、このような活動が地域コミュニティの防災力の向上に重要な役割を果たすと思われる。
一方、平成26年2~3月に内閣府が実施したwebアンケート調査によれば(調査概要参照)、地域コミュニティにおける防災活動を除く一般的な地域活動(地縁活動)と防災活動の関係をみると、一般的な地域活動(地縁活動)を行っている者のほうが、防災活動を実施している割合が高いことがわかる(図表6)。
ここから、一般的な地域活動(地縁活動)と防災活動の関係は深くなっており、一般的な地域活動(地縁活動)の活性化が、防災活動の活発化につながり、それが地域防災力の強化にもつながると思われる。
なお、地域活動の中でも、防犯活動(71.1%)、女性会・婦人会(68.6%)、高齢者・障害者福祉活動(64.4%)、老人会(63.3%)、盆踊り・祭り(62.1%)等に参加している者は、防災活動に参加している割合が比較的高い。これらは、一般的な地域活動(地縁活動)の中でも、特に日ごろから多くの地域住民とのつながりを有していたり、その関係が比較的長く継続される種類の地域活動であるが、このような性格を持つ地域活動と防災活動は、比較的親和性が高い可能性がある。
【調査概要】
<1>調査名 地域コミュニティにおける共助による防災活動に関する意識調査
<2>調査方法 調査会社によるWebアンケート調査
<3>調査対象者 3,000人
(20歳以上の神戸市、仙台市及び名古屋市在住者各1,000人を調査会社のモニター登録者の中から抽出)<4>実施期間 平成26年2月27日~3月4日
さらに、同調査において、自助・共助・公助を、それぞれ、「人・組織」、「モノ・金」、「情報」の3つの要素に分類した上で、地域の防災活動の活性化のために必要なものはどれかについて質問した。
その結果、まず、自助・共助・公助それぞれの中では、「共助」が重要だとする回答が最も多いことがわかった。
また、「共助」の要素の中でも、「人・組織」(48.1%)が最も必要だと考えられている。
そして、「公助」の要素のうち「情報」(37.1%)を必要だと回答した割合が全体で2番目に高くなっており、「公助」による情報発信が防災活動の活性化に特に必要だと考えられている(図表7)。
このことから、国民は、地域の防災活動の活性化のためには、地域コミュニティにおける防災に関する人・組織がしっかりしていることが必要だと考えており、また、同時に関連制度や支援に関する情報が不十分であることから、公助において、関連情報をしっかりと発信することを求めていると考えられる。
今後、行政において、地域コミュニティにおける防災活動の体制づくりを支援するとともに、積極的に関連情報の提供を行う等地域コミュニティと行政が連携して対応していくことが重要になる。
企業での防災活動における情報の重要性
ここまで、地域住民を対象にした調査の分析結果を紹介して、地域の防災活動の活性化のためには、行政からの情報提供が重要であること等について述べたが、ここでは、少し観点を変えて、企業に対する調査から判明した防災活動の活性化のための情報の役割について紹介しておきたい。
内閣府の「平成25年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」によれば、大企業が重要な経営資源だと考えているものは、「情報システム」が86.5%(平成23年度比10.8ポイント増)、「通信手段」が84.3%(同10.8ポイント増)、「データ・重要文書」が73.5%(同30.5ポイント増)となっており、上位に情報関係の資源があがっている。
これは、東日本大震災等の経験を踏まえたものであると思われる。つまり、東日本大震災のような大規模広域災害時には、「何が起きたか」を判断することが重要になるが、災害時には、通信回線の輻輳等により迅速に情報を入手することができない場合があるほか、入手できた情報も不正確で信頼できない場合もある。このような場合には、情報に基づいて適切な判断や行動を行うことも難しくなる。
そこで、その解決策として、災害にも強い「情報システム」、「通信手段」の多様化による情報共有、「データ・重要文書」の保全等が重要な経営資源にあげられていると思われる。
このように、企業の観点からも、防災活動の活性化に向けて、情報の在り方がとても重要だと考えられていることがわかる。