a 消防団の組織
2 国民の防災活動
2−1 消防団,水防団
(1)消防団
消防団は,消防組織法の規定により設置された市町村の消防機関で,ほとんどすべての市町村に設置されており,平成14年4月1日現在,全国で3,627団となっている。消防団活動を担う消防団員は,通常は各自の職業に従事しながら火災等の災害が発生したときは「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に基づき活動している特別職の地方公務員(非常勤)で,平成14年4月1日現在全国で93万7,169人となっている (図3−2−1) 。
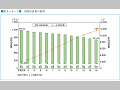
消防の常備化が進展している今日においても,消防団が地域の消防防災において果たす役割はきわめて重要であり,消防本部・消防署(常備消防)が置かれていない非常備町村にあっては消防団が消防活動を全面的に担っている。
b 消防団の活動
消防団は,常備消防と連携しながら消火・救助等の活動を行うとともに,大規模災害時等には多くの消防団員が出動し,住民生活を守るために重要な役割を果たしている。日常においても,各家庭の防火指導や防火訓練,巡回広報等住民生活に密着したきめ細かな活動を行っており,地域の消防防災の要となっている。
c 消防団の充実強化
消防団は,社会経済情勢の変化や都市化による住民の連帯意識の希薄化等の影響を受けて,団員数の減少,団員の高齢化,サラリーマン団員の増加等が進行している。団員数は10年前の平成4年と比べて5%減少し,団員の平均年齢は1.6歳上昇して37.1歳となっている。こうした中で,女性団員が着実に増加しており,平成14年4月1日現在,1万1,597人が地域の防災活動において活躍している。
消防団を取り巻く環境の変化に対応するため,消防庁では「新時代に即した消防団のあり方に関する検討委員会」を設置した。同委員会では,全国の市町村及び消防団を対象とした消防団の実態及び意識の調査を踏まえて,委員会においては,議論を重ねた成果を「新時代に即した消防団のあり方」をとりまとめた。
この報告書では,消防防災の観点,総合的な危機管理のあり方といった観点から,消防団の役割に関する将来展望を明確化し,消防団を要とする地域防災体制を確立する必要があることを提唱するとともに,その達成のため,総団員数の確保にあたって具体的な目標数値を設定すること,サラリーマン団員の活動環境の整備のため地域の実情に応じて消防団員の任務を弾力化すること,各消防団ごとに団員総数の少なくとも1割以上の女性消防団員を確保すること,災害現場における活動の安全確保のため若手・中堅団員の確保と中高齢者が活動しやすい環境作りを推進すること等,具体的な取組みを推進する必要性を提言している。
また,消防庁では,若手・中堅の団員を中心とした意見発表会や優良団員の表彰などの行事を開催するとともに,平成15年3月末から,消防団メールマガジンを創刊し,消防団活動を積極的にPRするなど,さまざまな取組みを通じて,消防団が要員動員力等の特性を発揮できるよう,充実強化を図っている。
|
(2)水防団
a 水防団の組織
水防は古くから村落等を中心とする自治組織により運営され発展してきた歴史的経緯等から,第一次的水防責任は市町村(あるいは水防事務組合,水害予防組合)が有している。
水防法ではこれらの団体を水防管理団体として定め,水防事務を処理させることができることとしており,平成14年4月1日現在,全国で3,233の水防管理団体が組織されている。
水防団員は,消防団員とともに水防管理団体(水防管理者)の所轄のもとに水防活動を行うこととなっており,平常時は各自の職業に従事しながら,非常時には水防管理者の指示により参集し水防活動に従事している。平成14年4月1日現在,専ら水防活動を行う水防団員は16,995人となっている (図3−2−2) 。
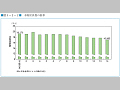
b 水防団の活動
洪水,高潮等による災害を防止するための水防活動は的確かつ迅速な行動が最大限に求められることから,事前の綿密な計画と十分な準備が必要である。
このため,都道府県は,[1]水防上必要な監視,警戒,通信,連絡,輸送,[2]水防管理団体相互間の協力応援,[3]水防に必要な資機材・設備の整備及び運用などについて定めた水防計画を策定している。
水防団は,災害発生時の洪水や高潮等の被害を最小限にくい止めるための活動のほか,水防月間や水防訓練その他の機会を通じて広く地域住民等に対し水防の重要性の周知や水防思想の高揚のための啓発,訓練及び危険箇所の巡回・点検等の活動を行っている。
c 水防団の充実強化
水防団員数は,最近の水防そのものに対する認識の低下と相まって減少傾向にあることに加え,大都市周辺における団員の地域外勤務による昼間不在,あるいは季節的地域外勤務による長期不在のため,現実には出動できない団員の増加等が進んでいる。
このような状況に対処するため,水防管理団体は,毎年,情報伝達訓練,水防技術の習得,水防意識の高揚等を目的とした水防団員等に対する水防演習を実施している。
また,水防団の活動に関する住民へのPRと水防団への参加の呼びかけとともに,水防団員の処遇等の改善措置が図られている。


 次頁
次頁