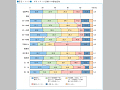平成14年9月に政府広報室(内閣府)により,「防災に関する世論調査」が,全国の20歳以上の3,000人を対象として,面接聴取で実施された(有効回収率71.8%)。
第3章 国民の防災活動
1 国民の防災に関する意識
今回の世論調査で明らかとなった国民の防災意識の概要は以下のとおりである。
(1)風化する防災意識
大地震が起こった場合に備えて,「携帯ラジオ,懐中電灯,医薬品などを準備している」と回答した者は,平成3年の調査では40.7%であったが,阪神・淡路大震災の直後の平成7年9月の調査では,59.1%に急上昇した。しかし,その後,減少に転じ,今回の調査では46.6%となっている (図3−1−1) 。

「食料や飲料水を準備している」と回答した者は,平成3年の調査では10.8%であったが,阪神・淡路大震災の直後の平成7年9月の調査では,23.5%に急上昇した。しかし,その後,減少に転じ,今回の調査では18.6%となっている (図3−1−2) 。

「家族との連絡方法などを決めている」と回答した者は,平成3年の調査では9.7%であったが,阪神・淡路大震災の直後の平成7年9月の調査では,16.3%に急上昇した。しかし,その後,減少傾向に転じ,今回の調査では12.8%となっている (図3−1−3) 。

このように,阪神・淡路大震災で高まった防災意識について,風化の兆しが見られる。
(2)建物の倒壊に対する危機意識は高いが,具体的な行動に結びついていない
「大地震が起こった場合,どのようなことが心配か」との質問に対し,「建物の倒壊が心配」と回答した者は,平成3年の調査では39.9%であったが,阪神・淡路大震災の直後の平成7年9月の調査では,61.8%に急上昇した。その後も横這い傾向で推移し,今回の調査においても,60.0%と高い水準を維持し,建物の倒壊に対する危機意識は高い。
しかしながら,「大地震に備えて自宅の耐震性を高くしている」と回答した者は,平成3年の調査で5.0%であり,阪神・淡路大震災の直後の平成7年9月の調査でも5.1%と変わらず,その後は微増はしているものの,今回の調査においても6.5%の低い水準にとどまっている。このように,建物の倒壊に対する高い危機意識は,必ずしも耐震性の向上のための具体的な行動に結びついていない。なお,近畿ブロックの数字も6.6%と全国平均レベルの低い水準にとどまっている (図3−1−5) 。

(3)家具の転倒防止に対する防災意識は向上
大地震が起こった場合に備えて,「家具や冷蔵庫などを固定し,転倒を防止している」と回答した者は,平成3年の調査では8.5%であったが,阪神・淡路大震災の直後の平成7年9月の調査では,12.9%に急上昇した。この数字は,その後も,上昇傾向にあり,今回の調査でも,14.8%と更に増加し,家具の転倒防止に対する防災意識は向上してきていることがわかる (図3−1−6) 。

(注)東山ブロックは,山梨県,長野県,岐阜県で構成される。
(4)ボランティア活動に熱心なのは50代
「今までに,災害時にボランティア活動を行ったことがある」と回答した者は,11.4%である。
年齢別に見ると,20代は6.3%,30代は8.7%とボランティアの経験者は少ないが,50代は14.6%,60代は12.1%,70代は14.5%であり,50代以上の世代に参加経験者が多い (図3−1−8) 。

また,今後「災害が発生したときにボランティア活動に積極的に参加したいか」という問いに対し,「参加したい」と参加意欲を積極的に表明した者は,20.8%である。年齢別に見ると,50代が27.2%と最も高く,20代,30代は,各々,18.1%,19.1%となっている。
(5)東海地震対策強化地域,南関東直下地震対策地域の住民の危機意識,防災意識は他の地域の住民と比較して高い
「住んでいる地域が安全であると感じているか」という問いに対し,「安全である」と回答した者は全国平均で66.1%であるが,東海地震対策強化地域,南関東直下地震対策地域では,各々,55.9%,58.1%と低く,危機意識が高い。
防災対策についても,大地震が起こった場合に備えて「食料や飲料水を準備している」と回答した者は全国平均で18.6%であるが,東海地震対策強化地域,南関東直下地震対策地域では,各々,28.4%,31.2%と高い (図3−1−11) 。

また,「ここ1〜2年ぐらいの間に,家族や身近な人と,災害が起きたらどうするかなどの話し合いをおこなったことがある」と回答した者は全国平均で34.9%であるが,東海地震対策強化地域,南関東直下地震対策地域では,各々,48.8%,41.6%と高い (図3−1−12) 。

なお,上記(3)で記述したとおり,家具の転倒防止についても,東海地震対策強化地域,南関東直下地震対策地域においては,対策が進んでいる。
また,「災害時の対応において,公助,共助,自助のいずれに重点を置くべきか」という問いに対し,回答は,「公助」が24.9%,「共助」が14.0%,「自助」が18.6%であり,「公助」に重点を置くべきとの回答が多かった。
しかしながら,東海地震対策強化地域では,「公助」が19.9%,「共助」が15.6%,「自助」が20.9%と「自助」に重点を置くべきとの回答が最も多く,自主防災意識の高さが現れている。
なお,職業別にみると,商工サービス・自由業の自営業主は「自助」に重点を置くべきという回答が27.4%と高い。
(6)高い農協の建物更正共済制度の普及率
「建物が地震保険や建物更正共済等によって補償されているか」という問いに対して,「補償されている」と回答した者は32.7%,「補償されていない」と回答した者は46.2%となっており,地震保険等の普及率は高くない。
職業別にみると,農林漁業の自営業主は,50.7%が「補償されている」と回答しており,農協の建物更正共済制度の普及率が高いことが伺える。また,管理職・専門技術職の雇用者も45.5%と高い (図3−1−15) 。

(7)災害時の流通業の営業に対する行政の支援を容認
「災害時に,スーパーやコンビニ等の民間企業が食料等の生活必需品を被災地の店舗で販売することに対し,行政が支援(優先的な輸送や通信の確保等)を行うことについての賛否」について質問したところ,「賛成」または「どちらかといえば賛成」である者は合計83.4%(「賛成」57.7%,「どちらかといえば賛成」25.8%)に達しており,他方,明確な「反対」は3.1%と少数であり,災害時の流通業の営業に関する行政の支援を容認する傾向があることが分かった (図3−1−16) 。

(8)まとめ
阪神・淡路大震災を契機に「建物の倒壊が人命に直結する」という知識は一般に定着し,建物の倒壊に対する危機意識は高いが,この危機意識は自宅の耐震改修等の具体的な行動に直結していない。
また,大地震が起こった場合に備えて「携帯ラジオ,懐中電灯,医薬品などを準備する」,「家族との連絡方法などを決める」等の具体的な事前対策を実施している割合も減少傾向であり,阪神・淡路大震災で高まった防災意識は,年月の経過とともに,風化の危機にさらされていることが今回の調査で明らかになった。
しかし,家具の転倒防止対策を講じている者は14.8%と低いものの,その割合は上昇傾向にあり,家具の転倒防止に対する防災意識は向上してきており,評価に値する。
また,東海地震対策強化地域,南関東直下地震対策地域の住民は,災害に対する危機感,自主防災意識は他の地域よりも高く,防災意識には明確な地域差が見られる。これは,関係者による長年の普及啓発活動の成果であると考えられる。
しかしながら,地震は東海地方,南関東地方のみで起こるわけではなく,例えば,東南海・南海地震については,今世紀前半での発生が懸念されており,また,阪神・淡路大震災の教訓は,「活断層の活動による直下型地震は全国どこにでも起こりうる」というものであり,自分が住んでいる地域が地震と無縁であるという過信は禁物である。
東海地震,東南海地震,南海地震等の海溝型の巨大地震が発生すると,その被害は広範囲に及ぶため,「公助」の役割もさることながら,住民自らが災害に立ち向かっていく,「自助」,「共助」の役割が極めて重要となる。
「自助」,「共助」の力を高めるためには,災害に自ら対応するための知識の提供,ハザードマップの提供,防災訓練の実施等の地道な努力を積み重ねていくことが大切である。
その際,国,地方公共団体等の関係者は,地域別,年代別,職業別に防災意識が異なることを十分に踏まえ,きめ細かな普及啓発活動を行っていくことが必要である。


 次頁
次頁