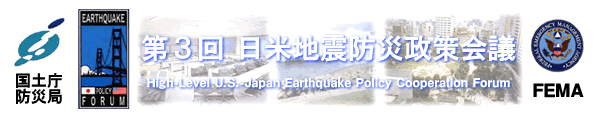 | ||
|
津波被害軽減と事前準備に関する包括的アプローチ カリフォルニア州における地震被害軽減プログラムの歩み 官民のユーザー主導によるライフライン耐震調査のパートナーシップについて 意図的な災害−アメリカにおける自然災害の再評価− FEMAによる改訂版沿岸建設マニュアル カリフォルニア州サンフランシスコ沿岸地域におけるHAZUSによる地震リスク評価能力を向上させるための官民のパートナーシップについて 地震被害軽減のための知識の拡充と活用 地震工学シミュレーションのためのネットワーク(NEES) 平時及び大規模災害時の情報交換 陸上や海底での地滑りによって生じる津波災害のモデル化について サンフランシスコ沿岸地域における「プロジェクト・インパクト」の概要 全米津波防災プログラム 津波に耐えうるコミュニティー 地震リスク軽減のためのプログラム 緊急事態における統合管理 | 全米津波防災プログラム | |
| ■プログラムの背景 1992年4月、カリフォルニア州北部で起きた地震により発生した津波を契機に、全米海洋大気局(NOAA)は、津波警報発令という任務に加えて、各地の津波対策の現状調査を連邦議会から命じられた。連邦政府は、州政府と協力して「全米津波防災プログラム」に取り組むこととなった。現在同プログラムは、NOAA、米国地質調査書(USGS)、連邦緊急事態管理庁(FEMA)の3つ連邦機関と、アラスカ州、カリフォルニア州、ハワイ州、オレゴン州、ワシントン州の5つの州から構成されている。 「全米津波防災プログラム」は、危険度評価、警報発令、防災の3つの要素からなる。危険度評価は各沿岸地域の性質や危険度を設定するもので、警報発令は、物理学的測定方法の研究、ネットワークのチェック、予報アルゴリズムの研究を行い、また警報発令の実務もになう。防災が目的とするところは、差し迫った津波の危険性に対する適切な対応である。 ■プログラムの現状 A.危険度評価 B.警報発令 C.防災 ■問題点と今後の見通し 問題点 今後の見通し ■日米協力体制の見通し 日米の津波モデル制作者は世界最高水準にあり、インターネットに接続していることもあって、協力体制は万全である。両国はともに遠方で発生した津波から海岸線を保護するための深海探知機を必要としていて、今後より一層の相互協力が見込まれる。 | ||
| |
