緊急地震速報の提供【気象庁】
特徴
1. 緊急地震速報により、企業や家庭等では、地震による大きな揺れが到達する前に、震度や猶予時間などを知ることができる。
2. 緊急地震速報は、適切に利用されれば、地震等の災害軽減に大きく寄与することが期待されている。
概要
緊急地震速報は、震源近くの観測点で地震波(P波)を検知して震源の場所や地震の規模を速やかに推定し、各地の揺れの強さや到着時刻を予測して、強い揺れ(主要動、S波)が到達することをその到達前にお知らせしようというものである。
一般向けの緊急地震速報は、原則1回の発表であるが、高度利用者向けの緊急地震速報については、時間経過とともにより精度の高い震度を予測できることから、繰り返し発表している。
高度利用者向けの緊急地震速報は平成18年8月1日から、一般向けの緊急地震速報は平成19年10月1日から提供を開始した。また、気象業務法を一部改正し(平成19年12月1日)、一般向けの緊急地震速報を地震動警報に、高度利用者向けの緊急地震速報を地震動予報に位置づけた。
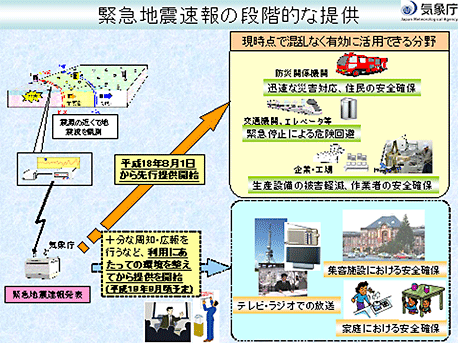
緊急地震速報の仕組みと利活用イメージ図
目的
住民や事業者等の利用者が、緊急地震速報を活用して主要動が到達する前に身の安全を図ったり、企業の防災対策・事業継続等のための適切な対策をとることができれば、地震被害の防止・軽減が期待される。
経緯及び活動状況
-
1. 緊急地震速報は、震源に近い観測点で地震波(初期微動:P波)を検知し、直ちに震源位置やマグニチュードを推定し、大きな揺れ(主要動:S波)が迫っていることを知らせる情報であり、広く国民に提供することにより、地震被害の大幅な防止・軽減に向け、以下のような利活用が図られることが期待されている(以下は、例示)。
(1)防災関係機関における迅速な災害対応、住民の安全確保
(2)病院、学校等の公共施設における避難、安全確保
(3)住民・家庭における火の元の確認、避難
(4)交通機関、エレベータ等の緊急停止による危険回避
(5)企業・工場における生産設備の被害軽減、重要データのバックアップ、作業者の安全確保
-
2. 一方で、緊急地震速報の実用化にあたっては、以下のような課題がある。
-
(1)利用者が緊急地震速報の特性や限界を十分理解して活用する必要がある。
緊急地震速報を受信する前に大きな揺れが来る場合がある。
-
(2)情報を受信した際に、不適切な行動をとることによる混乱や事故の発生
劇場や百貨店などで、非常口や階段に殺到
車を運転中に急ブレーキ など
-
-
3. 気象庁等におけるこれまでの取り組みの概要は、以下のとおり。
-
- 2004年 2月:
- 試験提供の開始
-
- 2005年 11月:
- 「緊急地震速報の本運用開始に係る検討会」の発足
-
- 2006年 3月:
- 試験提供を全国に拡大
-
- 2006年 5月:
- 「緊急地震速報の本運用開始に係る検討会」中間報告取りまとめ
-
- 2006年 8月:
- 先行的な利用分野への提供開始
-
- 2006年 11月:
- 緊急地震速報の伝達・利用に関するモデル実験開始
-
- 2006年 12月:
- 「緊急地震速報利用者協議会」発足
-
- 2007年 3月:
- 「緊急地震速報の本運用開始に係る検討会」最終報告取りまとめ
「気象庁 緊急地震速報一般提供に向けた周知・広報推進本部」設置
-
- 2007年 10月:
- 一般向け緊急地震速報の提供開始
-
- 2009年 2月:
- 「緊急地震速報評価・改善検討会」発足
-
-
4. 気象庁では、広く国民への緊急地震速報の提供に向けて、以下のような緊急地震速報の利用にあたっての「心得」を作成し、周知・広報に努めている。
(1)家庭での受信(テレビ・ラジオ、防災行政無線等による受信)
(2)多数の人が集まる施設(大型商業施設、映画館、競技場、駅、地下鉄など)での受信
(3)屋外(道路など)での受信
(4)乗り物で移動中(自動車運転中、エレベータ利用中など)における受信
| 団体名 | 気象庁 | |
|---|---|---|
| 連絡先 | 住所 | 〒100-8122 東京都千代田区大手町1-3-4 |
| 担当 | ||
| 電話番号 | 03-3212-8341(代表) | |
| URL | http://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/whats-eew.html | |
ssh19001
