「防災スイッチ」の導入と水位確認板の設置で速やかな避難を促す
兵庫県宝塚市川面地区自主防災会前会長の喜多毅さん
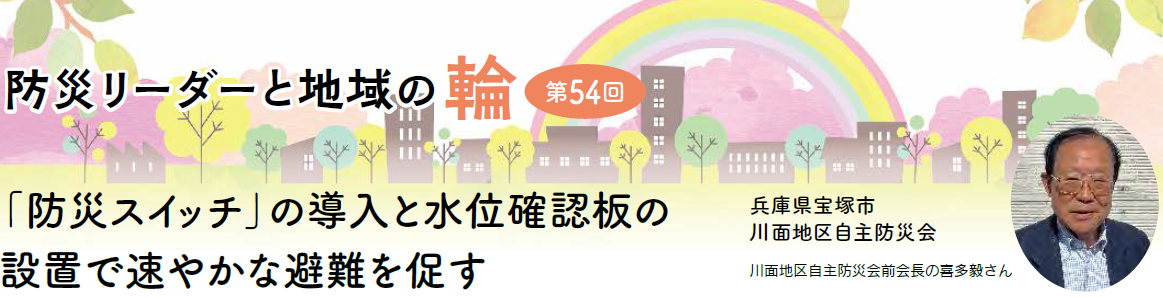
大阪・神戸のベッドタウンとして22万の人口を抱える兵庫県宝塚市。その中心街に位置するのが川面地区です。川面地区自主防災会は、阪神・淡路大震災の翌年の平成8年(1996年)に結成され、現在は19自治会、2万人の住民が所属しています。
川面地区は、二級河川の武庫川に面しているほか、その支流である一後川、荒神川、大堀川が地区内を流れており、広い範囲が浸水想定区域になっています。武庫川では、文化3年(1806年)に大洪水があり、宝塚でも大きな被害を記録していますが、最近は大きな水害が発生していないことから、住民の災害への危機感が薄くなっていることが課題となっていました。
そこで同自主防災会では、京都大学防災研究所の矢守克也教授及び竹之内健介准教授(現香川大学准教授)の支援の下、災害時の速やかな避難を促すための「防災スイッチ(避難スイッチ)」の仕組みづくりに取り込み、独自の地区防災計画を策定しました。
防災スイッチは、逃げ遅れを防ぐためにあらかじめ避難開始の目印を決めておくものですが、ここでは、川の水量を指標としました。当初は、目分量で観測していましたが、後に兵庫県の協力も得ながら武庫川と3支流、下の池の計5カ所に水位確認板を設置し、それぞれに具体的な水位を設定して、その水位に達した時点で避難を開始する防災スイッチとしました。
また、同自主防災会では、独自にポータルサイトを立ち上げ、様々な防災情報を発信しているほか、川面地区防災新聞「みんなの防災スイッチ便り」を発刊し、地区内で全戸配布する等住民への啓発活動を続けています。
一般に、自主防災組織では、高齢化や人材不足が課題となりがちですが、同自主防災会は、地区の伝統行事である「川面だんじり」の保存会がベースとなり、組織も保存会に合わせて西・東・南の3つの分会に分かれ、各地区の保存会の会長が、同自主防災会の分会長を務めています。年齢的にも働き盛りの層が多く、宝塚小学校区まちづくり協議会との連携を含め、コミュニティとして成熟していることが強みになっています。
これらの活動を牽引してきたのが、川面地区自主防災会前会長の喜多毅さんです。「誰にでもわかりやすいことが防災スイッチの良さですが、水位確認板の設置でさらにわかりやすくなったと思っています。今後はデータを蓄積して、適切なスイッチとなるように、水位の精度の向上を行っていきます。」と喜多さんは今後の活動を見据えています。

川面地区自主防災会の活動の一つである勉強会の様子

武庫川に架かる宝来橋の橋脚に設置された水位確認板

大堀川に設置された水位確認板とライブカメラ
