12の町会が一体となって目指す「災害に自立できる強い里づくり」
京都市 大原自治連合会大原自主防災会
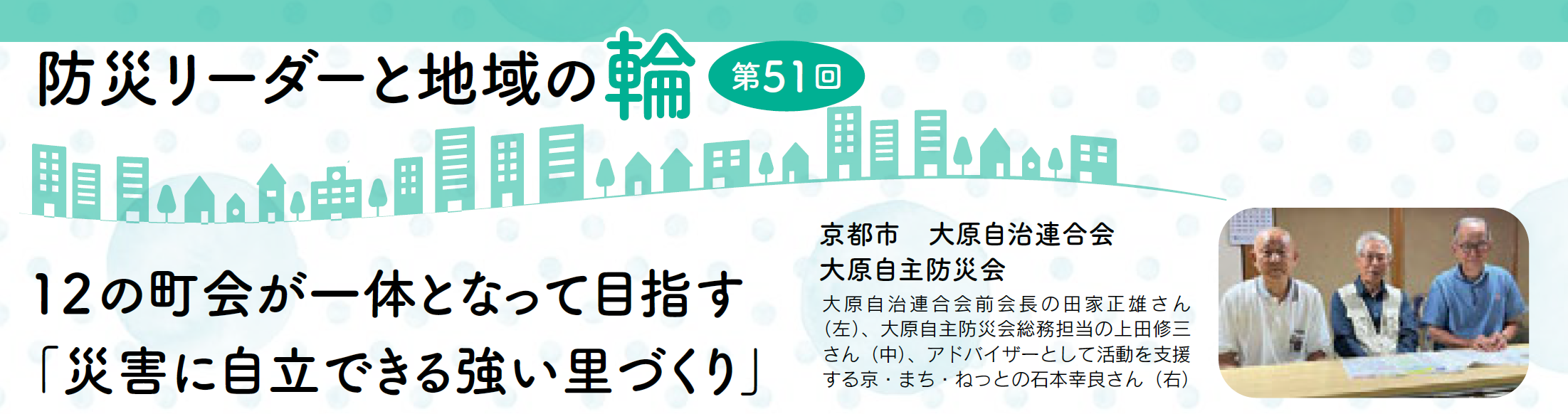
京都市左京区北部の大原地区は田園風景が広がる山里で、多くの人が訪れる観光地としても知られています。
大原地区には12の集落が分散して立地していますが、それぞれの町会(集落)ごとに防災マップや避難行動マニュアル、緊急連絡網、さらに災害時要配慮者が記された「大原安心台帳」がつくられ、3年に一度更新して各家庭に配布されています。防災マップには消防団がまとめていた大原地区の過去の災害の情報も記載されています。
「大原地区には花折断層が通っており、断層が活動して地震が発生した場合には孤立するおそれがあります。またそうなった時には京都市内は大きな被害となることが予想されるため、大原地区の支援が後回しになる可能性が高い。支援が来るまでは自助・共助でもちこたえる必要があります」と話すのは、大原自治連合会前会長の田家正雄さんです。
きっかけは、平成25(2013)年に策定した京都大原里づくりプラン(改訂版)において、重点プロジェクトとして「大原自主防災計画の策定」を掲げたことです。そして令和3年には目標としていた地区防災計画を策定し、市に働きかけて従来2か所だった避難所を4か所へと増やしたほか、避難所運営を自ら担い、消防団の判断で避難指示を発出できる体制も整えました。避難所単位での防災訓練を同時に実施することも行われています。
大原地区の防災まちづくりを支援するアドバイザーの石本幸良さんは、「里づくりプランも地区防災計画も含めて、自力でここまで実現しているのは凄いこと」と驚きを隠しません。もっとも、最初からすべてがうまくいっていたわけではありませんでした。
「最初の頃は安心台帳をつくると言っても、皆さん個人情報を出したがりませんでした。それが地道に活動を継続している中で、徐々に理解が得られるようになってきました。現在も『大原防災まちづくりニュース』を定期的に発行して全戸配布を続けています」と話すのは、大原自主防災会総務担当の上田修三さんです。
令和3年5月には実際に豪雨で避難指示が出され、実際の避難所の運営も経験し、その後の検証も行われました。自治連合会と自主防災会、消防団が一体となり、「災害に自立できる強い里づくり」を目指す活動は、確実に大原地区の住民に浸透しています。

避難行動マニュアル、地域の災害史がわかる防災マップ、防災まちづくりニュース。いずれも全戸配布される

4か所の避難所同時開設の避難訓練の様子
