避難機能付き共同住宅で育む共助の基盤
〈内閣府(防災担当)普及啓発・連携担当〉
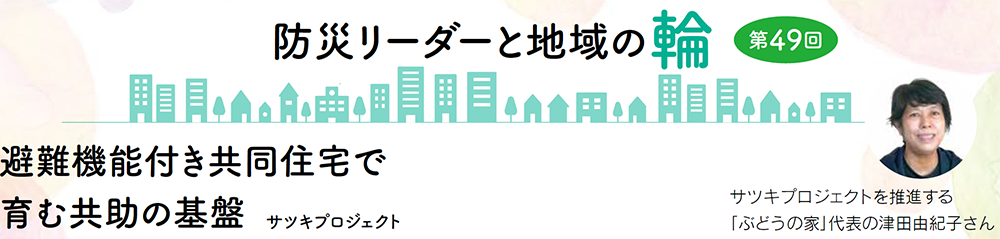
平成30(2019)年7月の西日本豪雨により甚大な被害を記録した岡山県倉敷市真備町。町内の小規模多機能ホーム「ぶどうの家」では2階まで浸水して建物は全壊、加えて近隣に住む施設利用者が命を落とす痛ましい出来事もありました。「亡くなった利用者は耳が悪いうえ、認知症も患っていました。こうした要介護者にとって避難のハードルは非常に高く、助かった方の中にも、『自分が避難所に行くと迷惑がかかる』『周囲が知らない人だと不安』と避難をためらった人がたくさんいました」と話すのは、ぶどうの家を運営する津田由起子さんです。
こうした経験から、津田さんら有志が中心となり、災害時に要介護者を取り残さない生活環境を実現するためにサツキプロジェクトが立ち上げられました。そして令和2年6月、真備町箭田地区にスロープで車椅子のまま2階に上がれる避難機能付き共同住宅を開所しました。被災したアパートを活用してリフォームを行い、2階の1世帯分はコミュニティルームとして居住者や地域に開放し、豪雨時には避難に利用できる仕組みになっています。
サツキプロジェクトの目的はハードを整備することにとどまりません。災害時に共助が機能するには、平時から住民同士に信頼関係を構築しておくことが重要だからです。
「避難先に知っている人がいるだけで避難の心理的ハードルは下がります。そのためには平時からコミュニティルームを利用してもらって、住民同士で見知った関係になっておく必要があります。定期的にみんなで集まって体操をしたり、お茶を飲んだり、イベントを行うようにしています。時には非常持ち出しを確認したり、マイタイムラインをつくったりといった防災の勉強会を開催することもあります」(津田さん)
共同住宅の入居者には、生活を支え合うことや災害時に自宅が避難所になる可能性があることを理解してもらっているそうです。現在は若い方も住んでおり、高齢者の見守りなどにも貢献しているといいます。
サツキプロジェクトはハードとしての避難機能付き共同住宅と、ソフトとしての住民の交流のどちらが欠けても成り立ちません。津田さんはサツキプロジェクトをひとつのモデルとして、全国に広めたいと考えています。

避難機能付き共同住宅

2階に設けられたコミュニティルーム

交流を深める住民の皆さん。取材の日は天気がよく、外でのお茶会でした
