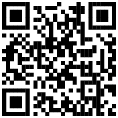「防災推進国民大会(通称「ぼうさいこくたい」)」とは
平成27年3月に第3回国連防災世界会議で採択された「仙台防災枠組2015−2030」を受け、平成27年9月、幅広い層の防災意識の向上を図ることを目的として、中央防災会議会長である内閣総理大臣の呼びかけにより、「防災推進国民会議」が発足しました。
平成28年度から毎年、内閣府では、各界各層の有識者から成る「防災推進国民会議」及び主に業界団体から成る「防災推進協議会」とともに、産学官、NPO・市民団体や国民の皆様が日頃から行っている防災活動を、全国的な規模で発表し、交流する日本最大級の防災イベントである「防災推進国民大会」を開催しております。本年度は、令和3年11月6日~11月7日岩手県釜石市にて開催いたしました。
被災地での「ぼうさいこくたい2021」開催と防災復興の取組
岩手県ふるさと振興部 県北・沿岸振興室
1 本改正の背景及び必要性について
それまでの日常が一変し、多くが失われた平成23年3月11日の東日本大震災津波から10年が経過しました。
岩手県は、震災の事実と教訓を次世代に継承し、防災力の向上に寄与していくことは、震災を経験した者の責務と考えており、震災から10年が経過した重要な年に、本県での防災推進国民大会(ぼうさいこくたい)開催を希望しました。
内閣府をはじめ、関係する皆様のご理解・ご尽力を賜り、6回目となる「ぼうさいこくたい2021」が、令和3年11月に被災地の岩手県釜石市で開催されました。
今大会は、初めてのハイブリッド形式(現地開催とオンライン開催の併用)での開催、初めての「オープニングセレモニー」(開催地からの特別プログラム)の実施、コロナ禍での初めての現地開催など、初の取組の多い大会でもありました。
「〜震災から10年〜つながりが創る復興と防災力」をテーマとして開催された今大会ですが、本県では、これまで国内外との数多くの「つながり」の中で復興を進めてきました。
本県にとって、今大会は、防災力の向上に寄与するとともに、震災復興へのご支援に対する感謝を伝える機会としても大きな意義を持つ大会になりました。
また、今大会に併せて開催した「いわて・かまいし防災復興フェスタ」では、本県沿岸市町村における防災学習の取組や高校生が主体となって取り組む伝承・防災活動などを、現地とオンラインを併用しながら幅広い層に発信することができました。
さらに、震災復興エクスカーションも企画し、東日本大震災津波伝承館「いわて TSUNAMI メモリアル」や震災遺構の視察、復興のシンボルとして知られる三陸鉄道の震災学習列車への乗車など、本県被災地でしか体験できない「学び」に、県内外からの参加者に触れていただくことができました。
本県では、これからも震災の事実と教訓の伝承、復興の姿の発信に永続的に取り組み、震災の風化を防ぎ、国内外の防災力強化につなげていくこととしていますので、今後とも皆様のご理解・ご協力をお願いします。
なお、大会当日のプログラムの多くは、ぼうさいこくたい2021の公式HPのほか、本県の「三陸防災復興プロジェクト」公式HPからも「オープニングセレモニー」などが、ご覧いただけます。「オープニングセレモニー」では、本県の「つながり」の一端を垣間見ることができますので、是非一度、ご覧ください。
●三陸防災復興プロジェクト

オープニングで挨拶する達増岩手県知事

県実行委員会主催セッションの様子

かさ上げ前の地盤に唯一残る“震災遺構”「米沢商会ビル」(陸前高田市)

三陸鉄道「震災学習列車」