防災・減災活動にはやさしい日本語が不可欠(在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン)
〈出入国在留管理庁 在留支援課〉
災害時のやさしい日本語での情報発信は、1995年の阪神・淡路大震災から取組が始まり、新潟県中越地震(2004年)や東日本大震災(2011年)を経て、全国的に広がっています。
一方で、災害発生時において、避難所などで外国人と日本人がうまくコミュニケーションを行うことができず、それが原因で外国人が孤立しがちになることが指摘されています。その背景の一つとして、日本人が、やさしい日本語によってコミュニケーションを行いやすくなることを認識していない点が指摘されています。
また、やさしい日本語の活用は、災害時のみならず平時においても、日本人と外国人双方のコミュニケーションを促進する際に有効です。平時からやさしい日本語を通じたコミュニケーションを行うことが、災害時における地域の防災・減災につながるものと考えられます。
●「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」掲載ページ
▶http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html 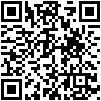
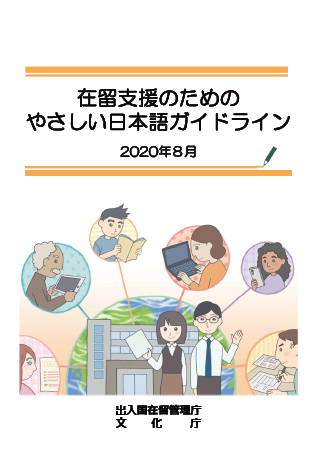
また、ガイドラインを解説した動画を法務省YouTubeチャンネルで公開しています。
