能登半島地震の教訓を生かそう
「これが要援護者マップです」。
石川県輪島市門前町の民生委員が示した1枚の住宅地図。地図のところどころに、蛍光ペンで印がつけてある。「黄色が一人暮らしのお年寄りが住んでいる家、ピンク色が寝たきりのお年寄りの家…」。地図はお年寄りや障害者などのいわゆる要援護者がどこに住んでいるかひと目でわかるように、4色で色分けされていた。この1枚の紙が、能登半島地震で大きな力を発揮した。
平成19年3月の能登半島地震。震源に近い門前町では震度6強の激しい揺れを観測した。当時、金沢放送局の記者だった私は、その日のうちに門前町に向かった。町に到着すると目に入ったのが、数多くの倒壊した木造住宅だった。門前町は65歳以上のお年寄りの割合が40%を超えていた。「かなりのお年寄りがケガをしているのではないか」。大きな不安を感じたが、実際にはケガをした人は29人にとどまった。
被害の軽減に役立てられたのが、冒頭で触れた要援護者マップだった。門前町の民生委員たちは、地震の揺れが収まるとマップを手に取り、受け持ちの要援護者の家に走った。そして、自力で動けないお年寄りを担いで避難所まで運び、倒れた建物や家具の下敷きになった人がいないか確認した。要援護者全員の安否を確認したのは、地震発生のわずか4時間後だった。
内閣府は平成18年に「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を作成して、全国の自治体にマップや名簿の作成を呼びかけている。しかし、いまだに対策に乗り出していない自治体が多くあるのが現状だ。消防庁の調査では、去年11月の時点で名簿の作成に着手していない自治体は18.3%あった。
防犯やプライバシーなどの観点から情報の提供を拒む住民がいるという事情はあるにせよ、まずは支援が必要な人がどこにいるのかを把握しないことには対策をとることはできない。
去年は台風や前線による大雨で65人が亡くなったが、このうち半数以上は高齢者だった。首都直下地震や東海地震などのリスクが足元に迫るなか、要援護者対策はより重要性を増している。能登半島地震から3年余り経った今でも、門前町の取り組みは他の自治体の参考になるはずである。
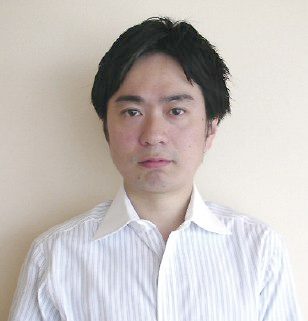
NHK報道局社会部
宮下 大輔
みやした・だいすけ
2002年NHK入局。金沢放送局を経て、2008年から社会部で災害の取材を担当。
