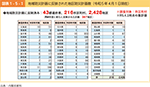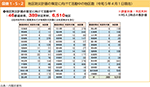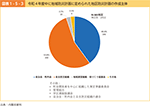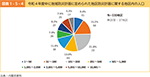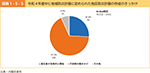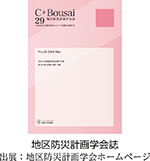1-5 住民主体の取組(地区防災計画の推進)
地区防災計画制度は、平成25年の「災害対策基本法」の改正により、地区居住者等(居住する住民及び事業所を有する事業者)が市町村と連携しながら、「自助」・「共助」による自発的な防災活動を推進し、地域の防災力を高めるために創設された制度である。これによって地区居住者等が地区防災計画(素案)を作成し、市町村地域防災計画に地区防災計画を定めるよう、市町村防災会議に提案できることとされている。
地区防災計画は、地区内の住民、事業所、福祉関係者など様々な主体が、地域の災害リスクや、平時・災害時の防災行動、防災活動について話し合い、計画の素案の内容を自由に定め、その後、市町村地域防災計画に位置付けられることで、「自助」・「共助」と「公助」をつなげるものである。計画内容はもとより、地区住民等が話し合いを重ねることなど、作成過程も共助の力を強くする上で重要である。
令和5年4月1日現在、43都道府県216市区町村の2,428地区の地区防災計画が地域防災計画に定められ、さらに46都道府県389市区町村の6,510地区で地区防災計画の策定に向けた活動が行われている。制度創設から10年が経過し、地区防災計画が更に浸透していくことが期待される(図表1-5-1、図表1-5-2)。
(1)地区防災計画の動向
内閣府において、令和4年度中に地域防災計画に定められた367地区の地区防災計画の事例等を分析したところ、以下のような特徴が見られた(図表1-5-3、図表1-5-4、図表1-5-5)。
<1> 地区防災計画の作成主体は、40.0%が自治会・町内会、54.8%が自主防災組織であった。
<2> 地区内の人口については、59.4%が500人以下、71.2%が1,000人以下であった。
<3> 地区防災計画策定のきっかけは、67.3%の地区が「行政側の働きかけ」であった。
このことから、地区防災計画の策定には、行政による後押しが重要であると考えられる。
(2)地区防災計画の策定促進に向けた内閣府の取組
内閣府は、地区防災計画の策定促進のため、地区防災計画ガイドライン等の地区防災計画の策定の際に参考となる資料の作成や、地区防災計画を地域別・テーマ別に一覧できる「地区防災計画ライブラリ」の構築を行っている。また、令和5年度には以下のとおりフォーラムや研修等を開催した。
(参照:https://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/index.html)

<1> 地区防災計画フォーラム2023「関東大震災100年の教訓を踏まえた地区防災計画づくり」の開催
各地における地区防災計画づくりに関する事例や経験の共有を図り、地区防災計画の策定を促進するため、「地区防災計画フォーラム2023「関東大震災100年の教訓を踏まえた地区防災計画づくり」」を、令和5年9月17日に「防災推進国民大会(ぼうさいこくたい)2023」の一つのセッションとして開催した。本フォーラムでは、関東大震災の被災地である東京、神奈川をはじめとする各地の地区防災計画づくりの事例を踏まえて、有識者と内閣府担当官による議論が行われた。また、本フォーラムのアーカイブ動画を公開した。
<2> 地区防災計画の作成に関する基礎研修会の開催
地区防災計画の作成に取り組む方々に向けて異なる立場の視点や取組を紹介することで、地区防災計画の作成を推進するため、「地区防災計画の作成に関する基礎研修会」を令和5年12月22日にオンライン配信により開催した。
同研修会では地区防災計画の作成支援に取り組む有識者、自治体の職員、それ以外の作成支援人材の方などがそれぞれの立場における経験について述べた後、参加者からの質問に回答した。また、この研修会についてアーカイブ動画を公開した。
<3> 地区防災計画に関するモデル事業
内閣府は、平成26年度から地区防災計画の作成の支援のためのモデル事業を実施している。令和5年度は、山梨県山梨市日川地区、大阪府岸和田市畑町及び岡山県矢掛町中川地区が対象となり、有識者や内閣府担当官の支援の下、地区防災計画づくりを進めた。
地区防災計画制度施行10年を迎えて
神戸大学名誉教授・地区防災計画学会名誉会長 室﨑 益輝
災害が進化すれば、それに見合う形で防災も進化しなければならず、コミュニティ防災も進化しなければならない。東日本大震災は、そのコミュニティ防災の進化が必要なことを、私たちに教えてくれた。その東日本大震災を受け、平成25年の6月に災害対策基本法が改正され、コミュニティ主体の地区防災計画制度の規定が盛り込まれた。
この改正を受け、翌年の3月に地区防災計画策定のガイドラインが示され、4月からその施行が始まった。今年は、その施行から10年を迎える。15地区のモデル事業からスタートした取組であったが、燎原の火のように地区防災計画の取組は全国に広がり、10年間で内閣府が把握しているだけでも9,000近くの地区で取り組まれている。
地区防災計画制度は、防災における協働や協治の大切さを踏まえ、公的な地域防災計画の中に、ボトムアップ型のコミュニティ提案としての地区防災計画を取り込んで、地域の防災力の向上を図ろうとするものであった。第一に地域の実状に即した防災の展開、第二に住民の自発性を引き出す防災の展開、第三に多様な担い手が連携する防災の展開、第四に持続的に課題を追及する防災の展開を、企図していた。
その中から、内閣府が事例集として提示している「地区防災計画ライブラリ」に示される創意工夫に満ちた取組が生まれている。応急時の活動だけでなく、予防時や復興時の活動まで広がっている。居住者に加えて事業者や市民団体さらには関係人口が関わる活動、行政区界を飛び超えて隣接コミュニティが連携する活動も生まれている。さらには、それらを産学官民の関係者が集まって研究する「地区防災計画学会」のような場もできている。
令和6年能登半島地震でも、地区防災計画の重要性が確認されており、より多くのコミュニティで果敢に取り組まれるようにしたい。