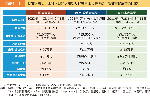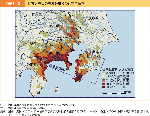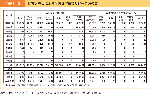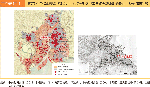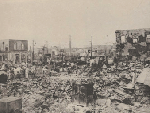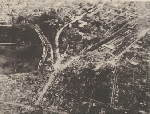第1章 関東大震災からの100年を振り返る
図表1-1は、関東大震災の被害状況等について、その後の二つの大震災である阪神・淡路大震災及び東日本大震災と比較したものである。関東大震災は、その後の二つの大震災と比べても、人的・物的被害の甚大さ、当時の社会経済に与えたインパクトの大きさのいずれの観点からも極めて大きい規模の災害であったことがわかる。
我が国の災害対策は、大規模災害の発生とその教訓を反映させる形で充実・強化が図られてきた。関東大震災以降、災害対策の転換点となった大規模災害としては、上述の二つの大震災のほか、昭和34年(1959年)の伊勢湾台風が挙げられる。
このため、本章では、まず、関東大震災に焦点を当て、第1節において、その被害の様相を詳述するとともに、第2節及び第3節において、それぞれ応急対策と復興の取組を振り返る。
その上で、第4節において、関東大震災を契機として充実・強化された災害対策を取り上げる。さらに、第5節において、その後の伊勢湾台風及び二つの大震災を契機として充実・強化された様々な災害対策についても触れ、関東大震災を出発点とした我が国における災害対策の歩みを俯瞰することとする。
第1節 関東大震災による被害の様相
(関東大震災の概要)
関東大震災は、大正12年(1923年)9月1日11時58分に発生した、マグニチュード7.9と推定される地震(大正関東地震)によってもたらされた災害である。この地震により、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県で震度6を観測したほか、北海道道南から中国・四国地方にかけての広い範囲で震度5から震度1を観測した。1
同地震は、相模トラフを震源とする海溝型地震であり、震源の直上に箱根や丹沢などの中山間地があることに加えて、人口が集中する首都圏にも近いことから、多岐にわたる被害を発生させた。具体的には、強震によって10万棟を超える家屋を倒潰2させるとともに、山間部での崖崩れなどの土砂災害、沿岸部での津波被害といった被害を発生させた。また、発生が昼食の時間と重なったことから、多くの火災が発生し、大規模な延焼火災に拡大した。さらに、地盤の液状化による被害は広範囲に及び、震源域から遠く離れた埼玉県の低地でとりわけ激しかった。
(人的被害・住家被害)
関東大震災により全半潰・焼失・流失・埋没の被害を受けた住家は総計約37万棟に上り、死者・行方不明者は約10万5,000人に及んだ。
人的被害の多くは、火災によるものであり、約9万人の死者・行方不明者が発生したと推計されている。特に本所区(現墨田区)横網町の被服廠(ひふくしょう)跡で起こった火災では、避難していた住民約4万人が亡くなった。一方、住家全潰による死者等も約1万人に上るほか、津波、土砂災害、工場の倒潰による死者等も多数発生するなど、様々な要因により人的被害が発生している。
住家被害については、地震の揺れによる全半潰が約20万棟以上発生した。特に、神奈川県の鎌倉郡(当時)、千葉県の安房郡(当時)等では全潰率が60%以上に達した。また、東京府を中心とした火災による焼失や、神奈川県や静岡県等で津波による流失や土砂災害による埋没も発生した。
(ライフライン被害)
ライフラインにも甚大な被害が生じた。多数の水力発電所や火力発電所、送電線や変電所が被害を受け、一般家庭への配電が再開されたのは9月5日の夜であったとされる。都市ガスについては、東京市(当時。以下同じ。)の約半数の世帯を占める約24万戸に供給されていたが、そのうちの約14万戸の家屋は焼失した。残りの約10万戸に対しては、9月末から部分的な供給が再開されたものの、完全な復旧は年末となった。上水道については、9月4日から山の手方面から徐々に通水し始めたものの、被害が甚大であった本所・深川等では時間を要し、全域に通水が完了したのは11月20日であった。
鉄道についても、東京や神奈川を中心に被害が生じた。192か所の停車場のうち178か所が全潰や破損あるいは焼失した。また、地震発生時に運転していた112の列車について、23の列車が転覆又は脱線し、11の列車が火災に遭遇した。多くの路線は地震から1週間ないし3週間で復旧したものの、東海道本線の横浜-桜木町間のように12月末頃までかかった区間や、熱海線の根府川(ねぶかわ)駅付近など、全線開通まで1年半を要した区間もあった。一方、総武本線の亀戸-稲毛間のように、9月1日のうちに再開した路線もあった。
1 当時の震度階級は震度0から震度6までの7階級であったが、家屋の倒潰状況などから相模湾沿岸地域や房総半島南端では、現在の震度7相当の揺れであったと推定されている。
2 本節では、関東大震災による住家被害について、「壊」ではなく「潰」の字を用いている。これは、当時の木造住家の構造的被害の態様が「壊れる」というより「潰れる」であったとする中央防災会議専門調査会の報告書の記述(中央防災会議(2006)「関東大震災報告書 第1編」)に即したものである。