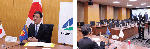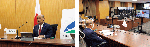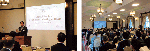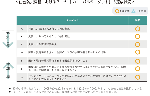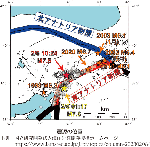4-2 二国間等防災協力
内閣府は国際機関を通じた取組に加え、海外からの防災を担当する閣僚級の訪問等の機会を通じて、防災政策の経験を共有するなど、世界各国の政府における防災担当部局との連携を深めている。
(1)日ASEAN防災閣僚級会合の開催を通じたASEANとの連携
令和元年11月に安倍内閣総理大臣(当時)が出席した「第22回ASEAN+3(日中韓)首脳会議」の議長声明を踏まえ、日本政府(内閣府)とASEAN加盟10ヶ国の防災担当部局による「日ASEAN防災閣僚級会合」が令和3年10月に発足した。
令和4年10月20日、「第2回日ASEAN防災閣僚級会合」がオンラインで開催され、星野内閣府副大臣が共同議長として出席した。同会合では、「日ASEAN防災行動計画」が策定され、今後一層協力を深化させていくことを確認した。
(2)内閣府と米国連邦緊急事態管理庁(FEMA)との連携
米国連邦緊急事態管理庁(FEMA:Federal Emergency Management Agency)とは、平成26年12月に締結された協力覚書に基づき、国際会議やビデオ会議等を通じて情報共有や意見交換を実施している。
(3)日中韓防災担当閣僚級会合の開催を通じた日中韓三国の連携
平成20年の「第1回日中韓首脳会議」における「三国間防災協力に関する共同発表」に基づき、平成21年以来、日中韓三国が、日中韓防災担当閣僚級会合を持ち回り開催している。
令和4年7月14日、「第7回日中韓防災担当閣僚級会合」がオンラインで開催され、二之湯内閣府特命担当大臣(防災)(当時)が出席した。会合では、それぞれの国から、近年の災害や防災政策の進展について発表するとともに、仙台防災枠組が令和5年に折り返し時期を迎えることを踏まえ、これを着実に実施し、三国間で情報と経験の共有を促すことを、共同声明として取りまとめた。
(4)防災技術の海外展開に向けた官民連絡会(JIPAD)の活動
「防災技術の海外展開に向けた官民連絡会(JIPAD:Japan International Public-Private Association for Disaster Risk Reduction)」は、我が国が強みを有する防災技術やノウハウを、官民が一体となり積極的に海外展開していくことを目的に令和元年に設立されたものであり、令和5年3月現在で207企業・団体が会員となっている。
令和4年12月2日には、第3回JIPAD総会を開催し、大使・臨時大使10名を含む38ヶ国・地域41名の大使館等職員、30以上の日本企業・団体が参加の下、星野内閣府副大臣が開会挨拶を行い、水鳥国連事務総長特別代表(防災担当)による基調講演、関係省庁等からの報告などが行われた。
JIPADでは、我が国の防災政策・技術・ノウハウを一体的に紹介するとともに、官民ネットワークを構築し、防災協力関係を強化する「官民防災セミナー」を開催している。
令和4年9月、前述のアジア太平洋防災閣僚級会議の会期中に、豪州(ブリスベン)にて、JICAと連携してアジア太平洋島嶼国官民防災セミナーを開催した。同セミナーでは、JIPAD企業・団体がプレゼンテーションを行うとともに、参加者との個別面談の場を提供した。
令和5年2月、JICA研修でベトナムから防災行政幹部や担当官が訪日する機会を捉え、JICAと連携し、内閣府において官民防災セミナーを実施した。
令和5年3月、前述のアジア防災会議と連携し、仙台市にて、内閣府とADRCが主催するサイドイベントとして官民防災セミナーを開催した。同セミナーにおいては、フィジーの閣僚の他、ASEAN事務局及びAHAセンターの担当者を仙台市に招待し、また、アジア防災会議に参加していたアジア諸国の防災関係者も多数参加した。
「仙台防災枠組」に基づく自治体レベルのモニタリングの取組
平成27年(2015年)3月に仙台市で開催された「第3回国連防災世界会議」において「仙台防災枠組2015-2030」が採択されたが、令和5年は、同枠組の令和12年(2030年)までの推進期間の中間年に当たる。このため、各国において目標等の進捗に関する中間評価が進められたが、仙台市は、世界に先駆けた自治体レベルでの中間評価に、東北大学災害科学国際研究所とともに取り組んだ。
評価作業の一環として、災害被害に関するデータ等を分析した結果、仙台市がこれまで市民や関係団体などのステークホルダーとともに推進してきた防災・減災施策が一定程度寄与し、仙台防災枠組の掲げる目標(死亡者・被災者・経済的損失・重要インフラの被害の減少などの7つの「グローバルターゲット」)を達成中であることが明らかとなった。一方で、災害種別ごとの分析を行った結果、風水害による被害は増加傾向にあることが明確となった。このため、仙台市では、統計を参考としながら効果的な防災・減災対策を進めるとしている。
また、評価作業を通じて、自治体における災害統計分析に有用なデータの項目等を確認できたことから、仙台市では、同様の分析を他の自治体で検討する際の参考となるよう、今後、国連や国等の機関とも連携し、評価手法の共有も含めた成果の積極的な発信に努めることで、国内外における仙台防災枠組の推進に貢献していくとしている。
トルコ南東部を震源とする地震による被害と日本の支援
トルコ南東部を震源として、令和5年2月6日4時17分(現地時間)頃、マグニチュード7.8の地震が発生し、その約9時間後にはマグニチュード7.5の地震が発生した。その他、複数の余震が発生し、トルコ及びシリアに大きな被害をもたらした。このうちトルコでは、死者50,000名以上(令和5年3月21日時点)、負傷者115,000名以上(同)、建物倒壊約50,000棟(同)などの被害が生じている。都市部を中心に甚大な被害が発生しており、被災各所では建造物が倒壊・一部損壊し、道路も各所で寸断されているほか、多くの市民が避難生活を余儀なくされている。2月27日に公表された世界銀行の報告書によると、本地震の直接的被害は推定342億ドル(トルコの2021年のGDPの4%に相当)とされている。また、シリアでは、正確な数値の確認は困難であるが、5,900名を超える死者が発生していると報道されている(令和5年3月21日時点)。
これに対して、日本政府は、トルコ政府からの要請に基づき、同国へ国際緊急援助隊の救助チームを2月6日以降順次派遣するとともに、医療チームを同月10日以降派遣した。3月6日には専門家チームを派遣し、被災した建物、インフラの状況を確認し、復興・復旧に向けた技術的助言を実施した。
また、トルコ・シリア各政府の要請に基づき、緊急援助物資を供与するとともに、2月24日には、両国に対する約2,700 万ドルの緊急人道支援の実施を発表した。さらに、3月20日に開催されたEU・スウェーデン共催のドナー会合において、林外務大臣によるビデオメッセージを発出し、日本政府の支援を紹介した上で、被災地の復興に向け、今後も資金協力や技術協力等を通じて貢献していく旨表明した。