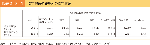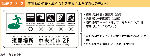2-3 指定緊急避難場所と指定避難所の確保
「指定緊急避難場所」とは、津波や洪水等による危険が切迫した状況において、住民等の生命の安全の確保を目的として住民等が緊急に避難する施設又は場所を位置付けるものであり、「指定避難所」とは、避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、又は災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設となっている。
東日本大震災時においては、避難場所と避難所が必ずしも明確に区別されておらず、そのことが被害拡大の一因ともなった。このため、内閣府は平成25年に「災害対策基本法」を改正し、市町村長は指定緊急避難場所及び指定避難所を区別してあらかじめ指定し、その内容を住民に周知(公示)しなければならないこととした。令和4年4月1日現在の指定緊急避難場所の指定状況は図表2-3-1のとおりとなっている。
また、指定緊急避難場所は国土地理院が管理するウェブ地図「地理院地図」で閲覧できるようにしている(参照:https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/hinanbasho.html)。
内閣府は、消防庁とともに、地方公共団体に対して指定緊急避難場所の指定等を促しているところである。また、災害の種類ごとに指定緊急避難場所を指定することとなっているため、案内板等を整備及び更新する際は、避難者が明確に判断できるように制定した「災害種別避難誘導標識システム(JIS Z 9098)(平成28年3月)」に倣い表示するように全国の地方公共団体に呼びかけている(図表2-3-2)。なお、災害種別避難誘導標識システムの国際規格(ISO22578)が令和4年2月に発行された。
(参照:https://www.bousai.go.jp/kyoiku/zukigo/index.html)
また、「災害対策基本法」第49条の7に基づく指定避難所の指定状況については、平成26年10月1日現在は48,014ヶ所であったが、令和4年12月1日現在は82,184ヶ所に増加した。
災害時に避難所において不自由な生活を強いられる状況下においても、生活の質を向上させ、良好な生活環境の確保を図ることが重要と考えられる。このため、内閣府では市町村における避難所や福祉避難所の指定の推進、避難所のトイレの改善、要配慮者への支援体制や相談対応の整備等に係る課題について幅広く検討し、必要な対策を講じている。
近年では、令和2年度に開催された「令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループ」(以下「高齢者SWG」という。)において、福祉避難所ごとに受入対象者を特定して、あらかじめ指定の際に公示することによって、受入対象者とその家族のみが避難する施設であることを明確化できる制度を創設することが適当であるとされたことを踏まえ、令和3年5月に「災害対策基本法施行規則」(昭和37年総理府令第52号)及び「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」等の改正を行った。
さらに、避難所をめぐって、感染症対策、生活環境等の改善、立地状況に応じた適切な開設、防災機能設備等の確保、女性の視点を踏まえた避難所運営などの対応が必要となっていることから、令和4年4月に「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」、本取組指針に基づく「避難所運営ガイドライン」と「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」を改定し、公表した。
また、避難所運営における先進的な取組事例について、令和4年7月に「避難所における生活環境の改善および新型コロナウイルス感染症対策等の取組事例集」を公表した。