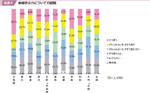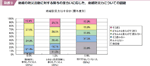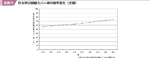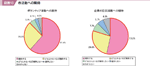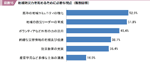5 地域防災力及び防災分野における「新しい公共」の活動に関する国民意識
内閣府では,郵送による国民意識調査を平成22年2月27日から3月8日にかけて実施した。全国の20歳以上の男女3,000人に調査票を郵送し,1,196人から回答を得た(回収率39.9%)。この意識調査は,地域防災力及びボランティア等による防災活動について,国民がどのように考えているのか把握し,今後,地域防災力を高める方策の検討に役立てるために実施したものであり,その結果の概要を以下紹介する。
(1)地域防災力についての認識
意識調査では,まず,回答者が住む地域において地域防災力は十分だと考えているかどうか尋ねるとともに,なぜそう思うのか理由を尋ねた。
結果を見ると,地域防災力が十分備わっていると肯定的な回答をした人(「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を回答した人)は38.1%,また,地域防災力が十分でないと否定的な回答した人(「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」を回答した人)の割合は36.8%となった(図表6)。
これを地域別に見ると,北海道では地域防災力が十分であるとの回答が59.4%,地域防災力が十分でないとの回答が20.3%であるのに対し,九州・沖縄では,地域防災力が十分であるとの回答が25.4%,地域防災力が十分でないとの回答が48.3%となるなど,地域により大きな差が見られる結果となった。
次に,回答理由を見てみると,肯定的な回答をした人の理由としては,「普段から近所づきあいがあり,地域に連帯感があるため」が62.7%を占め,次いで「消防団や自主防災組織等の活動が充実していると思うため」が46.5%で続いた。
逆に,否定的な回答をした人の理由としては,「地域の高齢化が進んでおり,災害発生時に頼りになる人がいないと思うため」が52.5%と最も高く,次いで「普段から近所づきあいが希薄であり,地域に連帯感がないと思うため」が46.3%で続いた(図表7)。
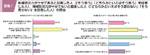
これを地域別の傾向との関係で見ると,肯定的な回答が多かった北海道では,その理由として「近所づきあい・地域の連帯感」を上げた人が85.4%と全国平均(62.7%)を大きく上回っている点に特徴が見られたが,地域防災力についての認識において反対の結果が出ている北海道と九州・沖縄のいずれもが,地域別の自主防災組織の活動カバー率(図表8)において全国平均(73.5%)と比べて顕著に低いなど,必ずしも明確な傾向が読み取れない面も見られる。
なお,地域防災力は十分かという冒頭の質問について,回答者の地域防災活動に対する関与の度合い(全体に対する割合は,積極的に参加:22%,ときおり参加:22%,特に何もしていない:56%)によって回答を分類すると,積極的に参加している人ほど「わからない」との回答が平均に比べて減少していることから,地域防災力に関する意識が強いことが伺えるが,積極的に参加している層においても,肯定的意見と否定的意見の割合はほぼ拮抗しており,自らの活動への参加が地域防災力を支えているとの意識とともに,活動に伴う問題も強く意識されていることがうかがえる(図表9)。
もっとも,今回あわせて,地域防災力についての認識と全国62のボランティア団体に尋ねたところ,19の団体から回答が得られたが,地域防災力が十分であると肯定的な回答をした団体が5団体であったのに対して,地域防災力が十分でないと否定的な回答をした団体は14団体と多くを占める結果も出ている。
(2)地域防災力の変化についての認識
次に,意識調査では,地域防災力が以前と比べてどう変わっていると思うのか,また,なぜそのように思うのか理由について,尋ねた。
結果を見ると,地域防災力が以前よりも高まっていると認識している人,地域防災力は以前よりも低くなっていると認識している人は,それぞれ17.1%,17.3%とほぼ同数となったが,それ以上に,「変化なし」と認識している人が30.0%,「わからない」との回答が35.5%と最も多かった(図表10)。
地域防災力が以前よりも高くなっていると回答した理由としては,「消防団や自主防災組織等の防災活動が活発になってきていると思うため」が55.9%と最も高く,逆に,低くなっていると回答した理由としては,「地域の高齢化が進み,若者が減ってきていると思うため」が79.4%と最も高く,「近年,近所づきあいが減ってきていると思うため」が65.7%で続いた(図表11)。
図表12のとおり,自主防災組織への参加及び活動カバー率は上昇傾向にあり,「防災活動が活発になってきていると思うため」という回答にはその点が反映されているのではないかと思われる。
(3)地域防災力を高める観点からの「新しい公共」の活動への期待
ボランティア,企業等が防災に関する活動に携わっている事例が各地で見られることは前述したとおりであるが,これらの活動に対する国民意識を把握するため,次いで,防災ボランティア活動への期待,企業の防災活動への期待について尋ねた。
いずれの活動についても,「期待する」「どちらかといえば期待する」と肯定的な回答を示した人の割合が,対ボランティア87.9%,対企業79.8%となり,「期待しない」「どちらかといえば期待しない」と否定的な回答をした人の割合を大きく上回り,地域防災力を高める観点からボランティア,企業等の活動への期待の大きさが伺える結果となった(図表13)。
また,各個人としても,半数以上の方が,災害発生時に余力があれば,避難所における協力(救援物資の運搬,避難所の清掃,高齢者の話し相手など),初期消火活動,体の不自由な方等の避難誘導,周囲の住民の救出・救護活動など,できることをしたいと考えていることも分かった(図表14)。
(4)地域防災力を高めるために必要なこと
国民への意識調査の最後に,地域防災力を高めるためにはどのような視点が必要か尋ねたところ,地域防災力を高めるための視点として,「既存の地域コミュニティの強化」「地域の防災リーダーの育成」「ボランティアなど外部の力の活用」の3つの視点が高い割合となり,地域内部での努力と外部活力の活用の両者が重要と考えられている結果となった(図表15)。