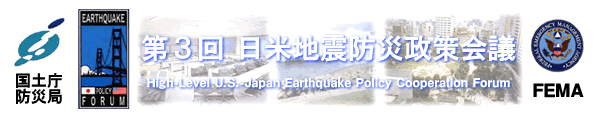 | ||
|
| 風および地震の影響に関する米日共同パネルについて 将来の展望 | |
| ■風および地震の影響に関する米日共同パネルは、強風、地震、津波などの災害に見舞われた際に、構造物の被害を軽減するための技術開発や技術交換を目的に、1969年に設置されたものである。「天然資源の開発利用に関する日米会議(UNJR)」の18のパネルの1つで、32年の歴史をもつ。参加機関は米国側19、日本側7の計26機関。実際の研究は11ある専門委員会毎に米日共同で行われている。同パネルは1週間の共同会議と1週間の現地視察の2週間のプログラム制で、毎年度日米交代で開催される。日本側議長は建設省土木研究所から、米国側議長は商務省標準技術院から選出されている。 同パネルは、過去32回の共同会議で1900の報告書を作成し、60以上の専門委員会を設立し、200人以上の研究員の交換を行った。その成果 の一例は以下のようなものである。 ・研究の土台となる地震の記録のデジタル化と相互交換 しかし、関係機関内で当パネルに対する優先順位が変化し予算が制限されたことによって、運営のあり方を見直す必要に迫られている。そこで、2000年5月に開かれた第32回共同会議では改革委員会を設置し、パネルの効率化と強化を図り、技術変化に柔軟に対応できる組織作りを目指すことになった。現在の運営に関わる一切を評価し、2000年11月後半をめどに日米両国間で意見を交換することとなった。 改革の重点は2つある。第1に、専門委員会を再検討・再評価し、その数を削減すること。第2に、共同パネルそのものを見直し、運営の効率化と事務局の削減を検討すること。また、共同会議および現地視察の機関を半分に短縮し、通 訳の削減、対応分野の変更も検討されている。改革委員会は11月に行われる会議で両国の合意を取り付け、2001年早々にパネルの承認を求めることとなる。その後12〜18ヶ月の移行期間を経て改革達成を目指すこととなった。
| ||
| |
